
岩津航『レトリックの戦場 加藤周一とフランス文学』書影
2022年1月26日(水)、岩津航氏(金沢大学人間社会研究域)の新著『レトリックの戦場――加藤周一とフランス文学』(丸善出版、2021年11月)の公開合評会が、「加藤周一おしゃべりの会・羊の談話室」(仮称)との共催によりオンライン開催された。
同会は、名称が確定していないことからもわかるように結成まもない組織で、三浦信孝・半田侑子・片岡大右の3人を発起人として2021年夏に立ち上げられたばかりだ。加藤周一に関心を抱く研究者間の、とはいえいわゆる「研究会」よりも気軽な議論と情報交換の場を志向する集まりとして非公開の会を重ねる一方、21年12月4日(加藤の命日のイブに当たる)に「加藤周一と21世紀の社会主義? 戦後日本思想と現代」と題する最初の公開オンラインイベントを開催しており(講演者:片岡大右)、本合評会は、公開イベントの第2の試みとなる。以下、片岡が登壇者のひとりとして開催報告を行う。

伊達聖伸氏
司会の伊達聖伸氏(東京大学大学院総合文化研究科)は本合評会の始まりに当たり、鷲巣力氏の著書『加藤周一はいかにして「加藤周一」となったか』(2018年)に言及した。長く平凡社で加藤周一の担当編集者を務め、その没後に立命館大学の加藤周一文庫開設に尽力した鷲巣氏(現在、同大学加藤周一現代思想研究センター顧問)の著作は『羊の歌』読解の試みであるが、表題に示されたこの問いをフランス文学との関係に的を絞って探究し、豊かな成果を上げた著作として、伊達氏は岩津氏の新刊を紹介した。
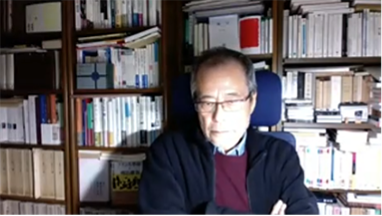
三浦信孝氏
最初に報告した三浦信孝氏(中央大学名誉教授・日仏会館顧問)はまず、岩津氏(1975年生まれ)の研究を、加藤(1919~2008年)の孫世代に当たる相対的な若手によってなされた例外的な仕事として祝福した。三浦氏はまた、岩津氏の研究・関心領域の驚くべき広さを強調し、プルースト研究から出発しつつも福永武彦の比較文学的研究に進み、多様な翻訳の傍らルーマニア出身のシオランやバンジャマン・フォンダーヌ、イラリエ・ヴォロンカをも論じるという広角的な仕事と並行して加藤論に取り組んだ事実を、「非専門化の専門家」を自称した加藤の研究にはふさわしいことであると評した。
1945年生まれの三浦氏が加藤を真剣に読みだしたのは遅く、ベルリンの壁崩壊とフランス革命200周年を経た1990年代になってからのことだけれど、その際に支えとしたのは、加藤とそれぞれのやり方でつながり、同じ1934年生まれの、海老坂武、樋口陽一、大江健三郎、西川長夫の4氏だったという。ただし彼ら「1934年生まれの世代」のうち西川氏は、1988年に自ら立命館大学に招聘した加藤を欧化と日本回帰の問題を考える比較文化論の先達として仰ぎつつも、その仕事に両義的な眼差しを注いでいたと三浦氏は指摘する。西川氏は初期の評論「日本におけるフランス――マチネ・ポエティク論」(1967年)では欧化主義の極として加藤を批判していたし、アジア重視のポストコロニアル思想に傾いた90年代には、加藤のヨーロッパ中心主義の限界を強調するようになった。
続けて三浦氏は、同じ1934年生まれの人類学者、川田順造氏にとって、加藤は(三浦氏によれば、川田氏の「文化の三角測量」のアイディアは加藤の仕事に通じるものを持っているにもかかわらず)アカデミックな評価の対象ではなくジャーナリスティックな評論家とみなされるにとどまったこと、若干年少のフランス文学研究者、二宮正之氏(1938年生まれ)や、三浦氏と同世代の比較文学研究者、大久保喬樹氏(1946年生まれ)が加藤の仕事にしかるべき敬意を払わなかったことを確認したうえで、以後の大学人がおおむね加藤の冷遇に傾いたことを惜しんだ。
フランス文学研究の分野について言えば、「象徴主義的風土」(初出1947年)は東大仏文の学生だった渡邊守章、阿部良雄、菅野昭正、清水徹といった諸氏に大きなインパクトを与えたものの、それぞれのクローデル、ボードレール、マラルメ、ヴァレリーの精緻な研究によって、加藤の論は乗り越えられた先達者の仕事とみなされるようになった。加藤がフランスから帰った1950年代後半以後、フランス文学論をほとんど書かなくなったことも大きいだろうが、彼が論じた対象自体、ロマン・ロランは読まれなくなり、ジャン=リシャール・ブロックやジャン・ゲエノは忘れ去られてしまう。また若い研究者世代の関心がブランショやバタイユ、さらにはフーコー、デリダ、ドゥルーズといった哲学者に移ったこともあり、サルトル止まりだった加藤は顧みられなくなったと三浦氏は述べ、こうした状況を「加藤周一の孤立」と表現した。
そんななか、海老坂氏(『戦後思想の模索――森有正、加藤周一を読む』1981年、『加藤周一』2013年)に続き、その関西学院大学での教え子である岩津氏が著した新たな研究では、加藤が読んできたフランス文学の諸著作が精読され、加藤がそれぞれの作家になぜ、どのように注目したのか、それぞれの作家から何を引き出したのかが、フランスの時代状況と加藤が抱える問題関心に照らし、時系列に沿って明らかにされている。『加藤周一著作集』『加藤周一自選集』所収作品であっても初出主義を心がけ、さらには多くの未収録著作に当たっている点も重要だ。ヴァレリー研究から出発した三浦氏は、岩津氏がデビュー直後の加藤の理性重視を強調しつつ、それをヴァレリー解釈にも結びつけているのには異論があるとしつつも、学術書としては薄手の『レトリックの戦場』の濃密な成果を称えた。

半田侑子氏
第2の報告を担当した半田侑子氏(立命館大学加藤周一現代思想研究センター)は冒頭で、岩津氏の著書によって加藤の初期著作の暗黙の典拠のひとつを教えられたことを感謝した。『1946・文学的考察』(1947年)所収「知識人の任務」を締めくくる、「優れた、しかし少数の知識人にとって、任務はただ一つ、嘗て人類の教師がティベリアドの湖畔に叫んだ如く、来れ、我に従えと、云う以外にあろうか」という一文は、これまで唐突なものと感じられなくもなかったのだけれど、『レトリックの戦場』を読むことで、この文がジャン=リシャール・ブロックの言い回しを踏まえたものだと知ることができたというのだ。ブロックが1931年に国際連盟の招待講演で行った知識人への呼びかけに倣い、加藤は戦後日本の知識人に向けて訴えたのだった。
岩津氏が戦後数年間の著作における言及を重視するブロックは、加藤が1937年から1942年にかけて記した「青春ノート」においても大きな位置を締めている。加藤周一文庫において加藤の未公開資料の整理に従事してきた半田氏は、岩津氏の著書が新たな光を当てた論壇・文壇デビュー後の加藤の仕事を、終戦以前の修行時代からの連続性において捉えなおすべく、この「青春ノート」の世界へと聴き手を誘った(なおその抜粋は半田氏と鷲巣力氏の共編で、人文書院より刊行されている)。
岩津氏が著書の表題とした「レトリックの戦場」という言葉は、「青春ノート」VI「覚書」(1939年10月3日)の一節から取られている。この「覚書」では、ジイドやヴァレリーが参照されながらも、冒頭では小林秀雄が引かれ、日本という東アジアの一国で、日本語で創作することへの決意が表明されている。「日本語で詩はかけぬとさえ誰かの云ったレトリックの戦場で僕は之から戦おうと思う」。「レトリック」という言葉は、同じ「青春ノート」VIの「立原道造論序」(1940年2月12日)にも見られる。半田氏は、芥川―堀―立原という師弟関係を論じた中村真一郎を参照し、「東京の下町生れで、その文学的傾向は西欧文学と我が古典との融合を目指した」(中村『芥川・堀・立原の文学と生』1980年)とされるこの3人から連なる系譜のなかに加藤を位置づけて、彼は1950年代半ばに定式化することになる「雑種文化」のなかを、青春期においてすでに生きていたのだと示唆した。
このことは、対米開戦後の加藤が、「レトリックの戦場」での戦いをいかに戦ったのかを見ても明らかだという。太平洋戦争開戦前夜から、「青春ノート」には詩の実作がほとんど見られなくなり、代わって評論や随筆が圧倒的に多くなるけれど、半田氏によればこの事実は加藤が詩や小説に見切りをつけたことを意味するのではなく、死の切迫感のなかの思考を言葉にしようというこうした努力もまた、1939年に宣言した時に自ら予想したのとは異なったかたちで、「レトリックの戦場」での戦いを実践したものとみなすことができる。やがて開始される「マチネ・ポエティク」の活動がとりわけ範としたのは、フランス象徴詩だった。無謀な戦争を遂行し日本の古典文芸の精神を歪曲する国家に反対しながらも、自らの生きる意味を求めてのことだ。
戦中の経験は、加藤に「日本的なるものへの呪詛」(樋口陽一「加藤周一は「洋学紳士」か、それとも「日本人論」者か?」『加藤周一を21世紀に引き継ぐために』2020年)を唱えさせることにもなった。けれども、「青春ノート」VIIIでは対米開戦前夜に源実朝の『金槐和歌集』が論じられており、このノートは『1946・文学的考察』所収の「金槐集に就いて」の原型とみなしうること、さらにまた、実朝の師である藤原定家を西欧の現代文学との関わりで論じた「藤原定家――『拾遺愚草』の象徴主義」を1946年に発表していることなどを思えば、加藤の文学的旅路は当初から、西欧の文芸と日本の伝統詩歌が同居するなかで歩まれていたと考えるべきだろう。岩津氏の『レトリックの戦場』は、こうした大きな枠組みのなかで、加藤周一がフランス文学をいかに読んだかを詳しく分析することによって、加藤の歩んだ道筋をたどりなおそうとする読者の視界に明かりを灯してくれる著作だと半田氏は結論づけた。

片岡大右氏
最後に報告した片岡大右(批評家)は、まずは丸山眞男と加藤周一という時に並び称される2人の知識人の死後の受容状況が、とりわけ大学という場ではむしろかなりの程度非対称的であることを確認した。姜尚中氏はかつて、「加藤さんほど、洋の東西を問わずいろいろな大学で教えながら、しかしアカデミズムの住人ではなかった人は、なかなか探すのが難しいのではないか」と評したけれど(菅野昭正編『知の巨匠 加藤周一』2011年)、東京帝国大学医学部に学んだ元内科医でありながら「非専門化の専門家」を志し、多様な領域にまたがる言論活動を展開した加藤が、そのためにかえって、大学におけるどの分野の専門家からも扱いかねる存在となってきたことは否定しがたい。
こうした現状を思うと、終戦後間もない時期の加藤が医師業の傍ら文系の一分野、すなわちフランス文学の事実上の専門家のように振る舞い、一般読者に歓迎されるばかりか、東大仏文科の院生たちを始めとする未来の研究者にも真の影響力を行使していた事実には驚くべきものがある。とはいえ、学問的インパクトを与えた仕事は「象徴主義的風土」に代表される象徴主義重視の文学史観に立つものにほぼ限定されており、また今日の一般読者の多くにとっては、この分野の加藤の仕事としてはサルトル紹介の功績が記憶されているにとどまるだろう。岩津氏の『レトリックの戦場』の意義はなにより、三浦・半田両氏も触れたブロックへの言及を始め、今日では――しばしば論じられた対象ともども――半ば忘れられた仕事を含む加藤のフランス文学論の全容を視野に収めて、それらの論考の持つ意味を、対象となった作品を読み込んだうえで探究することで、多くの発見をもたらしている点にある。
そうした発見のひとつとして、1940年代後半の加藤のフランス文学論が、理性重視を基調とするあまりに、しばしば参照元の文脈に無頓着になっていることの指摘を挙げることができるとして、片岡はいくつかの例を紹介した。ここでは1点だけ取り上げよう。加藤はジャン=リシャール・ブロックのエッセイに拠りつつ「我々も亦、我々のマンドリンを持っている」(『1946・文学的考察』所収)を著し、戦後日本が旧弊な伝統を打破して合理性重視の表現へと向かうことを望んだ。ところがブロック自身は、同胞に向けて「デカルトの遺産の愚直な礼賛とも、礼節とも簡潔さとも、縁を切ろうではないか」と呼びかけ、古典主義的均整への志向を克服することで民衆の現実に近づくことを唱えていたのだった。
こうした啓発的な指摘を通して、岩津氏は加藤の初期の理性重視の姿勢を強調する。片岡はそのことを評価しつつも、合理主義的志向は若き日の加藤においてもその一面をなしていたにすぎないとして、同じブロックからの、同じく本来の趣旨に反する別の引用を取り上げた。「青春ノート」VIII「鴎外・ブロック・ポール・ヴァレリー」(1941年)の加藤は、ブロックから「思考のアナーキー」という言葉を引いている。ブロックにとってこの言葉は、新しい世俗的な信仰の共有によって乗り越えられるべき思考の混乱状況であるにすぎない。ところが加藤はそれを、デカルトやヴァレリーのタブラ・ラサの経験、すなわちあらゆる思考を可能にする潜在的な環境を指し示すために用いているのだ。文脈に無頓着な引用という点では同じでも、方向性は正反対であって、これら2つの例を比べることでわかるのは、加藤が最初から、理性的秩序への志向性と同時に、それを支える潜在的な、より豊かな何かへの関心を抱いていたということだろう。したがって加藤の思想を論じるにあたっては、展開と同時に連続性を見ていく必要があると片岡は主張した。
最後に片岡は、加藤のシュルレアリスム評価の問題を取り上げた。『抵抗の文学』(1951年)においては、シュルレアリスムから出発したアラゴンのような詩人が、レジスタンスに参加するなかで、民衆にもわかりやすい詩を書くようになったことが高く評価される。文学者・知識人と民衆の両者が共有しているはずの理性への信頼が、晦渋ならざる詩への志向性を帰結しているわけだけれど、日本の現代詩におけるシュルレアリスムの影響の大きさを思えば、この文学運動に対する加藤の扱いは、例外的なまでに冷淡だと言える。そのことをどのように評価すべきかはともかく、こうしたわかりやすさへの志向は、理性を分有する人びとからなる集合性の希求の一側面であり、「レトリックの戦場」で戦うという課題との関係で捉える必要があるだろうと片岡は結んだ。

岩津航氏
続いて岩津氏が著者としての応答を行った。自分にとって今回の著作は、福永武彦やジョゼフ・チャプスキやバンジャマン・フォンダーヌに関する仕事とともに、「外国人にとってのフランス文学」という問題関心の一環をなしている。デビュー当時の加藤は、医師でありながらフランス文学を読む理由を、それが「役に立つ」からだと述べていた。では、どのように役立てたのか。フランス文学者としての加藤周一をめぐる回想はいくつかあっても、詳細な研究はまだ少ない。海老坂武『加藤周一』も、初期のフランス文学論については軽く触れているにとどまる。先陣を切って論じることで、加藤のフランス文学理解の変遷を描き出すことにはある程度成功したのではないかと考えていると岩津氏は述べた。
加藤のシュルレアリスムに対する「感度のなさ」を改めて取り上げつつ、岩津氏は、加藤はこの文学運動の試みを理解しつつも、無意識を重んじ理性から離れていくという方向性への警戒があったのだろうと指摘した。同じように、加藤は文明や文化といった理念を尊重し、原始的なものへの接近といった主題にも関心を示さなかったという。理性の軽視こそが軍国主義のプロパガンダの成功要因だとみなす加藤は、文学においては知的な方法論の自覚を説き、マチネ・ポエティクで自ら押韻詩の実験を行った。その一方、理性の共有の主題は、すでにその行使のすべを心得ている知識人が大衆を教えるという啓蒙の身振りを導き出す。けれどもそうした「上から」の姿勢の限界――知識人の孤独を帰結せずにはいない――を加藤自身も自覚することから、文学者が自ら危険に身を晒しつつ大衆と言葉を分かち合うというレジスタンス文学の経験に感動し、その紹介を行ったのだろう。
そのように説いたのち、岩津氏は、3人の報告者によって強調されなかった論点として、コミュニスムとの関係という課題を、カトリックへの並行的な関心ともども取り上げた。「神を信じたものも――信じなかったものも」で始まるアラゴンの詩(「薔薇と木犀草」)に典型的に見られるように、両者はレジスタンスの経験のなかで結びついていたが、加藤はさらに、当時のカトリックの労働問題への取り組みにも大いに注目し、さかんに論じており、こうしたカトリック左派の運動への関心が、サルトルの無神論的実存主義に接近する際の下地となっていたようにも思われる。こうした点からすると、フランス留学を経た1950年代後半に加藤が最初期の紹介者となったシモーヌ・ヴェイユについて、工場労働の証言的価値を重視する一方、彼女のカトリック的側面への関心が感じられないのは不思議だと岩津氏は述べた。
『レトリックの戦場』では加藤の小説を批評として読むという姿勢を採用したが、この点で岩津氏は、「香港逃避」(1956年)や『神幸祭』(1959年)への言及を含む片岡の研究(「非ヘーゲル的な夕暮れへの招待」、前掲『加藤周一を21世紀に引き継ぐために』)からヒントを得たのだという。加藤という作家の思想を論じる上で、フィクションとノンフィクションの区別にとらわれずに読むというこうした姿勢は、非フィクション的なものも文学だと言い続けた加藤自身に通じるものでもあるが、日本では両者は分けて論じられがちだ。加藤の小説作品は必ずしも傑作ではないが、その時々の批評の問題意識と照らし合わせた時に意味が出てくる。こうした観点に立つことで、『羊の歌』――雑誌掲載時は「連載小説」と称されていた――をそれまでの小説の集大成として読むこともできる、という仮説を示すことができた。
最後に岩津氏は、伊達氏が冒頭で触れた「加藤周一はいかにして「加藤周一」となったか」という鷲巣力氏の命題に立ち返った。フランス文学だけが加藤を構成する柱ではなく、例えば美術、例えば社会主義といったテーマについても初期からの変遷を跡づけることができるはずだ。そうした読解を総合することで、加藤周一の全貌が見えてくるのではないか。自分の研究がその礎のひとつになることができたら、と岩津氏は締めくくった。
総合討議の時間はそれほど残されなかったが、そこでも意義深い議論がなされた。ここでは、半田氏が加藤の創作の自伝的性格を強調しつつ、彼が鴎外の史伝を将来の新たな小説形式の模範とみなしていたことに言及し、その実践として中村真一郎の作品を示唆したこと、三浦氏が、「青春ノート」の加藤がヴァレリーを「アナーキー」の主題との関係で論じていたという片岡の指摘に関し、ヴァレリー自身が両大戦間期に残した手記『純粋および応用アナーキー原理』(恒川邦夫訳、筑摩書房)を紹介したこと、片岡が、ヴェイユのカトリック性への加藤の無関心をめぐる岩津氏の問いに応答し、労働条件の変わりがたさを前提に美的感情による救済を説くという彼女のヴィジョンが、コミュニスムとカトリックを集合性構築の課題において結びつけるという加藤の関心から外れていた可能性を示唆したことを取り上げておくにとどめる。
視聴者からの応答としては、シュルレアリスムに対する無理解という論点に関し、それを加藤の文学観における「決定的な問題点」とみなす澤田直氏のコメント(それは文学の有用性、という岩津氏が強調した論点の意義にも関わる)、また、加藤は精神の外在化という発想で造形芸術を捉えていたように思われるが(岩津氏の著書で大聖堂の記述に関して指摘されているように)、それは加藤の文学観にも当てはまるのかという宮代康丈氏の問いかけがあった。
精神とその外在化という発想をめぐる宮代氏の問いは、事後に同氏が補足されたように、ロマン主義の問題と関わっている。片岡が以前指摘し(「1950年前後の加藤周一――ロマン主義的風土の探究と日本的近代の展望(上)」2015年)、岩津氏の著書でも多少とも言及されているように、ヴァレリーを範として戦前に象徴主義重視の文学史観を形成した加藤は、留学直前の数年間にロマン主義の再評価を試みていた。
この点を含め、本合評会で展開できなかった主題は数多い。とりわけ、事前の「概要」で加藤が「東アジアとりわけ中国との歴史的関わりを重視し、晩年には東北アジア諸国を結ぶ共同体構築を展望していた」ことを指摘し、「フランス文学史の枠組みの参照と中国の文化伝統の重視が交錯する」という『日本文学史序説』(1975-80年)の眼目に言及していながら、岩津氏の著書でも取り上げられたこの論点を議論できなかったことは、東アジア藝文書院という場を考えるならいっそう惜しまれる。それでも、限られた時間のなか、いくつもの重要な問題に光が当てられる充実した会となったことを喜びたい。
報告者:片岡大右(批評家、東京大学非常勤講師)








