この講義が、東アジア教養学「世界歴史と東アジアIII」を銘打つ以上、竹内好はいつか必ず取りあげる必要があると考えていた。しかし、日本の宗教学からフランスにフィールドを移した私のような人間にとって、竹内は遠くに見えてしまう存在でもあった。戦時中に回教研究所の研究員だったことは知っていたが、丸山眞男や加藤周一や鶴見俊輔のような戦後を代表する知識人と比べても、明示的な宗教論が少ない印象は否めない。とはいえ、彼が論じたアジア主義において仏教は重要な位置を占めるし、イスラームを取りあげた研究もある(臼杵陽「竹内好のイスラム観」安丸良夫・喜安朗編『戦後知の可能性』所収)。たんに私が読む機会を設けることを怠ってきただけかもしれないし、宗教を入り口にしなければという観念に囚われすぎていたかもしれない。
竹内好のパーソナリティーは単純ではない。優等生であることに疑問を抱き、東京府立一中から大阪高校に進んだが、「ねたみ」の感情から自由だったわけではない。東大支那文学科に入った1931年に満州事変が起き、翌年初めて中国を訪れた。「自分たちに近い生活」をしている人間が「隣の国」にいるのに、その「心の中に入っていくことができない」ことを問題だと考えた。1934年に「中国文学研究会」を結成した竹内の目には、伝統的な「漢学」は守旧的で、当時の「支那学」には主体性が欠けていると映っていたから、「文学」は重みのある言葉だった。日本のエリートが欧米を留学先に選ぶなかで、竹内は中国を選択した。1937年7月中旬に出発を予定していたところ、7月7日に盧溝橋事件が起き、日中両軍の衝突が拡大した。一時保留となった留学許可が下りると、友人・武田泰淳の出征を見送った翌日に自分も中国へと向かった。日中戦争下の中国で2年を過ごした彼は中国人に同情していたが、日本人である自分がそのことを中国人に表明するのは躊躇われた。1941年12月8日に大東亜戦争がはじまると、竹内はこれを支持した。強大なアメリカには譲歩しながら中国には大きな態度を取ってきた日本が、欧米に立ち向かう姿勢を示したのを評価したのである。しかしそれは国策への同調ではなかった。戦中の日本文学報国会に、竹内の中国文学研究会は参加しなかった。戦争終結後もすんなり戦後の世界に入っていくのではなかった。戦前・戦中からの連続性のなかに身を置いてもがいた。日米安保と日中国交回復は両立しないと考えた竹内は1960年安保に反対し、強行採決に抗議して勤めていた都立大を辞職した。そのことを知った鶴見俊輔も東工大助教授を辞めている。
『日本とアジア』(ちくま学芸文庫、1993年)は、『竹内好評論集』第3巻として1966年に刊行された同じ題名の本を文庫化したもので、重要な論考が多く含まれる一方、重複する議論もある。文庫本としては重量級で、わずか1、2回の授業で所収論文をすべて網羅するのは難しい。受講生には、第III部に位置し最後を飾る「方法としてのアジア」からはじめて第I部の巻頭論文「中国の近代と日本の近代」へと進み、第II部に収められた重要論文「近代の超克」と「日本のアジア主義」にも目を通しておくように、あとはそれぞれ気になったところを読んだらよいと案内しておいた。
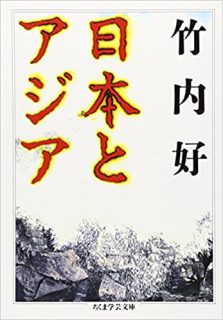
竹内好『日本とアジア』(ちくま学芸文庫、1993年)。
*
「方法としてのアジア」は1960年安保の最中の講演をもとにしている。「敗戦」が「研究上の転機」と語る竹内は、「日本の歴史がどこで間違ったかを探ることから出発」すべきと述べつつ、「日本人は中国に負けたという実感がない」ことを問題視している。「後進国における近代化の過程に二つ以上の型があるのでは」と述べる彼は、西洋・日本・中国の「三本立」で日本の近代化を考察するよう提唱する。竹内の見るところ、日本の近代化は西欧の型をそのまま外から持ち込んでいるのに対し、中国の近代化は「民族的なもの」を中心に打ち出して来ることになった。そこに「近代化が純粋になり得る」ポイントがあったと彼は見ている。「西欧的な優れた文化価値を、より大規模に実現するために、西洋をもう一度東洋によって包み直す、逆に西洋自身をこちらから変革する、この文化的な巻返し、あるいは価値の上の巻返しによって普遍性をつくり出す。東洋の力が西洋の生み出した普遍的な価値をより高めるために西洋を変革する」。西洋の普遍をそのまま受け入れるのではなく、それに対置されるものから巻き返すことで、その価値を高めること。「その巻き返す時に、自分の中に独自なものがなければならない」。それが日本にあるかと竹内は問うている。
「中国の近代と日本の近代――魯迅を手がかりとして」(1948)において、竹内は「抵抗を通じて、東洋は自己を近代化した」と書いている。日本社会における前近代性の残滓を批判したのが丸山眞男だとすれば、竹内好の批判のポイントは日本の近代化には抵抗の契機が弱いということである。「日本は、近代への転回点において、ヨーロッパにたいして決定的な劣勢意識をもった。(それは日本文化の優秀さがそうさせたのだ。) それから猛然としてヨーロッパを追いかけはじめた。自分がヨーロッパになること、よりよくヨーロッパになることが脱却の道であると観念された。つまり自分がドレイの主人になることでドレイから脱却しようとした」。このために「進歩と見えるものが同時にダラク」ともなった。「優勢感と劣勢感の並存という主体性を欠いたドレイ感情」が習い性ともなった。
竹内好の「近代の超克」(1959)を簡潔にまとめるのは容易ではないが、ここでも「抵抗の契機」がキーワードで、「ある状況の下における抵抗と屈服はほとんど紙一重」と書かれていることは見逃せない。抵抗か屈服かを判定して賞賛と断罪で二分する態度ではなく、抵抗と屈服が紙一重であるような地点に「思想の創造作用」を求めて、あえて火中の栗を拾う身振りを竹内がしたことは、押さえておく必要があるだろう。
「日本のアジア主義」(1963)も『現代日本思想大系』第9巻「アジア主義」の解説として書かれた重厚な論稿だが、日清戦争までは「小国」と目されていた日本が圧倒的な「大国」である清を破って大国化していく過程で、通常は「左」と目されることの多い自由民権運動から、「左」の社会主義も出てくる一方、「右」へと流れ込んでいく動きも出てきて、結局アジア主義が「右」から回収されてしまうという論点が重要だろう。第1に、宮崎滔天の「非侵略的なアジア主義」の「心情」が岡倉天心の持つ「普遍性」を備えた「アジア」の「思想」に昇華しなかったこと。第2に、ルソー主義者の中江兆民と玄洋社の頭山満のあいだには交友があったが、日露戦争に際して、兆民の弟子の幸徳秋水は社会主義の立場から非戦論を唱えたのに対し、玄洋社は民権論から国権論に転じており、頭山の弟子の内田良平は主戦論を唱えたこと。竹内の『日本とアジア』が自分の研究のスタートにあると言う中島岳志が的確に把握するように、「宮崎滔天と岡倉天心の出会い損ね」と「内田良平と幸徳秋水の出会い損ね」という「二つの出会い損ね」が、日本における「思想としてのアジア主義」の成熟と「抵抗としてのアジア主義」の連帯を妨げ、「政略としてのアジア主義」を帰結させてしまったと言えるだろう(『アジア主義』)。

中島岳志『アジア主義——その先の近代へ』(潮出版社、2014年)。
*
欧米ではなく中国を見て、しかも多分に中国を理想化しながら日本を批判的に考えるという竹内好の議論と思想の方法は、その後の中国と日本および日中関係の展開に照らすと、時代の刻印を受けた議論のほうは、そのままの形ではなかなか使いにくい。それでも再検討に値する論点が多く含まれているのは、彼の方法上の態度に今でも十分に学ぶべきものがあることと関係しているのではないか。
西洋の学問に依拠してきた近代日本において、竹内は借り物ではない思想を自分の頭で考えようとした。この「方法」は並大抵のことではないわけで、デカルトの『方法序説』を思わせる。実際、竹内自身、「私は昔から、カント流の範疇的思考が苦手で、カオスから出発して何度でもカオスに立ちもどるデカルトの流儀に魅力を感じていた」と述べている。
竹内好が「方法」に意識的だったことは間違いない。鶴見俊輔は『竹内好——ある方法の伝記』において、竹内が「掙扎」(そうさつ)という「方法」を魯迅に見出したことに着目している。「掙扎chêng-chaという中国語は、がまんする、堪える、もがく、などの意味」で、「魯迅精神を解く手がかりとして重要」な概念であり、日本語に訳すなら「抵抗」に近い(竹内好『魯迅』)。孫歌の指摘にしたがえば、竹内は魯迅が言う「掙扎」の検討を通して、「抵抗」の意味を「外向き」から「内向き」に鍛え直した。それは「他者に内在しながら他者を否定する」と同時に「自己のなかに他者が入ることによって自己を否定する」プロセスであって、「主体が他者のなかで行う自己選択」である(『竹内好という問い』)。
竹内が「方法としてのアジア」で、西洋が生み出した普遍性を、東洋の側から巻き返してその価値を高めると言ったのも、このことだろう。近代西洋の普遍が、侵略的な植民地主義とも結びついていたことは否定すべくもない。それに対して侵略される側が「外向き」の抵抗を示したことは当然だが、抵抗を「内向き」にすることで、身悶えしながら普遍の意味をより実質的にする道があることを、竹内は示しているのだと思われる。
溝口雄三(1932〜2010)は『方法としての中国』(1989)において、自分たち「戦中・戦後育ちの中国研究者」は竹内好の「中国の近代と日本の近代」に大きな影響を受けて、中国に対しては「批判的視点」を持つよりも「憧憬」を抱いてきたが、毛沢東の文化大革命以来はそれまでの中国認識を改めて「つきはなして見る」ようになったと述べている。それまでの中国学には、「世界」を「方法」として「中国」を「目的」とするところがあったという。それは、マルクス主義的な世界史像の枠組みのなかに中国を位置づける説明の試みと言ってもよいだろう。それに対し、「中国を方法とするということは、世界を目的とするということである」。それが可能になったのは、中国も西洋も日本も、さらにはその他の地域も構成要素のひとつとするような、多元的世界像が説得力を持つ前提が構築されてきたからである。
*

三浦信孝・福井憲彦編『フランス革命と明治維新』(白水社、2018年)。
多元的世界像が前提となれば比較の仕方も変わる。竹内好は「中国の近代と日本の近代」において、「明治維新を成功させた日本の文化の優秀さが問題だ」と書いた。日本では進歩主義の力が強く、反動の力は弱かった。反動の根が絶たれたとき、「革命そのものの根」も同時に絶たれた。それに対して中国では、反動の力は大きかった。「それが、革命を下へ下へ追いやり、底の人民のあいだに根をはらせた」。フランス革命からロシア革命を経て中華人民共和国の成立へというモデルでは、明治維新を革命と呼ぶことには躊躇がつきまとう。少なくとも辛亥革命のほうが明治維新よりも革命として徹底しているという見方に傾く。
これに対して三谷博は、明治維新はあれほどの大きな変化にもかかわらず、世界のさまざまな革命と比べて犠牲者数が顕著に少なかったことに注目している。フランス革命やロシア革命をモデルとして出発するのではなく、明治維新から相対的に暴力の少ない革命というひとつのモデルを立ちあげ、そこから世界の革命との比較へと道を拓いている。近世日本は260余りの小さな国が2人の君主を戴く「双頭・連邦」体制で、その複合的構造は不整合を抱えており、革命が生じやすく、比較的スムーズな解体再編が起こった。これに対して、中国の政治組織は整合性が高く、革命後の権力闘争が長く続いたと三谷は指摘する。
渡辺浩は、アリストクラシーの時代から「境遇の平等」を特徴とするデモクラシーの時代へという歴史の大きな流れを見ていたトクヴィルの議論を手がかりに、仏日中の革命の特徴を論じ直している。通常、トクヴィルが論じた「デモクラシーに特有の専制」は米国の観察から将来を予見して述べたものとされるが、渡辺はトクヴィルが同時代の中国を「デモクラティックな社会」と見なしていたことをテクストから掘り起こしている。それをもとにまとめ直すと、フランスでは社会がアリストクラシーで政治が絶対王政だったが、1789年以降は政治と社会のデモクラシー化が同時に追求されて混乱が長引いた。日本ではアリストクラシーの社会と連邦制の政治だったところに「革命」が起き、形式上2つあった連邦制の頂点が1つにまとめられて中央集権化が進むとともに、世襲身分制度がほぼ廃止されてデモクラシー化が進んだ。中国では、もともと社会がデモクラシーで政治が中央集権的な専制だった。そうしたところで皇帝のいない新たな政治体制の建設が模索されたが、外国の干渉や侵略もあってうまくいかず、共産党支配が確立した(三浦信孝・福井憲彦編『フランス革命と明治維新』)。
日本と中国の近代および革命についての解釈は、竹内好の世代と三谷博・渡辺浩の世代とでは大いに異なっており、正反対と言ってもよいほどである。しかし、西洋からの借り物をモデルとはしない「方法」の精神は、しっかりと受け継がれているのではないだろうか。
*

竹内好『日本とアジア』からは、日本の近代化には抵抗が少ないというテーゼ、また日本に遅れて近代化のプロセスに入った中国やアジアの抵抗のほうが本物ではないかというテーゼを引き出すことができる。受講生のS・Nさんは、その点を踏まえつつ、日本にも活用可能な「遅れ」や「抵抗」があるのではと問題提起した。竹内は「敗北感のないこと」が問題だと述べたが、S・Nさんは「敗者」とは「自分が『子ども』の位置にいることに気づかない子ども」であるのに対して「弟子」とは「自分が『子ども』の位置にいることに気づいた子ども」であると区別した内田樹の議論を紹介しながら(『他者と死者――ラカンによるレヴィナス』)、「弟子」の位置に身を置いて自覚的に「遅れた」立場を取るやり方もあるはずと述べた。内田樹は『日本辺境論』でも、文明の辺境にいる者は学習効率がよいと指摘している。また、折口信夫について研究しているS・Nさんは、折口の言う「もどき」には「真似る」のほかにも「反対する」「批難する」「からかう」「説明する」などの意味があり、一見ドレイの位置にある者が、模倣を通して主人より多くのものを引き出す可能性があると指摘した。思い出したのは、加藤典洋『日本の無思想』の最後に出てくる「もどき」と「べしみ」で、権威を笠に着る中央の役人は地方の田舎者に「蔑視」の視線を注ぐかもしれないが、制圧された側も相手に取り合わない「べしみ」で応じるという、無力ながら「最後の抵抗の拠点」を持つことができる。「もどき」にも「屈従的抵抗」の姿勢があると加藤は言う。
授業の事前読書箇所には指定していなかったが、「戦争責任について」など戦争体験に関する第II部の諸論文を読んできた参加者も複数いた。私の世代もそうだが学生たちはなおのこと、過去の戦争の記憶と体験を自分のものとすることはなかなかできない。テッサ・モーリス−スズキを読んで「連累」という考えを学んだというN・Mさんは、敵国人を殺害したのは自分(たちの世代)ではないけれど、記憶の風化に加担する言動には責任が生じてくると述べた。「連累」(implication)という言葉を用いて、モーリス−スズキは「あとから来た世代も過去の出来事と深く結びついている」と述べている(『過去は死なない——メディア・記憶・歴史』)。K・Mさんはそれを受けて、直接的な体験を持たなくても、累積する歴史の襞(pli)のなかに分け入り自分を置いてみることですねと応じた。それは竹内が魯迅から学んだ「掙扎」という内向きの抵抗とほとんど同じものなのではないだろうか。「中国の近代と日本の近代」でも竹内は、敗北はむしろ敗北の事実を忘れることによって決定的になることから、「敗北を忘れることにたいする抵抗」を説いていた。
報告者:伊達聖伸(総合文化研究科)








