「柳田の思想は、一言でいえば、「小さきもの」の価値を見いだすことである」。そう喝破する柄谷行人によって柳田国男のテクストが編まれているのがこの本である(文春学藝ライブラリー、2014年)。柳田自身も『小さき者の声』(1933年)という本を編んでいるが、彼のコーパスは広大で、「小さきもの」というテーマが柳田の核心をなすということは、必ずしも自明の共通了解ではあるまい。「小さきもの」に注目する観点からこの民俗学者を読むことは、当代きっての思想家・柄谷行人のいわばお墨付きで、柳田国男をその「可能性の中心」において読むことである。この本は、「小国論」の観点から柳田にアプローチするに際しても、ひとつの最良の入り口になりうる。
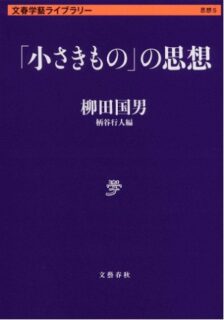
私は、1990年代から2000年代にかけて学部生・大学院生時代を過ごした。当時のひとつのトレンドは、系譜学的な手法で学問の政治性を問い直すことであった。私自身も、特に磯前順一の影響を受け、日本の宗教学の創始者・姉崎正治にせよ、フランスの宗教学にせよ、この学問が帯びていた政治的な意味について考えるよう促された。民俗学の状況に通じていたわけではないが、柳田国男について言えば、少なくとも傍目には、村井紀の『南島イデオロギーの発生——柳田国男と植民地主義』が有力な研究と映っていた。沖縄に「原日本」を見る柳田は、日韓併合に関与した自分を隠蔽しているのであり、その民俗学の成立には植民地主義が影を落としているという議論は説得力があると思った。
また、柳田のキャリアを見ると、初期には狩猟採集民の山人についても論じたが、次第にそこから常民へと関心の中心を移していき、一国民俗学を作りあげたように見える。
だが、そうではないと柄谷は言う。1974年に「マルクスその可能性の中心」と並行して「柳田国男試論」と「柳田国男の神」を書き、1986年には常民=稲作農民を中心とすると見られていた柳田民俗学批判の向こうを張って「柳田国男論」を書いた批評家は——この3篇はインスクリプトから『柳田国男論』として2013年に出ている——、『「小さきもの」の思想』を編むのと並行して『遊動論――柳田国男と山人』(文春新書、2014年)を著し、柳田が山人に対する関心を手放したことはなかったと主張する。また柄谷は、柳田の一国民俗学は内閉的なナショナリズムではなく、むしろ満州事変以降の時代状況に抵抗するものであったと評価する。実際、日本の国家と資本が膨張して「脱領域性、多様性、遊動性を唱導した時期」には「東亜新秩序」を裏づける「比較民俗学」が要請されていたのであり、柳田は「それに背を向け」て「一国民俗学」を唱えたのである。このような柳田の姿勢は、1910年代に小日本主義を唱え、大国主義化する日本に警鐘を鳴らした三浦鉄太郎や石橋湛山の系譜に連なる。
しかも柳田は、日本を均質的な小国とは見なしていない。柳田が単一民族説に与したことはない。「山人考」でも、「現在の我々日本国民が、数多の種族の混成だということは、実はまだ完全には立証せられたわけでもないようでありますが、私の研究はそれをすでに動かぬ通説となったものとして、すなわちこれを発足点と致します」と述べている。柳田の民俗学にはマイノリティや地域的多様性への関心がある。
しかし、それは地域の独自性を即時的に肯定して称揚するものではなかった。「最初から自分の地方の変っていることを見つけようとし、ないしは未熟なる独断をもって女房や眷属のような自分を信じてくれる者に講釈していい気になっているようでは、地方主義は有害です。真の地方主義は事実を確かめること、そうして結局はどこにも飛び抜けて珍らしいことはないという結論に行くつもりでなくては駄目です」(「東北と郷土研究」『東北の土俗』)。
東北のみならず、沖縄についても、同様の眼差しが感じられるのが次の一文である。「沖縄の有識階級に属する人々は、いかなる瞬間も中央の文化の恩恵が、孤島の端々に及ぶこと遍からずして、時運が彼等を後に取り残して進みつつあるのではないかを、気遣わざる時とてはないのである。しかも他の一方には、沖縄の中部日本に対する関係と、いたってよく似た外様関係をもって、沖縄自身に従属するさらに小なる孤島あることを忘れんとし、また往々にしてこれを取り残してひとり進もうとしたのである」(「南島研究の現状」『青年と学問』)。
沖縄が日本の中央から差別されていることに柳田は敏感である。しかし、沖縄本島と周辺の島々のあいだにも同様の差別があることを彼の目は見逃していない。また、そこから差別されている側も実は差別をしているというありきたりの結論を引き出して満足するわけでもない。むしろ次のような可能性を語るのである。
「ゆえに今もし沖縄の学者たちが、一たびこの大小孤島の比較に徹底して、一方には目下自分たちの知友親族等の悩み患うるところのものは、以前年久しく微小なる諸属島が、痛烈に味わっていたところの不幸と同じものであったことを知り、さらに他の一方にはそれがまた、この日本という島帝国全体の、行く行くまさに陥らんとするところの惨状であるべきを覚って、自ら憐むとともに同種国民のためにも悲しみかつ思い、よく病源を探り治術の要点を見出すことに率先したならば、彼等の学問の光は一朝にして国の光となり、ついには人間界の最も大なる希望も、これに伴うて成長するにちがいない」(同上)。
ここには、韓国の歴史学者・白永瑞が言う「核心現場」の経験からもうひとつの普遍に至るための道筋が示されている。
帝国主義の論理のもとに置かれた小国や小さな島を、普遍的な観点からとらえることを柳田が学んだのは、1921年から1923年にかけて国際連盟常設委任統治委員会の初代日本人委員としてジュネーヴに赴任したときであった。このとき柳田は、ジュネーブ大学の講義を聴講するとともにヨーロッパ各地を訪れ、当時の欧米人文社会科学の最先端の学問に触れた。マリノフスキーやボアズらの民族学・文化人類学、またデュルケム学派からも大きな刺激を受けた(川田稔『柳田国男——知と社会構造の全貌』)。それは日本に戻って民俗学を開くに際してひとつの方法になったことは間違いないだろう。ただ、いわゆる民俗学者や社会学者とは異なるアナトール・フランスを柳田が愛読していたことも考慮に入れたい。
柳田は、自分が一番影響を受けた外国の本は、アナトール・フランスであると語っている(中野重治との対談「文学・学問・政治」)。渡欧の際にもフランス語の稽古にだいぶ読んだと言っている。「時々日本人としてこれは心得ていいと思うようなことを言っています」と述べて、「言葉は土の中から生まれた。言葉を知らなければ土と人間の関係はわからない」という言葉を紹介している。アナトール・フランスの『白き石の上にて』は、西洋で黄禍論が語られていたとき、黄色人種は禍をもたらそうとしてわざわざ西洋にやってきたわけではなく、そもそも長いあいだ白禍に苦しめられてきたのだという国際関係における収奪関係についての洞察を示している。ここからたとえば和辻哲郎は、「日本が世界史的にきわめて鮮やかにはっきりした意味を持つこと」を理解したと言うのだが、柳田の場合は、西洋に日本を対置するというより、収奪されてきた側も収奪する側に回りうることを認識し、そのような負の連鎖を避けるためにはどのように身を振るのがよいのかというところまで、きちんと感覚が届いているように思われる。
女性への視点にしても、柳田はセクシュアリティに関する議論を避けているとも言われるが、たとえば鹿野政直は次のように述べている。「民俗学は、既存の学問では例外的といっていいほど、対象としても担い手としても、女性を視野にいれてきた学問でした。〔……〕女性への民俗学の深い関心は、日本におけるその創始者である柳田國男に、すでによくあらわれています」(『婦人・女性・おんな——女性史の問い』)。
宗教についても柳田は、氏神を信じることによって、国家神道を批判するという論理を掴み出している。理性的な近代からは排除される幽冥談にしても、「僕はもっと根本にはいって困って来たる所を研究しようという傾きを有っている」と述べて、経験のリアリティを捨てずに取っておこうとする。
宗教学・宗教研究は、このような柳田の姿勢に学ぶことができる。それは、古びた宗教学ではなく、むしろ来るべき宗教学の在り処を示唆しているのではないだろうか。1873年生まれの姉崎正治と1875年生まれの柳田国男は同時代人だが、宗教学者の柳川啓一は1987年の著書で「二人の具体的な交流の事実をいまだ確かめられないでいる」と述べている(『祭りと儀礼の宗教学』)。今ではほとんど読まれなくなった姉崎正治と今なお読まれ続けている柳田国男を「官の科学・野の科学」と対比し、後者を価値づけるような柳川の振る舞いは宗教学者としては韜晦しているところがあるが、今から100年前の1920年代初頭、姉崎と柳田はジュネーヴの国際連盟で平和構築のための努力をしていた。そのような観点から、柳田のみならず、姉崎やこの時代にアプローチする宗教学研究があってもよいのではないかと思われる。
以上、報告者:伊達聖伸(総合文化研究科教授)

*
【受講者からの感想】
柳田國男の「小さきもの」たちへの視線は、明治という外向きの時代を背景にした時、ある種時代に逆行する印象を与えるものであるかもしれない。しかしながら、「小さきもの」たちを眼差すそのあり方には、近代化の大波によって押し流されようとしているものたちを救おうとする確かな決意と、同時に、徐々に寄る辺を失いつつあったものたちへの慈しみとが共存していたと言ってよい。アンソロジーの編者である柄谷行人によれば、柳田國男にとって「小さきもの」とは文字通りに小さな存在、すなわち子供ということであったけれども、実際の子供にとどまらず、誰かの庇護を必要とする弱きものはみな柳田にとっては「小さきもの」であったのではないか。彼にとって「子供」という小さな存在が守るべきであったのは、7歳までは神のうち、と呼ばれた弱くも尊き存在である「子供」が、ある意味彼の「固有信仰」を支えていたためではないかとさえ思えてくる。
あるいはまた、この世間に寄る辺なく、どうにも進退極まって山に逃れた人々や、衝動的に山に入り込んでしまう人々も、彼にとっては「小さきもの」であったに違いない。そうした存在を救うということは、しかしながら金銭的・物質的援助を行うということではない。『遠野物語』を見れば明らかなように、彼が行ったのは、「小さきものたち」の存在を記憶に留めるという作業である。渡欧経験もある明治の国際人であった柳田が、近代化の波濤の抑え難く不可避であること、そして「小さきもの」たちがいずれ消えてゆく運命にあることを分かっていなかったはずはない。とすれば彼がなし得る抵抗は、「小さきもの」たちが確かにいたという痕跡を、できる限り生き生きと残すことにあったと言えるのではないだろうか。
このように柳田の営みを捉えたとき、思い起こされたのはカズオ・イシグロの言葉である。彼はあるところで、「記憶とは死に対する部分的な勝利である」と述べたが、まさに柳田の営みは、間もなく消えんとする者たちを記憶に留めることで彼らを「生かそう」とするものであり、「小さきもの」たちの救いがあるとすれば、彼らが完全な死から逃れる術があるとすれば、それはこのような仕方をおいては他にない。であればこそ、柳田國男の民俗学なる営みは、「小さきもの」たちに捧げられた祈りであったように思われるのである。
(以上、K・M)
*
柳田国男が民俗学に多大な影響を与えたのはもちろんのこと、その影響は他の学問分野にも及んでいる。『遠野物語』を「日本民俗学の発祥の記念塔ともいうべき名高い名著」といい、「私は永年これを文学として読んできた」と述べているのは、あの三島由紀夫だ。特にその『遠野物語』の序文については、「殊に何回よみ返したかわからない」、「名文であるのみではなく、氏の若き日の抒情と哀傷がにじんでいる」と、文学的に柳田の文章の魅力を語っている。
三島がこの小論で次のように述べていることは、注目すべきだろう。「そういえば、『遠野物語』には、無数の死がそっけなく語られている。民俗学はその発祥からして屍臭の漂う学問であった。死と共同体にぬきにして、伝承を語ることはできない。このことは、近代現代文学の本質的孤立に深い衝撃を与えるのである」(三島由紀夫「柳田国男『遠野物語』——名著再発見」『三島由紀夫全集第三十四巻』新潮社、1976年)。
ここで、「近現代文学の本質的孤立」とは何を意味しているだろうか。本文ではそれ以上に敷衍されることはない。上記の引用の直前で、吉本隆明の『共同幻想論』から「『遠野物語』の新しい読み方を教えられた」とあり、その本文も引用されているため、それらを踏まえて考えるべきだろうが、ここでは措く。
もっぱら受講生としての私の関心に引き寄せるならば、この授業で今まで読んだうちの2冊、有島武郎『或る女』と林芙美子『浮雲』が、まさに三島のいう「近現代文学」に相当する作品だった。振り返れば、二つの作品を扱った際には、「越境」という観点で議論したこともあったと記憶している。他方で、「共同体」というワードにあまり焦点が当たらなかったようにも思われる。むしろ、授業の最初に扱った内村鑑三『余はいかにしてキリスト信徒となりしか』では、「共同体」が主要なテーマの一つであった。
そうすると、三島は我々受講生がこれまで読んできた作品に、『遠野物語』を通して新たな読みの視座を提示してくれた、と感じるのである。内村は三島の視野には入っていなかったかもしれないが、内村も含めて、「死と共同体」という観点から再検討する試みは有意義なのではないか。そうすることで、「近現代文学の本質的孤立」の感触も掴めてくるのかもしれない。
また、柳田を扱った2回目の授業では、柄谷行人が柳田のテクストを通して「共同体」へ注目していることを指摘してくれた受講生がいた。柄谷が「山人」に求めようとしたのは、その到来が予見不可能な交換様式Dの未来だった。つまり、「共同体」というテーマは未来にも開かれている。
昨年、原本遠野物語編集委員会編『原本遠野物語 柳田國男自筆』(岩波書店)が出版され、講談社学術文庫からも今年8月に『遠野物語 全訳注』(新谷尚紀)が出版されるようだ。110年以上も読み継がれ、さらにまた次なる世代へと受け継がれようとしている。過去の読みを引き受けつつ、また新たな読みを見つけていくこと。連綿と続くそうした営みの先端に自分自身を位置付けてみることで、読みの可能性は過去にも未来にも開かれていく。過去の強靭な読み手の足元にも及ばない私は、普段はいま目の前にある文章の解釈に必死だが、たまにはそうして視野を広げてみるのも良いだろう。
(以上、S・K)








