2025年7月12日(土)14時より、第46回東アジア仏典講読会がハイブリッド形式にて開催された。今回は柳幹康氏(東京大学東洋文化研究所准教授)と小川隆氏(駒澤大学教授)が発表を行った。当日は対面で14名、オンラインで延べ21名が参加した。

柳幹康氏の発表に先立ち、現在東京大学東洋文化研究所の訪問研究員として滞在しているLaurent Van Cutsem氏が、柳幹康氏の発表で取り上げられる『天聖広灯録』(1029年)をはじめとする禅宗史書について、簡潔な文献学的説明を提示した。Laurent Van Cutsem氏は、Ghent Universityでの博士論文において『祖堂集』の書籍の成立について研究し、当時の必要に応じて『祖堂集』、『宝林伝』、『景徳傳燈録』、『天聖広灯録』(金蔵本・毘盧蔵本)などに収録された禅僧たちの伝記内容の先後関係について考察を行った。Laurent Van Cutsem氏によると、文献間の比較のみならず、同一文献の版本間の比較も有効であるという。

発表者の柳幹康氏は近年、『景徳伝灯録』『天聖広灯録』『建中靖国続灯録』『聯灯会要』『嘉泰普灯録』と、それをまとめた『五灯会元』という禅宗歴史書(灯史)に関する研究に取り組んでいる。各史書が持つ特徴を明確に解明し、これまで無作為に参照されてきた禅宗の歴史叙述がいかなる史観に基づいて書かれたかを把握する重要な作業である。「歴史叙述の歴史」に関する研究といえよう。柳氏の研究により、各史書をいかに扱うべきかに対する感度が向上し、今後の禅宗史研究に新たな地平が開かれることが期待される。
柳氏の発表では、臨済宗の流れで初めて編まれた灯史である『天聖広灯録』のうち、臨済宗の歴史を詠んだ綱宗頌の内容を検討した。綱宗頌は84字で構成された短い詩に過ぎないが、著者が属した当時の臨済宗の視点を含む歴史観を一目で示しており、『天聖広灯録』に現れた禅宗史観を把握する上で重要な手がかりとなる。
検討においては、動詞としての「出」を“いだす“と読むか、“いづ“と読むかなどの文字単位での読み方から、従来の灯史の法脈観と比較して『天聖広灯録』で具体的に何が変わったのかという灯史全体における『天聖広灯録』の位置づけの問題まで、多様な次元での議論が行われた。
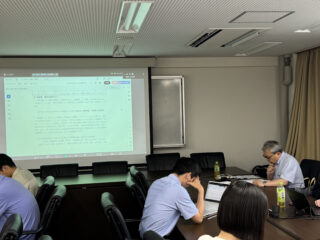
小川隆氏は、本研究会において数回にわたって検討を重ねている『大慧普覚禅師宗門武庫』の訳注原稿を発表した。今回は顒華厳および富鄭公・司馬温公の逸話が紹介された。小川氏の原稿は、いつものように現代語訳、原文、語釈の順で構成されていたが、語釈に原文がそのまま含まれており、語釈を上から順に読むだけで全体の内容が自然に理解できる読者に親切な構造となっている。語釈は原文、現代語訳、そして各単語の説明とその根拠となる原文の引用で構成される。
内容中、富鄭公と司馬温公が洛陽招提寺の住持の座に就く修顒(顒華厳)を迎えに行ったところ、修顒の数十の荷物が運ばれているのを見て司馬温公が失望して帰る場面が取り上げられた。小川氏は関連する二つの研究を紹介した。一つ目は土屋太祐氏の著書『北宋禅宗思想及其淵源』(巴蜀書社、2008年)であり、今回講読した逸話を北宋期における雲門宗の「貴族化」の傾向を示す事例として引き、この傾向により雲門宗は士大夫層の支持を失い衰退したと分析している。二つ目はジョン・マクレー氏の『虚構ゆえの真実:新中国禅宗史』(大蔵出版、2012年)であり、152頁においてジャン・ナティエの文を引用し、仏教の衰退は単純に反仏教的な君主の弾圧によるものではなく、仏教教団が過剰な物質的成功を享受したことに起因するものであり、僧侶が世俗的な成功を収めることは、そうした精神の喪失を意味するのであると論じている。このような小川氏の補足説明は、単に文献を正確に読解することを超えて、当該内容をより大きな議論の場へと引き出し、仏教全体を改めて顧みさせる、卓越した叙述方式であろう。

今回の研究会で印象深かったのは、柳氏の発表において、版本の差異について多くの議論が行われたことである。一般人が仏教を見る視点とは異なり、学問としての仏教学では文献学的方法論を極めて重視する。仏教学においては、内容の意味や内容の事実性を考える前に、その材料となる記述自体をまず検証する。一次文献において実際に何が書かれており、何が書かれていないのか、そして書かれているとすればどこに書かれており、それは文献によってどのように変化していくかを把握する。叙述内容自体に没頭してその価値を問う前に、その叙述がいかなる性質を持つかをまず正確に把握する作業である。戦に出て一撃を加える前に甲冑と武器を研ぎ澄ます過程のようなものであろうか。しかしこれは、関連する全ての文献を網羅して細心に読み比較しなければならない、時として至難(または退屈)とさえ感じられる作業である。学習を進めるうちに、この前段階が際限なく続くこともある。しかしそのような作業を行うことこそが実証的で確実な基盤を築く作業であり、学問を業とする学者の良心が懸かった事柄であり、より発展的な議論の方向性を提示できる作業でもある。そのため、単なるコラムニストではなく学者となるためには、背景知識(先行研究)、原文読解能力はもちろん、文献学的素養も必要であるということになる。本会で行われた版本に関する議論を通じて、このような文献学の重要性を改めて自覚する良い機会となった。
報告者:宋東奎(EAAリサーチ・アシスタント)








