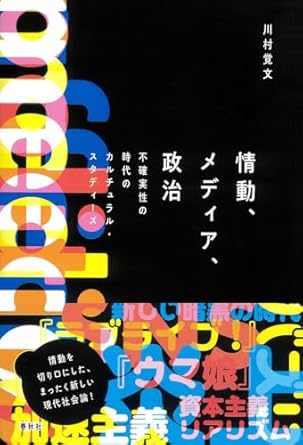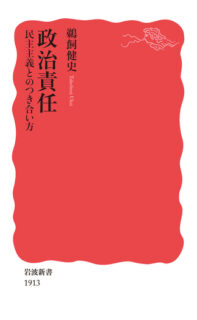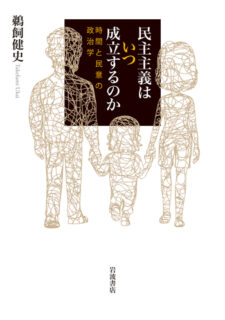川村覚文『情動、メディア、政治―不確実性の時代のカルチュラル・スタディーズ』公開書評会
去る2025年1月25日(土)、東京大学東洋文化研究所にて14時から3時間に亘って、川村覚文氏のご高著『情動、メディア、政治———不確実性の時代のカルチュラル・スタディーズ』公開書評会を開催しました。
著者の川村覚文氏(大妻女子大学准教授)のほか、評者として鵜飼健史氏(西南学院大学教授)、須川亜紀子氏(横浜国立大学教授)にご登壇頂き、司会を崎濱紗奈(EAA特任助教)が務めました。
当日のライブ感あふれる議論の様子をお伝えするため、全文を公開します。
キーワード:情動/政治/カルチュラル・スタディーズ/神経政治学/加速主義/2.5次元文化・ファンダム(『ラブライブ!』『ウマ娘』)/ネット右翼
開会・主旨説明
(崎濱) 皆さまお忙しいところお集まりくださり誠にありがとうございます。本日は川村覚文先生の『情動、メディア、政治——不確実性の時代のカルチュラル・スタディーズ』(春秋社、2024年)の公開書評会を行いたいと思います。
本日は評者としてお二人の先生をお迎えしております。最初にお話しいただきますのが、政治学がご専門の鵜飼健史先生(西南学院大学)です。続きまして、お二人目の評者はメディア研究がご専門の須川亜紀子先生(横浜国立大学)です。本日は少人数でじっくり議論できる良い機会になるかなと思いますので、リラックスした雰囲気で議論を進めさせていただけましたら幸いです。
最初に主旨説明ということで、なぜこの本の書評会を企画するに至ったかということを簡単に述べさせてください。申し遅れました、私、東アジア藝文書院特任助教の崎濱紗奈と申します。よろしくお願いいたします。私は沖縄の近現代思想史を専門としているのですが、皆さまご存知のように、「沖縄問題」という言葉があります。沖縄問題というと、通常は米軍基地問題が連想されると思うのですが、その淵源を辿ってみると、これは単に基地問題というだけではなく、あらゆる社会・政治・経済・文化課題が複雑に絡み合っていることがわかってくるわけです。
ですが、このような複雑さに向き合わずに、事態を単純化して捉えようとする言説が世の中にはあふれています。例えば基地問題に関して言えば、基地に反対する人々を仮想敵とした、いわゆる「ネット右翼」的な言説が散見されるようになって久しいです。反対に、こうした「ネット右翼」に対して「反知性主義」というレッテルを貼る動きも見られます。しかし、こうした現象の背後で一体何が起こっているのか、丁寧に解きほぐす研究はまだ少ないと言わざるを得ません。単なるレッテル貼りで済ませるのではなく、沖縄をめぐって展開される「ネット右翼」的言説を理解するためにはどうすればよいか。そこで私が出会った概念が「情動」でした。
川村先生のこのご著書は、「情動」を切り口としながら、さまざまな方法論を有機的に組み合わせることによって、現代社会が直面している問題を批判的に分析しておられます。私がこれから沖縄のことを「情動」を切り口に論じるに際して、お手本にしたい一冊です。このような背景から、今回川村覚文をお招きしました。先ほども述べたように、先生のご著書は文化批評理論、フランス現代思想、メディア研究、政治学、など多岐に亘る方法論を参照されています。今日は政治学をご専門にされている鵜飼先生、そしてメディア研究を専門とされている須川先生、それぞれのご専門の見地から見えてくる本書の意義や、今後の可能性についてお話しいただきたく思っております。

鵜飼健史氏(西南学院大学)による書評
(鵜飼) ただ今ご紹介にあずかりました、西南学院大学の鵜飼と申します。よろしくお願いします。一応パワポはありますが、手元に資料を配っていただいたので、このまま座ったままやらせていただくという形にさせていただこうかと思います。

レジュメは全部で3枚ございます。1枚目、冒頭は私の自己紹介的なことが書いてありまして、今朝、九州からはるばる飛行機でやってきたということになります。専門は政治理論で、ここで川村さんとお会いすることになるわけですが、ロンドン大学のゴールドスミス校で私は政治学、彼は社会学で研さんを積んでということで、同じ所に住んでいましたよね。本当に夜を徹して、よくしゃべったという記憶が濃厚にあります。2時、3時までよくしゃべっていて、またいろいろ教えていただいてそれが大きな財産になっています。ゴールドスミス校は一応満期までいたのですけれども、結局、博士論文は母校の一橋大学で出したということです。
この間、『政治責任:民主主義とのつき合い方』(岩波新書、2022年)という著作がありましてということと、本日、関係するところではウィリアム・コノリーの翻訳(『プルーラリズム』岩波書店、2008年)をだいぶ前に出したことがあります。昨日くらいに岩波から広告が出ていたのですけれども、『民主主義はいつ成立するのか』という著作の出版が決まっております(※編集追記:2025年7月にEAAでの公開書評会を開催しました)。また目下新書を準備しており、年齢と観点から現実政治を考えるという内容で、夏ごろには刊行できるのではと考えております。(※編集追記:2025年10月刊行予定)
- 鵜飼健史『政治責任:民主主義とのつき合い方』岩波新書、2022年
- ウィリアム・コノリー『プルーラリズム』杉田敦・鵜飼健史・乙部延剛・五野井郁夫訳、岩波書店、2008年
- 鵜飼健史『民主主義はいつ成立するのか:時間と民意の政治学』岩波書店、2025年
さて自己紹介はこれぐらいにいたしまして、政治学をやっている人間から、川村先生のご高著をどういうふうに読むのかというところで、特徴を4点ぐらい挙げます。
まずはやはり「情動」です。これを理論的に位置付けた著作です。それが本書を多分揺るぎないものとしており、その観点から社会現象等々を論じているというところは、一読して、皆さまはご承知かと思います。さらに私みたいに政治学をやっている人間からすると、政治の領域にこの情動という観点を、どう使っていくのかというあたりを指し示していただいた本で、これが本書の最大の貢献かなと思っています。
二つ目としては、「テクノロジーの位置付け」、あるいは「真理との距離感」というふうに書いてありますが、こういった想定、テクノロジーや真理というような問題の中で政治や社会というものがどのような位置付けにあり得るか。あるいは、民主主義、現状私たちが享受しているとされるような政治体制を、どう評価していくのかという問題に接続できるだろうと考えています。このテーマは実は私も、例えばコロナとかを題材としつつ、この2月に出る本でも一章を割いて論じて、川村先生も言っているようなことを、別の角度から考えております。私の本の該当部分は、オリジナルは中国語です。中国語で初めて書かせていただいて、それを自分で編んだのを翻訳するという作業がある作品です。
三つ目としては、「現代哲学のアプローチ」というところ、よりミクロ的な話に入っていっているわけですが、こういった加速主義等々のテーマというようなものを拾っていかれていて、それを社会・世界との結び付きで論じています。これは完全に現代政治学が見失っている視点かなと思っているところでございまして、この辺の視点を出していただくのは、現状の政治社会を考える上で大変貴重な貢献をされていると思っております。
四つ目はさらに個別の話なのですが、ウィリアム・コノリーの神経政治学(neuropolitics)というものを解釈していただいています。コノリーは確かに政治学、私みたいに政治理論をやっている人間からするとほぼ常識的な知識になってきたのですが、この神経政治学に関してはほとんど誰も言っていないような気がするので、そこを必ずしも政治学がアイデンティティではない川村先生から出していただいたというのは、大きい貢献かなと思っております。あとは、その「宗教的なものの位置付け」というところで、この辺は非常に面白いテーマを拾っていただいていると考えております。

William E. Connolly. Neuropolitics: Thinking, Culture, Speed. Minneapolis: Univ Of Minnesota Press, 2002.
さて、ご高著に対する注文というところでは、これはぜひどうした事情があったのかということを聞いてみたいのですが、画像が欲しいですよね。特に僕みたいなサブカルに対して詳しくない人間からすると、もう少し画像を入れてもよかったのではないか、これは何かもう少し裏事情的なものがあるのか何なのかというあたりとか教えていただきたいです。例えば私の今度出る著作でも、これは政治理論の本ですけど、それでも画像を2個か3個ぐらい使っているので、この辺あえて使わないというあたりはどうしたこだわりなり、お考えがあったのかということをお聞かせいただきたいです。
もうひとつは、ご高著でももちろん触れられているのはいるのですけれども、極右的な政治運動ですよね。ネット上の言説に、どういうふうな切り込みを本書が可能かというところは、川村さんが詳しい兵庫県の状況を考えるならば、そこを押さえておいた方がより現代的な問題とつながるというふうに政治学の人間からすると思います。そことの何か接点があった方がなお良かったのかな、という印象を持ちました。
さて内容に入っていきますが、私は基本的に一章、二章、三章を集中的に読ませていただいておりまして、各章のお話ということを必ずしも順序立ててしゃべるという形ではなくて、まとめることができたものから展開してみたいと思っております。
本書は、第一章につきましては現代社会に対する認識ということが一番マクロ的な形で出ている章だと思います。テクノロジーが高まっていくということと同時に、不確実性が高まるという状態になっていくという図式が示されます。そこにはリスクがはらまれていて、そしてリスクを管理しなければいけないというまた別な要求が出てきて、ただリスク管理はそれ自体が利潤を生むということで資本主義等に含まれるという構図です。場合によってはそれは環境破壊につながるということで、そのテクノロジーというところにまた返ってくるという構図になります。本書ではこれはフーコーの表現を使いながら、「真理陳述の体制」という課題でもあるわけです。
こうした連関から逃れるためには、本書の表現によると、「テクノロジーの諸規則のもとの作動を知り、それを奪用していかなければいけないのだ」という方向性が見られるということです。これは恐らく別の著作で川村先生はかなり言及されている、日本の戦前の国体ですよね、本書では国体への論及はほぼないわけなのですが、そことも何かシンクロがある議論なのかというふうに読ませていただいております。
こういったテクノロジーからリスク管理を巡るような、これは本書にない表現なのですが、ウロボロス的な連関というところの中で自由の可能性、そこに情動というものがどう絡むのかというところを考えてみようという感じの流れになっております。
現状、私たちの社会においては情報が過多という状態になっていて、人間行動の基盤というものが意味から情動というものに移り変わっていっているのだというところが、基本的な認識として示されています。あるいは、昨今さまざまな議論がなされているAIについても、この中で位置付けられているということがありまして、大変勉強になります。
ちょうど2、3日前に中国で死刑判決が出ていましたよね。本書を私が最初に読んだときに、ちょうど深圳の日本人児童の刺殺事件があって、その事件はとても重要だと思うのだけれども、その反応自体にこの川村氏の本を何かひきうつすことができたという印象もあります。あの事件もネットの反応だと「日本人だから刺された」とか、条件反射的にネット言論がバーッと出たわけですよね。こうした状況というのは、まさに情動の反応だということを思わされております。日本人が刺されて、日本人に対する攻撃だというような反応が出るということ自体が、そこまで読み込めるのかというのが普通だと思うのですよ。少なくとも外見的には分からないですし、犯人とされる方のメンタリティも分からないところで、「なぜそんなイデオロギー的な殺人という解釈ができるのか」というあたりは、これなどは根本的な情動的な反応で、考えさせられるところではありました。
これは川村さんの本から書き抜いているところなのですが、「テクノロジーが確実性をもたらしてくれるという期待(幻想)を捨て、・・・世界の不確実性に向き合う」というものが必要であると。情動というものは「前個体的なものである」と表現されていて、「個体はさまざまな潜在性から偶発的に出現をする」と。すなわち「創発」するという存在であると。あるいは、「感情とは位相が異なる」というあたり、このあたりはその情動に対する根本的な認識というものを示していただいていると。情動というものは私なりにそれなりに分かっていたつもりなのですけれども、新たな知見といいますか、政治や社会を考える上での基本的な認識を示していただいているというところです。方向性としては「存在権力」、すなわち「創発」という、権益をのっとるような権力としての存在権力というものに対する抵抗。あるいは、これもフーコーの言葉ですけれども「自己への配慮」というもの、対抗的な存在権力というものをつくるというあたりが、大きな道筋として示されています。
さて、第一章では必ずしもこちらの展開があったわけではないのですが、私みたいに政治学をやっている人間の見地からすれば、不確実性やリスクがあってというところで、政治の場合はそこに権力が出てくるわけです。安全保障とか治安などが出てきて、それがナショナリズムを伴って、ひどい場合には原理主義とか陰謀論というようなものをはらみながら、さらに不確実性を高めるというふうな構図になります。すなわち自由や解放というものを目指すということが、どこの社会も恐らくそうなのだと思いますが、ナショナリズムを引き連れてきて、いっそう抑圧を強めるという連関です。もちろん、これは川村さんが気付かれていないわけではなくて、別の著作では結構言及されているところだと思うのですけれども、本著作では必ずしもメインテーマではなかったということで、私なりに触れておきたいというところです。
さて、こんな感じで第一章をごく簡単にまとめた上で、レジュメの(A)(B)は私の質問になります。まず(A)ですが、不確実性というものは、社会や経済では上述の構図のように展開されていますし、私がお節介にも付け加えたものに、政治の局面でも多分そうだろうというふうに思われます。そこで昨今流行っているのがエピストクラシー(知者支配)というもので、要は、頭がいい人が統治すればいい、大衆にはもうやらせるなという議論が結構あるのですが、それは駄目なのでしょうかというのがまず一つです。逆に言うと、現状のデモクラシーとされる政治状態の方が、不確実性に対応する上で、まだマシというような判断をされているのかなというあたりはいかがでしょうか。
あるいは偶然性・偶発性みたいなものがキーワードになってくるのはもちろんですし、これはそれにどう取り組むのかということが恐らく人文社会科学の一つのテーマだとは思うのですが、それをより実感するという意味でも、くじ引き(ロトクラシー)というのを、私の分野では言う方は結構出てきているのですが、これをどうお考えでしょうか。ちなみにうちの学生に聞いても、くじ引きは評判がよくないのです。やはり選んだという感覚が欲しいし、「一般の民衆のためにくじ引きだ」という言い方を結構されるのだけれども、あまり一般の方はそこまで求めていないところがあったりするのですが、川村先生の議論とこれはどう関わるのかと。このあたりの政治体制的な対応の可能性はありえないのでしょうか。
(B)に関しては、日本の政治・社会の場合には、不確実性をめぐっては相対的にマシなのではないでしょうか。アメリカとかイギリスとか、場合によっては中国・台湾・韓国と比べるとマシなのではないかということすらいえるのかもしれません。この私の認識は間違っているのかもしれません。まずそこの評価というところと、仮にマシだとするならば何が抵抗力になっているとお考えでしょうか。
例えば「真理の位置付け」というところでは、真理が絶対的で、私たちがそこに近づくべきだという感覚をあまり社会的に持っていないのではないでしょうか。そのため、不確実性に対しても、引いた形で見ることができるという特性があるかもしれません。
あとは特に東アジアの方とかとしゃべると、日本には論壇があって羨ましいと言われます。私としてはもちろん、脆弱にはなっているかとは思っております。本書はまさに論壇的な本だと思うのですけれども、論壇がない社会だと学術的な知が社会からむき出しになって、真理自体が武器になってしまうかもしれません。あるいはこれも私は適当に発言しますけど、高齢者の割合が非常に高い日本社会なので、逆にテクノロジー一元論に対しては抵抗の余地があるのではないかという感じすら覚えるわけですけれどもね。
あるいはサブカルが強いというのも、理由になりうるかもしれません。これは適当に言っているわけではなくて、例えばロバート・ダールなどでも、「民主主義の実現において。サブカルが強いのが条件だ」というふうに言っているのですよね。つまり、多元的な民主主義ができるというところでは、文化的な多様性があるということを言っていて、真理への抵抗を担保する条件かもしれません。
二章ですが、これは「神経政治学から情動論へ」というところで、前の議論が続いてくる、より深まっていくという感じの章立てになっています。「感情とは情動によって担保された潜在性の一部が、主観的な意識として表出され現実化されたもの」、情動というのは関係性を生じさせるものであると定義されます。情動は創発のプロセスを生じさせる原理でありつつ、経験そのもの、こういう感じで表現がなされています。ここで代表的な事例として、私が担当したウィリアム・コノリーの翻訳書の部分に言及されていて、その神経政治学という政治学者があまり注目しない議論を拾っていただいているというのがこのパートになります。ここでは「身体と文化との間の多層的なネットワークというのが自由の基盤だ」というコノリーの主張に注目されています。それは内在的な自然主義というものです。分かるような分からないような感じがするのですが、取り急ぎ内容を進めていくと、あとは「非神論的感謝」への言及があります。何か上位規範に対し感謝するのだというのを、そこは神的なものではなくて多分何かあるのでしょう。内発的に生じるような感謝の心みたいなことを言っているのかなと思います。それをだから内面化する必要性があるのだと。情動というものは、間主観的なレベルで働きかけが行われる。本能的な領域というところで個人を形成していきます。コノリーの表現で言うと、それは「生成の政治」だと言うわけです。彼の結論としては、深い多元主義(ディーププルラリズム)というものが求められて、それは思考の創発をもたらすような情動というものに反応した先にあるというか、それが導く当然の結論なのだという言い方ですよね。それは社会における加速化という背景と調和しているのだというみなし方をしています。
さて、私からの疑問ですが、政治学では遅さや熟議という観点から、コノリーの議論に対しては批判がありますが、川村先生はどうお考えでしょうか(C)。その情動の立場、コノリーに完全に賛成することができるのでしょうか。もちろんコノリーの議論が有益だという趣旨で出されているのは間違いないのだけれども、これに対して全面賛成しているのでしょうか、というあたりの距離感のことを伺っているつもりです。私、鵜飼としては多元主義的な時間の導出の方に、コノリーの議論というのは意義があるという気がします。そもそもコノリーの議論に、社会が加速化していくという状況とディーププルラリズムでうまく整合しているのでしょうかという印象はあります。つまり、その加速化が進んでいくと、むしろ私たちの反応はより一元化しませんかというふうな気がするのです。加速化というのはその多元性ということとは必ずしも導くわけではないぐらいのことを私は思っていて、実際2月に出版される本ではそうした議論が展開されている箇所もあります。
二章の後半は、ジョディ・ディーンとジェレミー・ギルバートの議論を下敷きにしながら展開されてくるということで、ディーンの場合にはどちらかというと情動というものは資本主義の枠組みから出られないのではないかという、批判的な立場から議論がされています。たしかに、「女性の活躍」という言説のように、すぐにパッと思いつく事例はあります。
それに対してギルバートの方は、割と肯定的であって情動が共同性とか、そうしたものが導くというふうな原理になり得るのだということで、川村さんの本もどちらかというとギルバート的な集合体、共同性みたいなものを原理として情動というものを考える可能性があるのだということをおっしゃっています。
そのディーン、ギルバートの議論を踏まえた上で、そのためにこの場合には集合性をラディカル化するという方向性、その原理としての情動ということを導き出す本書なのですが、そのために取り組むべき課題や方向性は具体的にどういうことなのでしょうか。つまり、その三章以下の議論というのは基本的に思弁的なお話になっていくので、具体例というのは政治学の立場からするとそこから道が外れていくというような印象を受けるわけですが、あえてこの場で言ってしまうとどういうことが想定できたのでしょうか(D)。例えば福祉政策をやるとか、政治における時間を短縮するとか、脱国家的なナショナリズムの強化とか、政治の参加年齢を引き下げるということによって若い方により参入していってもらって、情動あふれる政治の空間をあちこちにつくるというふうな議論などは考えられないでしょうか。
あと、僕は自分の新書『政治責任』では、例えば党派を超えた不正の感覚あるいはそれとの連帯という事柄に期待しています。たとえば裏金問題や、兵庫県の例の知事の問題とか、最初はこれだったわけですよね。パワハラとかは駄目だという話で、ある意味、情動的な反応だったと思うのだけれども、それが別の情動に今度は塗り替えられていくというところがこの間だと思うのですが、こういった方向性とかこのあたりはどういう解釈が可能でしょうか。
さて、残り10分ほどで第三章のお話をさせていただいて、私の担当のところを終えます。第三章は「加速主義と情動」というタイトルの下、スルニチェクとウィリアムズに左派加速主義の可能性というものの是非を展開されるという章になっておりました。ここでは主に「加速派政治宣言」、これは一応念のためですが、加速化政治に関する宣言です、厳密に言うと。私も最初は誤解していて、加速化の政治宣言だと思ったのですけれども、加速化政治に関する宣言です。危機というものは加速していくという状態の中で、政治は一般的には衰滅する、隠退するというふうに言われていて、これは政治学全般が基本的に問題意識として持っているはずです。にもかかわらず、仕方ないから実証可能な対象の研究とかそういうところばかりやってしまうというのが政治学なのです。そこには大きな問題性があるというふうには個人的にはもちろん思うわけなのですが、こうした状況においては「未来がキャンセルされている」という表現がなされております。そこで求められるのは、加速主義政治あるいはプロメテウス的な政治というものですと。それは資本主義というものを乗り越えるような政治なのですが、自分たちで制御してテクノロジーを加速して資本主義を超えるということが目指される政治です。確かに、そこには政治の出番というものがありそうだなという印象を、私は持ちました。
『未来を発明する』(原題はInventing the Future)の中で、「ハイパースティション」という概念が展開されていて、これは非常に面白い概念で、予測不可能な未来というものを現実化するということ、私たちの動作というか問題設定なわけです。「未来を肯定することにおいて、ユートピアは情動的な調整役として機能するのだ」というふうにまとめ的な言及がなされております。

Nich Srnicek and Alex Williams. Inventing the Future. London: 2015
(E)のところの問題設定を私なりにさせていただきたいのですが、川村さんの本にしたがえば、ここで「未来を発明」するとか、政治の可能性ということとか、テクノロジーをどう超えるのかというところに対して、割と批判の声がメディア研究者や評論家の中には多いようです。しかし、私はここに関してはかなり甘くてその情動的な政治や、この趣旨における未来の発明というものは私は結構、有益な方向性があり得るかなぐらいに思っているのです。ただ、そうした政治はあり得るかもしれないのだけれども、つまりテクノロジーをコントロールする政治というものはあり得るかもしれないのだけれども、「でも、それは民主主義を必然的なものにしなくないですか」という気はするのです。この場合、左派加速主義という、この左派という表現自体が、資本主義に対する対抗という1点のみにあるとするならば、意味としてはちょっと弱くないですか。左派と言ってしまっていいのでしょうかというふうな印象が、このグループに対してはあります。この点はいかがでしょうか(E)。
また、自由を実現する、自由に対する法的な規制というものは、プロメテウス的な政治においては構想外なのでしょうかと。私はたまたま法学部に所属してしまっているので法学の可能性も考えたいのですが、人文系・社会学系の方は法学をちょっとなめている側面があって、やはり法的な規制というのは大切なのではないかなぐらいのことを、ここ5年、10年ぐらい言い始めています。こういう方向は駄目なのでしょうか。そういうことをやってしまうと資本主義にからめとられるということは分かりますが。あるいは、私が使っている民主主義という意味が、ひょっとしてこの方たちが展開される内容とは違っているかもしれません。制度的なレベルで民主主義というものを考えがちな法政治学と、あるいは広範な情動による触発みたいなぐらいのことを、ゆるく民主主義と言えてしまうようなメディア学系の方たちとのひょっとして意味の違いというのがあるのかもしれないな、というところは考えさせられました。
後半のところは基本的に私のような人間から見ると、ほぼラクラウですよね。普遍ということがいろいろあって、それを組み立てましょうみたいな話です。だから、ラクラウの議論みたいなことを、加速主義に対する議論として使われているなという印象がこのグループにはあります。私は別に駄目と言っているわけではなくて、そういった適用ということがあり得るのだなということで勉強させられております。
最後の方になってきて、これは川村さんも言っているわけですが、「コミュニケーション的機会ということによってどうにかなるのだ」というふうにこの『未来を発明する』も言っているのだけれども、ちょっと曖昧だよねということで四章以降ではその辺に対して、かなり具体的な考察というものが深まると。ケーススタディをそのまま拾っていくことになるという流れです。
最後に、私がやっている政治学に引き付けてまとめ直すと、現代政治は一般的に情動が不在ではないのでしょうか、情動があるとしても抑圧されているような管理の場なのではないかという気がするのです。特に私のように普段は田舎で住んでいる人間からすると、政治はそういうものかなという印象すら持ちます。となると、情動があるだけまだマシかなと。例えばそこは国政のレベルであったりとか、都知事選であったりだとか、あるいは兵庫県の事例とか、あるいは先ほど沖縄の話がありますが、沖縄の場合には情動が出まくっている政治状況だと思うのだけど、とはいえ例外ではないか。日本全国的な規模でいうと、政治における情動があふれているというものは、やや例外的かなという印象すらあいます。
となってくると、いわゆるオールドメディアという表現がなされてしまっているような、テレビ・新聞というものは日常の報道を続けていくというのが重要かなと考えます。もちろん国政とか東京、兵庫、沖縄などはやっているわけですが、そうではない地域という所もそうしたものを拾っていくということが多分オールドメディアの仕事かなと感じております。
現実というものを唯一の現実にさせなくて、「可能性の束」、政治学の教科書でよく出ている表現なのですが、その辺で情動というものに関しては考える余地がありそうです。兵庫県などもそれはどういう出方をしたかということはもちろん批判の余地があるのだけれども、その情動というものとつきあうということは、多分21世紀社会においては避けられないかなという印象はオチといいますか、触発されて考えたことということになります。
さて、というふうな形で、私の報告ということで終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
須川亜紀子氏(横浜国立大学)による書評
(須川) 横浜国立大学の須川と申します。本日はよろしくお願いいたします。

私は自己紹介文を作ってこなかったので、鵜飼先生の素晴らしいレジュメを見てドキッとしたのですけれども、まず川村先生との出会いは、2016年ぐらいだったかと思います。共通の知り合いの研究者の方に紹介していただいて、ラブライバーだということを聞いて、「川村先生はラブライバーなんだ」と。ラブライバーは皆さんご存じですかね。『ラブライブ!』のファンの方。なので、川村先生イコールライブライバーというふうに記憶をして、そのときは「はじめまして」という感じだったのですけれども、よくよく聞いてみますと結構共通点や共通の興味がありました。私は元々イギリスのウォーリック大学というところで、映画・テレビジョン学部にいまして、テレビ学で博士号を取っています。そのときの博士論文を基にしたのが、この結構古いのですけれども、『少女と魔法』というこの本でした。そのときは魔法少女アニメと女性の視聴者のviewershipに関してカルチュラル・スタディーズ的に研究して、実際に大人の方々やお子さんたちにインタビューして、実証的なデータとテキスト分析と混ぜて研究をしていました。なので、私の元々の興味は、アニメとオーディエンス研究だったのです。

須川亜紀子『少女と魔法——ガールヒーローはいかに受容されたのか』NTT出版、2013年
その後、オーディエンス研究、ファンの研究という形でファン研究のスカラシップが結構増えてきた中で、「2.5次元」に注目しました。その現象は2000年代初頭からあったのですけれども、隆盛になってきたのは2010年代、ちょうど川村先生とお会いした頃がその『ラブライブ!』のコンサートや、それから2.5次元の舞台というものが結構流行ってきた時代だったので、それで2.5というのが結構キーワードになったときに、単著を書かせていただいたのが『2.5次元文化論』というものです。舞台、キャラクター、ファンダムという形で、ファンダムというものがアカデミアの中で重要になってきていた頃です。今から思うとその走りですね。日本でもファンダム研究というのが学生の間で流行ってきて、私の学生も「自分がファンである、だからファンを研究したい」という形で、卒論や修論などにトピックとして取り上げ始めていたのですけれども、でも当時は方法論が分からないというような感じでした。

須川亜紀子『2.5次元文化論——舞台・キャラクター・ファンダム 』青弓社、2021年
それで、「2.5次元の文化」という形で、大きな枠組みでリアリティとファンタジーの間を行き来するようなコンテンツとファンの実践をプロジェクトとして総括的に研究しようではないかということで立ち上げて、そこに川村先生が参加して下さいました。一緒にシンガポールに行ってファンの人たちに話を聞いたりしたのですが、彼は現地人と間違えられたりして、すっかりシンガポールの人たちとなじみになっているお店などに私たちを連れていってくださって、おいしい料理を紹介してくださったり・・・専門分野は全然ちがうのですけれども、その時いろいろと話をさせていただきました。
『2.5次元学入門』が去年の11月ごろに出版されました。表紙が簡素なのですが、「2.5次元」という用語がそこかしこで聞かれるようになって、今は定着していっているけれども、なかなかその研究書が多くない。何かありきたりなことをずっと言っているような状況がアカデミアの中で続いてしまっていて、それを何とか別の切り口がないかという形で、そのプロジェクトのメンバーを中心に論集を組んで、もちろん川村先生が書いてくださって、なかなかいい本になったのではないかなと思います。まだまだこの分野では「入門」というぐらいですから、これをきっかけにいろいろな研究領域とも接続しながら発展させていきたいなと思っています。

須川亜紀子編『2.5次元学入門』青土社、2024年
ですので、こちらの本も今日の川村先生のこのご単著と接続されていて、詳細版として私はこの本を読ませていただきました。バックグラウンドとしては川村先生とも全く違いますし鵜飼先生とも全く違って、どちらかというとファン研究とかジェンダーの問題などから見たときにどういった気づきがあったのかなということを中心にお話しさせていただきたいと思います。
私は特に四章、五章のサブカルチャーを題材にしている章を基本的に取り上げさせていただきたいです。その背景として13ページに書かれているように情動は前景化しているその状況というのがとても重要だということをまず捉えました。「今日の、電子化されたコミュニケーションネットワークの発展それ自体が、情報のオーバーフローによる再帰性のこれまでにない上昇をもたらす。それによって、『象徴機能の衰退に拍車がかかり、合理的な思考は後景に退き、情動的反応を前景化させる。そしてその結果、コミュニケーションネットワークはプラットフォームを通じて構成される、無限の情動的循環回路となってしまう」ということですね。引用させていただきました。
鵜飼先生も言及されておりますけれども、さらなる不確実性へつながるこの乖離というところに情動が深く関わっているという前提で、第四章の「情動を通じたリアリティの構築とメディアの宗教性」というところを論じたいと思います。『ラブライブ!』と『ウマ娘』です。ポピュラーカルチャーを専門にやっているわれわれとしては非常に身近な問題ですし、トピックとして、実は私のゼミの学生にラブライバーが二人いまして、この話を彼らからずっとされている今日この頃なのですけれども、でもラブライバーだからこそ、当事者すぎて見えないところがあって、ラッキーなことに二人とも大学院に進んでさらに研究を進めるということで、ここは絶対、教科書として取り上げるぞと思って読ませていただきました。
それで、『ラブライブ!』『ウマ娘』のキャラコンサートです。声優さんがキャラクターとしてそのキャラクターを演じるというか、同一化してパフォームするということですね。「そのオーディエンスの情動を触発するものとして、新しい集合性や抵抗の可能性を考えるきっかけになるのではないか」ということで、非常にポジティブにこのラブライバーやウマ娘のファンの方々を捉えています。
ここで押さえておきたいのが宗教的なもの=情動的なものということで、先ほども少し言及されましたけれども、宗教的なもの=個人的な選択以前に集合的なもの、集団的なものである、で「前個体/個人的」とか「横断個体」などという言葉をタラル・アサドから引用されて使っています。そしてまた宗教的なものというのは個人的な意識に先立つ感情、「直感的/内蔵的領域」、これはコノリーの言葉ですけれども、ちょっとリダンダントになりますが、個人性と集合性あるいは横断個体、横断個人性の双方を総括させることを可能にする原理だというふうに押さえておいて、「オタク」の潜在力という話になります。
ここで「『オタク』は情動によって創発可能となった単独的/特異的個人であると同時に、情動的に生産された特定の『リアリティ』を共有する集合性である」というところです。この「リアリティ」という言葉が、ある時期、ポピュラーカルチャーを論じているメディア研究の中では忌避されていた言葉で、何をもってリアリティとするのかというような単純な問いから、リアリティという言葉をあまり使わせないというか使わないようにしていたときがありました。『2.5次元学入門』でも川村先生は私が虚構的身体とか「虚構」という言葉をあえて使っていたところを、実はそれがリアリティなのではないかというふうにまた問い掛けをしてくださって、それが私にとっては新たな気づきでした。リアリティという強い言葉を使って説明されるというのは、何か切り開かれたような思いがしました。そこで情動的に構築されたオルタナティブなリアリティの可能性というものを、川村先生は見ていらっしゃるということです。
ここでマーク・フィッシャーの『資本主義リアリズム』を引用して、「資本主義だけがあらゆる社会的領域を貫通して機能する原理となる」と。「資本主義リアリズムにおいては、あらゆる信念/信仰は経済的な交換価値として商品化されており、それゆえそれらの超越性は完全に失われている」という状況ですね。これはオタクのグッズ集めですとかチケット収集とか、そういったことにも通じると思うのですけれども、それはファン研究の中でも結構、信仰主義ということが問題視されているのです。自由選択として好きだからやっていることが、いつの間にか可視化される数値によって、本当のファンなのか本当のファンではないのかというのを詮議されるような、そういった事態もファンダムの中で起こっていたりしますので、まさにこの状況だなというふうに私は思っていました。

マーク・フィッシャー『資本主義リアリズム』 セバスチャンブロイ・ 河南瑠莉訳、堀之内出版、2018年
またメディアテクノロジー的条件として、スチュアート・ホールの「エンコーディング・デコーディング理論」を再確認・再検討して、ヘゲモニーが明確な場合にその「エンコーディング・デコーディング理論」は有効なのだけれども、今日では特権的なポジションは不在のため、それはもう有効ではないのではないかという問い掛けがあり、それからプロシューマーとしての個人、こちらもしかし意識的な主体的活動としては、なされていないものの比重が大きくなっているということで検索やホームページ訪問のデータによる属性蓄積などというのが事例として挙げられています。
また、「プラットフォーム」による生産と決定です。これは「プラットフォーム資本主義」などと言われていますけれども、「分配的で調節的なシステムによって管理されている」と。今アメリカの状況などを見ますと。政府によってそういったプラットフォームがコントロール、レギュレートされるということの問題点がメディア研究の中で長い議論になっていまして、これからどうなっていくのか、トランプ政権になってそれがまたもっともっとひどくなっていくのか、それともまた別のオルタナティブが出てくるのかということで結構ホットなトピックですけれども、「プラットフォーム」という観点に非常に重要な点を提示していると思います。
その抵抗の可能性ということで、ポスト世俗主義的な資本主義リアリズムと異なるリアリズムを与えてくれる、オルタナティブな対象を内在的に生み出すという試みがあります。このあたりはアニメ研究者やポピュラー文化研究者の中でも、こういったところと接続するのはすごく面白いなというふうに思うのですけれども、トーマス・ラマールという人の『アニメ・マシーン』というのが非常に有名な著書としてありまして、なぜアニメが研究されるのかということで哲学的・思想的なバックグラウンドとしてよく使われるものなのですけれども、ラマールが提示しているアニメ的機械(アニメ・マシーン)は情報の分配的な領域をつくり出すのだと。多平面的なイメージ、これは多分ラマールにとっては、日本のアニメを前提として論じているので、2Dやセルルックを前提としていることなので限定的な論ではあるのですけれども、コンピュータ画面上の複数のウィンドウに近い効果、いわゆる階層がなくてそれぞれ横断的なリンクでつながるという、そういった機械的というかアニメ・マシーンとして考えるということで、結構出版されたときは画期的な論としてメディア文化論の中でもよく使われていました。「プラットフォーム資本主義によって捕捉されない創発の可能性は『情報の分配的な領域』に見出せる」と川村先生は主張していらっしゃいます。

トーマス・ラマール『アニメ・マシーン』藤木秀朗監訳・大﨑晴美訳、名古屋大学出版会、2013年
それからこちらも引用なのですけれども、このジルベール・シモンドンの説明を経て、「オタクの生成」というところが興味深かったと思います。この「オタク」という言葉を用いていますが、オタクとは誰かということはいったん脇において論じられていると思うのですけれども、恐らく男性オタクを前提として考えていらっしゃるのかなとも思いました。情動が創発する「オタク的個体/個人」、さらに「群集としてのオタク」です。「特定のアニメについての同じ情動的経験を共有する集団として生成されるのだ」と論じられています。これはギルバートのものからそういうふうに結論されていますけれども、そのときに『ラブライブ!』シリーズこそ横断的個体性の創造を考える上でとても適切な作品群なのだということで『ラブライブ!』の事例研究になってきます。
ここで『ラブライブ!』のコンサート、声優さんがキャラとしてコスチュームを着て、髪型もほぼほぼ一緒にして、アニメの画を後ろに映してそれと同じようなポーズで踊るということが大体コンサートで行われるのですけれども、外見は全く違うのに声優キャラクターそのものの現前として経験されるのはなぜか、そういうふうに疑問を投げ掛けています。声優キャラクターの声こそが、このような情動的経験を引き起こしているということで声の一致ですね。もちろん声による情動というのはとても重要で、特に『ラブライブ!』の場合は、ほぼ新人であまり色がついていない声優さんがキャストされました。一般に声優さんの声は大体似たような発声をするのですが、例えば男性ではイケメンボイス(イケボ)の声優さんや、女性の声優さんだと、例えばかっこいい系とかかわいい系とか、声で判断するというのがファンの中でも定着しているのですね。『ラブライブ!』の場合はあえてオーディションで新人さんを選んでいるので、あまり他の(声の)データベースで浮上してこないような声優さんの声というのを使っていますので、よりキャラクターとの粘着というのが可能になるのですね。ですからラブライバーにとって、キャラクターの声を発している声優さんがそこにいるというのは、よりキャラクターに近い、キャラクターの同一化が可能になるような、声の情動的経験を引き起こしやすいような状況にもなっています。
ここでB.マッスミの「ムーヴメントヴィジョン」ということを持ち出しています。「動きの中にある視座。個人が動きの中に在るとき、その人は自分自身を他人がその人を見るように見ることができない」ということから、主体/主観、客体/客観の消失というものを導き出して、情動は特定の「ミラーヴィジョン」から生じさせる、つまり情動がどのようにリアリティを生み出すのかということを論じています。
こちらは面白いなと思ったのですけれども、「情動的経験というのはリアリティとフィクションの対立を無化してしまう」ということがあります。ここが2.5次元の理論の中では私が「ハイブリッドリアリティ」と「ハイブリッドファンタジー」という言葉を使って、(元々はメディア研究者の言葉なのですけれども)説明しているところがあるのですが、情動論から見ると対立の無化というふうに論じられるのだなということで、私はここはすごく気づきがありました。
165ページでまた引用しますけれども、「なぜなら、情動とはそもそもそれによって主観/主体と、客観/客体の対立が産出されるものだからだ」ということで、これが触発する情動というのが有効に働くというふうに論じられています。ここで、歌がなくてもインタビューでも情動は触発されるという、恐らく個人的な体験があったと思うのですけれども、ファンにとってはやはり声とキャラクターというのは分かちがたく感じられているので、そういった情動というのはラブライバーにとっては触発されるのだなということがここでよく分かりました。
それで「声優としての身体とキャラクターとしての身体、さらには他のものとしての身体へと変容する潜在性を持つ。情動は、そういった身体を触発してキャラクターとしての身体を創発させる」ということで、声優キャラクターの二重のアイデンティティということがいえるのではないかということを論じられています。このあたりはポピュラー文化を研究している人は、総じてこういったことは体験しておりますので何ら不自然な論ではないのですけれども、それに対して『ウマ娘』に対しては、「情動と偶発性の関係性を考える契機だ」ということで、『ラブライブ!』とは違うまた別の事例であるということをおっしゃっています。私は「ラブライブ!」はいろいろ聞いているのですけれども、『ウマ娘』はそんなに詳しくないので、アニメと若干コンサートを見たぐらいなのですけれども、偶然性ということで驚きの情動があるということです。そういったことでも情動が触発されてさらなる興奮、そして強い情動的リアリティが生み出されるというふうにおっしゃっています。恐らくそれはそうなのだろうなというふうに思います。
ここまで結構いろいろな論と接続されたり、ポピュラー文化に関してポピュラー文化以外の領域から論じたりすることによって『ラブライブ!』や『ウマ娘』、それからその奥にある情動や情動への触発というのが、私やファン研究者などにとってはとても新鮮で非常に興味深いものです。なので、2.5次元論に新しい視座を与えてくれるなということが私の実感でした。ただ、2.5次元空間におけるフィクションとリアリティの混交を「ハイブリッドリアリティ」「ハイブリッドフィクション」と呼んでいますけれども、情動的リアリティはその代替と理解できるのか、全く異なるコンテキストと捉えるのかというのはこちらでははっきり分からなかったので、何か応答があればお願いしたいなと思います。
それから問いとしては、これは本当にアプローチが違うので、全く重箱の隅をつつくような問いかもしれないのですけれども、群集としてのオタクの生成プロセスにジェンダー差はあるのかなというのが率直な問いでした。自分は女性オーディエンスや女性ファンを中心に研究したり実証的なデータを取っていたりしますので、川村さんのその研究では実証的なデータというのは全くありませんので、そもそもアプローチが違うのでこういったことは言及されないのは不自然では全然ないのですけれども、取り上げられたのが次の章でも男性オタク、男性ファンというのを前提に論じられているので、ジェンダー差はあるのかないのか、あるとしたらどうなのか。
実は女性向けとして同じような事例として、『うたの☆プリンスさまっ♪』というのがあります。これは男性アイドルのゲームなのですけれども、それを演じる声優さんが、自分が演じたキャラクターとしてコンサートを行うというのが、古い事例としてあるのですね。その声優さんは、『ラブライブ!』はみんな女性で若い声優さん、若い女性の声をあてているので若干、「外見は全く違うのに」と川村さんはおっしゃるのですけれども、私にとっては外見の差というのはそんなにないなと思っていました。ただ『うたの☆プリンスさまっ♪』の声優さんは、本当に上は40代とかいるので、そういう人たちが若い男性を演じるわけですね。だから、外見はおじさんとして捉えられるのだけれども、声の情動によってそれがノイズにならないというような楽しみ方を女性ファンの方々はされているのですね。それは女性特有なのではないかと私はずっと思っていたので、声が創出する情動というものを考えた場合に、そういったジェンダー差というのはどうなのだろうかというのが一つの問いでした。
また、声優の身体が可視化されない場合の情動の生成について、同じ機能として捉えていいのだろうかというのが、ここから発出された新しい問いだと思います。例えば『あんさんぶるスターズ!!』という、こちらも男性アイドルを育成するようなゲームから発したメディアミックスコンテンツなのですけれども、この『あんさんぶるスターズ!!』は、声優さんがそのキャラクターとしてコンサートを行う「声優ライブ」というのが一つあります。だから『ラブライブ!』とほぼ一緒です。
もう一つは、「3DCGライブ」というのもあります。これは「初音ミク」を想像していただけたら早いのですけれども、まったくのホログラムのライブです。だから、キャラクターがそこにホログラムの身体を持って立っているのですね。それには声優さんが声をあてていますので、声を発していて声を媒介に情動が触発されるというのは同じ機能は機能です。ただし、そこに身体はないのですね、実体としての身体はない。
その他の事例にも『ヒプノシスマイク』というのがあります。『ヒプノシスマイク』というのは、ラップバトルです。ラップをする男性3人組のグループたちが、ラップで戦うというコンセプトで作られたものなのですけれども、こちらはラップをしている、声をあてている声優さんたちのライブがあります。それはあまりキャラクターを意識しないで、特に声でラップの歌を歌って盛り上げるようなライブなのですけれども、もう一つ「3DCGライブ」というのがあって、やはりホログラムなのです。いろいろな人がキャラクターとして出てきて、声をあてているのでしゃべるわけです。しゃべるのですけれども、動いたりツッコミを入れたりとか、あたかも本当にリアルな身体がそこにあるかのような妄想ができるわけなのです。これはどちらも女性ターゲットです。けれども、この『ヒプノシスマイク』や『あんさんぶるスターズ!!』のような3DCGライブは、女性のファンにはすごく受けるのですが、男性に対しての3DCGライブは意外と少ないです。ということはウケないのだろうなというふうに思うと、ではその情動の生成の同じ機能として、ここは差があるのだろうかとか、そのリアルな身体、特に女性声優の身体がそこにない場合の情動の生成というのはどういうことになるのだろうかというのも結構気になりました。
第五章は「海のネットワークと反復あるいは抵抗する情動の政治」で『艦これ(艦隊これくしょん)』『アルペジオ(蒼き鋼のアルペジオ)』『はいふり(ハイスクール・フリート)』というものが取り上げられています。こちらは、多分ナショナル・アイデンティティの問題で、今の第四章とはまた別口のアプローチがなされているなというふうに思いました。
ちょっと時間の関係で少し端折りますけれども、海洋性という問題を論じていらっしゃって、戦時期の日本の海のイデオロギーとか、そういった日本の思想史というのは川村先生は専門のど真ん中だと思いますのでかなり詳細な説明がなされていて、「敗戦によって潰え、忘れ去られる」が「欲動/情動が30年代から40年代にかけてと同じ様に反復される可能性」と、もう一つ、「そのような反復にある意味で抗するようなかたちで情動が触発される可能性の、両方の事態が考えられる」という、その事例として『艦これ』『アルペジオ』『はいふり』が取り上げられていました。『艦これ』『アルペジオ』『はいふり』は、海として継承されるネットワークにおいてキャラクターとして、戦艦のプラットフォームとしては、どのように情動を流出・分配させるべきなのかという問いから『艦これ』がまず取り上げられて、これはアニメのお話をされているのですけれども、元々はゲームです。「深海棲艦」によって侵される海が赤くなっていく。これは「第1期には『艦娘(かんむす)』が勝ち続ける限りにおいて『享楽の盗み』を通じた『享楽』の組織化をフィクショナルに達成するものとして機能しうる」と。同時に「アニメ第二期では、『艦娘(かんむす)』が次々と撃沈する様子が描かれると、逆説的にもリアルな戦争への反発へと情動が強く触発される」というふうにおっしゃっています。
これはアニメですので、それを見た視聴者の感情や情動というものをターゲットにしていると思うのですけれども、それに対して『アルペジオ』『はいふり』というのは、「ネットワークを循環する情動を権力がどのように捕獲するのか、そういった権力への抵抗はいかに可能か」というものを、事例として提示してくれているということです。このあたり、『アルペジオ』と『はいふり』を見るとよく分かると思うのですけれども、全く知らないとちょっと分かりにくいかなというような感じで出してみましたが、ポピュラー文化の研究者たちはもうデフォルトで見ていますし、私も大好きな作品群です。ただ、それぞれちょっと設定は違います『アルペジオ』の方は、『艦これ』と共通している点がありますが、メンタルモデルという戦艦のシンボル的な少女たちが出てきてお茶を飲んで話し合うみたいな、そういった幻想的なシーンが出てきます。『はいふり』の方は高校生たちが戦艦に乗るということですね。だから、少しずつ違う事例を「海」というところで共通して出してくださって、「なるほど、そういった読みができるのかな」というふうに結構興味深かったのですけれども、「キャラクターによって触発されるオタクの情動が、アテンション・エコノミーを通じて、一つの方向へと誘導されることの隠喩なのだ」というふうにおっしゃっているのですが、応答としてはとても興味深くて「海洋性」という視点で捉える。少女が戦艦として表象される『艦これ』『アルペジオ』、それから少女が見習い海兵として戦艦に乗る『はいふり』の分析は非常に興味深かったです。私は多分こういう視点が取れなかったので、これはすごく面白かったなと思って読みました。
それで戦前戦後のナショナル・アイデンティティの形成のコンテキストから考えると、「男性オタクの右傾化」という当時の言説に批判的に応答しているといえるのではないかとここはちょっと読めたので、そういう意味でも興味深かったです。
問いも先ほどと同じで、全くアプローチが違うのでこちらはどういうふうに答えてくださるかなという興味も含めて考えたのですけれども、『艦これ』はゲームですね。やはり「俺の物語」「私の物語」というそれぞれの物語が形成されるわけです。多くの物語の一つ、多くの物語の推しキャラクターの一人という多層的な読みの場合も情動は同じように機能するのだろうか。『艦これ』『はいふり』でも撃沈時は、恐らく男性オタクの方が一枚岩的な情動を触発されるのかな、本当かなというのを、その辺はファン研究の視点から見るとちょっと思います。つまり、多様性ですね。プレーヤーの多様性、ジェンダーや国籍などの差異というのはそのときに見えなくなってしまっているというのがありますので、もちろんそういったアプローチをしていないのでそこまで言及することは必要ないとは思うのですけれども、ポピュラー文化に落とし込んだときにそういった視点も見えてくるなという問いです。
それから、あえてオタクの実践まで見ると3作をきっかけに情動を触発された結果、自衛隊の船、例えば観艦式、それから歴史遺産、帝国海軍の鎮守府跡などは私も大好きなのですけれども、聖地巡礼、いわゆるコンテンツツーリズムというものを行うファンがいると。そういったファンの行為やファンのそういった文化的な参与、コミットメントの抵抗の可能性はあるのだろうか。例えば「はいふり」の場合は実際の土地、横須賀、猿島などが聖地になっています。実際そのアニメの中に出てきたりしますけれども、そういったところで四章でも論じられていた「オルタナティブの抵抗の可能性」というのは、果たしてあるのだろうかというのが問いとして提示したいものでした。
(須川) これもずれると思うのですけれども、時間があればですね。これは多分、全然関係ないかもしれないですけれども、『アルペジオ』や『はいふり』も実はライブをやっていて、『アルペジオ』は「Trident(トライデント)」ですね、声優さんたちがその場限りのグループをつくって歌ったり踊ったりしている。『アルペジオ』の場合は、自衛隊の船の上でプロモーションビデオを撮ったりしてやっていました。それから『はいふり』は「TrySail(トライセイル)」、こちらも演じている声優さんのライブです。そのライブなどでは、『ラブライブ!』のキャラクター、声優キャラコンサート的な情動が喚起されるのであろうか、ファン層が重なるのであろうか。例えば、女性の場合は『刀剣乱舞』とか『あんさんぶるスターズ!!』とかがあるのですけれども、ほぼ重ならないというのがありまして、そのあたりはどうなのか。
それから『アルペジオ』は海上自衛隊のプロモーションDVDがあるのです。『アルペジオ』の声が、海上自衛隊の潜水艦などを紹介するビデオがあるのです。プロモーションをやっているのですよね。『アルペジオ』のアニメには、海上自衛隊が協力していますですので、そういった関係からかもしれないですけれども。あと『はいふり』は自衛隊神奈川協力本部の自衛官募集ポスターに使われています。そのときには結構批判を受けました。ネットワーク的権力に抵抗するパワーとしての情動は、うまく絡みとられているのかな、どうなのかなというのもちょっと余談として考えたいなというふうに思います。例えば、『ガールズ&パンツァー』という陸上自衛隊が協力している、女子高生が戦車に乗って模擬戦をするクラブのお話があって、そのアニメを見て自衛隊に入った少年の事例なども紹介があるのです。結構、情動は危ういなとそのとき思っていたのですけれども、その情動の危うさとはどういうことなのだろうか、あやふやなものだからこそ可能にする別の方向への誘導の潜在性とは何なのだろうかというのが、結構ぐるぐる、本を読んで考えさせられたものでした。
すみません、これは時間があればの話なのですけれども、ありがとうございました(拍手)。
(崎濱) 須川先生、ありがとうございます。いろいろな事例を詳細に紹介くださって、大変興味深く拝聴しました。
では、15分間のコーヒーブレイクを挟みまして、川村先生からの応答、続いて川村先生からの応答に対するお二人の先生方からの応答およびディスカッションということで進めていきたいと思います。ありがとうございます。では、いったん休憩に入ります。
著者・川村覚文氏(大妻女子大学)による応答
(崎濱) では議論を再開したいと思います。早速ですけれども、川村先生に、鵜飼先生そして須川先生からありました議論に応答していただきたいと思います。
(川村) 鵜飼先生、須川先生、ありがとうございました。これは私自身の初の単著で、この書評会を通じて、どういうふうに他の人に読まれるのだろうかということを知りたいと思って本日はやって来ました。若干雑談的な感じで導入をさせていただこうと思うのですが、私は何が専門なのかみたいな話になったりすることがよくあって、その意味でも今日の書評会に期待するところがあります。というのも、例えば鵜飼さんのような本当にガチ政治学の人からすれば、私に対する印象は「いや、あなた、メディアとか文化研究やってる人でしょう」みたいな感じになって、一方で須川さんみたいにきちんとメディア研究をされている人からすると、「いや、あなた、どっちかというと政治学寄りっぽいよね」みたいな感じになってしまうと思うのですね。

自分としては、「理論を重視したカルチュラル・スタディーズです」というのが一番、しっくりくるかなと思っています。というのも、カルチュラル・スタディーズは文化の政治学というように言われていて、もともと学際的かつ理論的な研究も重視していた分野なのだと自分では理解しているためです。おそらく、たとえば政治学をやっている人だと、政治学というディシプリンの中で論文を書いて、そのディシプリンの中だったらこういう感じかなみたいな評価が自分の中でも何となく反省できると思うのです。メディア研究も一緒で、メディア研究の文脈でこんなことをやっているから、こうかなみたいな。でも、僕みたいに割といろいろなものを混ぜて──カルチュラル・スタディーズは、割とそういうところが元々ある分野かなと思うのですが──しまっている場合、どういうふうにみんなからこれを読まれるのか、よく分からないなというか、想像がいまいちつかない、というのが自分自身としてちょっとあったんですね。
ただ、できれば面白いことを書きたいなというのが元々あって、この本も面白い内容にしたいというのはありました。その意味で、自分自身も最も興味あるし、現代のメディア文化の話で、おそらくはより多くの読者の興味を引くであろうと思われる問題を取り上げている、第四章、五章がこの本の一番ヤマだというような感じでこの本は構成されています。そして、それ以外は割と何か前座的な役割が与えられている印象があると思うのですが、それは確かにそういうところはちょっとあるとは思います。この本の各論考は、その元ネタは全部一応ばらばらの時期に書いたもので、それを一冊にするためにいろいろと大幅に書き直したり、書き足したりしてという感じでやりました。そして、この本自体は日本語としては書き下ろしで書いているもので、というのも、元ネタとなっているものですでに発表済みのものは、英語で発表している内容だからです。このようにバラバラな論考を集めたものであるのですが、その割には割とこれは全部通して読まないと、いまいちよく分からない話になっているというところがあるかなとは、ちょっと思います。つまり、私としては一つの問題意識で構成されている本である、という感じではあります。
その上で、今、お二人の先生から書評をしていただいたのですが、本当に疑問はごもっともだなと思うことばかりで、基本的には、この本の一番不足しているのはジェンダー関連の話だと思うのですよね。私はそれを、本のあとがきに不足していますというふうに書こうかどうしようかなとすごく悩んだりもしました。
(川村) だから、実際、須川さんがいろいろとおっしゃったことは本当に、本当にそうだなというところなのですけれども。ただ、やはり情動ということを扱うというところが、これの一つの大きなポイントというのが、一応ジェンダーやセクシャリティにかかわらず使える理屈として情動を練り上げたかったというのが一応あります。というのは、これはジョディ・ディーンの精神分析的な議論などにもつながってくるのですが、情動と欲望は違うというところがあって、性的なものは欲望のところに入ってくるのだとしたら、これは分ける必要があるのではないか、そこをどう考えるべきか、ということをちょっと検討したかったなというのがあるのですね。
例えば男性オタクの議論とかになってくると、やはり著名なものとしては東浩紀、大塚英志、といった人たちの議論があって、特に東浩紀さんの議論では、男性オタクの萌えの問題というのは、男性オタク的な性的欲望と密接につながるという話になっていると理解しています。一方で、これはこの本が大きく依拠している文献の一つであるトーマス・ラマールの議論を考えた場合、そういった話とは違う理路を用意するために、情動理論を提示しているのがラマールさんの『アニメ・マシーン』ではないか、と私は理解しています。ですので、私もそれを意識したというのがあります。ただ、とはいえ、さっき須川さんが提起された問題は、ちょっと僕も考えたいなと思うところがあって、それは後でまた応答として議論させていただきたく思います。
それとは別に、まず鵜飼さんの質問に応答していこうと思うのですけれども、要するに情動というのが、例えばそれが政治的な問題として関わってきた場合に、どういう方向に行くのかという問題ですね。例えばナショナリズムの問題というのが確か第一章のところで触れていたと思うのですけれども、つまり情動というのがそういうナショナリズム的なものを起こすのかという問題ですが、それにはちょっと私は疑問に思っているところがあるのです。というのは、ナショナリズムもある種の欲望の次元にあるのではないかというところがあると思うのですよね。何が言いたいかというと、例えば今のナショナリズムは結局、国民的統合とは全然関係ないように見えるのですね。あまり国民的統合をしようと思っているように見えない、ナショナリズムが。これは鵜飼さんもご存じだと思うのですけれども、山崎望さんが編集された『奇妙なナショナリズムの時代』という著書がありますけれども、あれなんかを読んでいて思うのですが、今はもうナショナリズムがかつてのナショナリズムと違うというところがあると感じるのです。国民的統合を全然目指していないナショナリズムとなっているというところがあって、そしてそこがむしろ情動的なのではないかと私はちょっと思っているところがあります。

山崎望編『奇妙なナショナリズムの時代:排外主義に抗して』岩波書店、2015年
ですので、情動と政治の話でいくと、これも第一章で論じたジョディ・ディーンの議論ですが、結局もともとのナショナリズムというのは、ある種の、みんなが納得する象徴秩序をつくって、そこに向かってみんなで欲望するみたいな話かなと思うのですけれども、いまやナショナリズムはもうそういったものではない、みたいな。情動というのは、もうちょっと、それこそ各自に任せるみたいなものなので、各自に任せるとなってくると、A集団とB集団とC集団と・・・みたいなのがぱぱっと出てくるだけの話であって、それを全部つなぐ原理は不在ですみたいな話なってしまうのではないかというのがあって、それは結局国民統合とはならないのではないかな、と私は思っているのです。ですから、そこが情動の問題でもあり実は可能性でもありうると思ったりしています。
そして、エピストクラシー、ロトクラシーの話なのですが、どうなのですかね。どうなのですかねというか、つまりエピストクラシーは恐らく今の話だったら、要は「AI支配でいいじゃん」みたいな感じになってしまうのではないでしょうか。
(川村) 知者=AIみたいな。だから逆に政治学とかでAI支配とかはどう考えられているのかなということが私には興味深いのですけれども。もちろんプラトンの哲人政治みたいな話がもともと政治思想にはあって、それ以来議論が続いているということなのかもしれませんけれども。あるいは日本の文脈でも例えば吉野作造みたいな人は、要するに民本主義と議会制度というのはエリートが大衆を導くための場所で、それを大衆が意識することによってお互いに啓蒙され合うみたいな話になっているのですね。そういう知者による啓蒙的支配みたいな話は元々あるのですよね、政治学の中では恐らく。エリート支配というか、知者支配みたいなのがいいのだみたいな。
では、AIではないとして、誰が知者なのですかという話になってしまうと思うのですよね。日本だと、知者というと、ひろゆきとか、あるいはホリエモンとかになってしまうのではないかという疑問があるのですけれども。つまり、民主的なものにおいてエピストクラシーをやるのだったら単にポピュリズムに走ってしまうのではないかと思うのです。しかし、それはあまりリアリティがないし、多分政治学の中でもそんなに意味のある話にならないと思うのですよね。そうすると、やはりAI支配みたいな話になるのかなという感じはするのですけれども、エピストクラシーというものを突き詰めていくと。
でもそうすると、結局この議論の範疇で言うと、いや、それは結局不確実なものなのに、確実性というのを僭称しているに過ぎないものに頼っているのではないか、という話になってしまうのではないかというのを思うのです。
あと、ロトクラシーなのですけれども、確かに偶然性に委ねるという意味で、ロトクラシーはエピストクラシーよりよほどいいと思うのですが。ただ、この情動の問題は、一方で集団性をどうするかという問題が結構大きい話で、ロトクラシーはやはり個人を選ぶという話になってしまうから、そういった政治はちょっと違うかな、と。つまり何が言いたいかというと、恐らくここで私が前提としている議論というのは、やはりネオリベ的な状況があって、ネオリベラリズムというのは基本的に全て個人に分化していくわけですよね。さまざまな問題を個人の単位にしていって、そして、その個人が動いた結果、それが何らかの全体性となるのだけれども、その場合の全体性というのはあくまで個人の集合だから、集合として何かがなされるかというと、そういうわけではない。これが多分ネオリベ的なロジックだと思うのですけれども、ロトクラシーはそれにすごく適合してしまうのではないかという疑問があります。そうすると、集合政治みたいな問題にならないわけですよね、これは第二章で論じている議論なのですけれども。そこを考えたら、ロトクラシーは単にネオリベ適合的な議論に過ぎないのではないかと、ちょっと思うというのがあります。というので、ロトクラシーはどうなのでしょう。ロトクラシーは政治学の中で、どの程度の真面目さで主張されているのか、よく分からないので、どの程度真面目に議論されているのかということをむしろ知りたいなというのがあります。
「日本政治・社会の現状は、不確実性への対応をめぐり、相対的にマシにも思われる」という議論ですけれども、これは以前から鵜飼さんは非常によく主張されているというか、二人で話をするとこの話がよく出ると思います。鵜飼さんに誘われたりして、台湾に私はよく行くのですけれども、台湾の政治状況というのはやはりまずいのではないかという話を鵜飼さんはよく言っていて、それは日本との関係におけるポストコロニアルな状況とか、中国の問題とかが背後にあって、台湾はある種切羽詰まっているという話なんですよね、それは。それに比べれば日本は全然安定していて、マシですよという話をよく鵜飼さんはされていて、それはそういうものなのかなと伺ってはいるのですけれども、ただ日本の場合も、どうなのでしょうか。不確実性が「相対的にマシ」というのは、単に保守派の力が強いだけなのではないかという問題もちょっとあるではないかなという気もするのですけれども、つまり、それを保守派と見るのか、あるいは何かうまいことシステムがそういう安定的なものとして機能していると見るのかというのは、もちろん見方の問題はあるとは思うのですけれども、その辺はなかなか、私はここに関しては難しいなと思います。
ただ、さっき、ロバート・ダールが「サブカルは重要だ」と言ったのは面白いなと思って聞いていました。でも、ダールの議論はアメリカのことを前提にされているのですよね。アメリカはポリアーキーだから、結局ポリアーキーというのがうまく機能するのは、という話で。今、アメリカは何かやばい感じですよね。そうすると、では、アメリカのサブカルは弱まったという話なるのでしょうか。この意味でも「サブカルが強いと社会が安定するかどうか問題」というのは、これはちょっと興味深いなと思って、これはむしろ僕は鵜飼さんと、あと、須川さんにもぜひどう思うのかなと聞きたいなと思う論点だと思うのですけれども。
(川村) 「第二章:神経政治学から情動論へ」という話なのですが、「政治学では遅さや熟議からのコノリー批判」があると。この章に関していうと、僕は「ニューロポリティクス」について議論したいなと実はずっと思っていたのです。だから、これはぜひ議論しようと思っていて出した議論なのです。僕の知る限りでは、ニューロポリティクスは全然日本では議論されていなくて、受けが悪いというか、そもそもあまり全然文脈が理解されていないように思われます。
ちょっと英米の政治理論の細かい話をすると、ウィリアム・コノリーのパートナーはジェーン・ベネットという人で、私も現代思想に紹介を載せたことがありますが、「ニュー・マテリアリズム」という議論で有名な人なのですけれども、要するにそれは昨今盛んに議論されていたノンヒューマンとかポストヒューマンとか、あるいはオブジェクト指向とかといった理論的枠組みを使って政治を考えようというような主張をされている人なわけです。こういった思潮は欧米では既に二〇〇〇年代前半ぐらいからあるのです。そういう文脈がまずあって、それと関係する形で複雑性の議論の問題とか、動的非平衡とか、量子力学だとか、そういった議論に影響されているというのがある。そういった文脈の上にニューロポリティクスは論じられているんですね。ですので、やはり全然そういうことに触れてこなかった日本の政治学の文脈だとよく分からないという話になってしまうのではないでしょうか。だから、神経政治をもう少し理解可能なものにしたいと思い、議論しています。

川村覚文「ノンヒューマン的転回と『モノ』たちの政治──ジェーン・ベネット『諸システムとモノたち』について」(『現代思想』2021年1月号 特集=現代思想の総展望 2021)
ですから「熟議からのコノリー批判」がありますがという話なのですが、私は「コノリーに完全に賛同できますか」という話を言われると、いや、おおむね賛同していますという感じですね。どちらかというと、僕がコノリーに賛同できないところは、コノリーはいわゆる「アメリカの政治」の問題、つまり民主主義とかアイデンティティとか、そういった問題とどういうふうにこういった理屈を接合するかというところを考えているから、そこで僕からすると随分日和っているというか、既存のアメリカ的民主主義の制度に譲歩しているなと思うところがあって、そこに納得できないところがあったりはします。けれども、そういった点を省けば、理論的な構えは基本的には割と賛同しているという感じです。それが、いわゆる政治学の現実的な問題と交錯すると、「うーん、それでいいの?」という話になってしまったりするので、そこがちょっとなと思うところがあったりしますけれども。
そして「加速化と深い多元主義は、うまく整合しているのか」という話なのですが、これは整合しているところと整合していないところがあるという話なのではないかな、とちょっと思っています。先ほども言いましたけれども、一方でネオリベラリズムの問題がやはりあると思うのですよ。そこが基本的に何でも包摂してやろうというわけで、マーク・フィッシャーが言うように、あらゆるもの、市場がないものはないという話になっていくわけなのだから、そうすると、結局、いかに先鋭的な議論であっても、それが結局市場に取り込まれてしまうという可能性があるというところなのですよね。
ですから、元々権力は、これは第一章で書いている話につながるのですけれども、やはり制限したり命令したりするのが権力だったのが、結局そうではなくなってきているという話だとおもうのです。もう「勝手にやりなさい」ということにして、そこから出てきたものを捕獲してやるというのが今の権力のやり方で、それは非常にネオリベ的なわけです。そう考えたら、結局ある種の多元主義的なものというのは、ネオリベ的なものの支配というのが多分大前提だと思うのですね。だから、加速もまた、ネオリベ的な資本主義を加速するということになってしまう。そう考えたら、コノリーの議論はそこの中でどうやるのか、その支配からどのように逸脱することができるのか、という話かなと思っていて、資本主義が全てを一元化し均質化してしまうみたいな話を、多分前提としてはしていないのだろうなと思います。ここは資本主義をどう捉えるかという問題はやはりあると思うのですけれども。
この章でのディーンのコミュニケーション資本主義論の話とギルバートの議論なのですけれども、ここの(D)の問いかけは、ここでいうと、「党派を超えた不正の感覚と連帯?」というのが一番方向性的にあり得る問題なのではないかなというのはちょっと思っています。具体的な制度はどうすればいいのかという問題は私もよく分からないというか、それは政治学の人で考えてくださいよと言いたいなとは思いますが。ただ、ギルバートはイギリスにおける道路建設に反対する環境運動の話を取り上げています。それは何かというと、ある時イギリスで道路を新たに建設する計画が打ち出され、それに反対する運動が生じるのですが、まず環境問題という感じで反対するのですけれども、では、その環境とは何ぞやとなった場合に、いろいろな人がいるというわけです。それは右派から左派までいるという話で、僕も最近まで知らなかったのですけれども、例えば環境問題は左派だけではないのですよね。たとえば日本にも参政党というのがありますよね。あれは要は環境右翼なんですよね。健康に悪いものは外国から来たものという発想で、「日本というのは元々農本主義的で、緑に優しくて、そういう健康的な生活を送っていたのだけれども、そういったものを汚染しているいろいろな連中がいて、それから美しい日本の国土を取り戻すのだ」みたいな、そういうのが参政党らしいのですよね。そういった集団の中に、そこまで右翼ではなく、ナショナリズムとか右翼とかのことはあまり考えていなくて、取りあえず環境にいいとことを推進しましょうと言っている人が、参政党にはいっぱいいるらしいのですけれども。まあ、参政党がどうなのかはさておき、何が言いたいのかというと、要するに環境問題という形で、そこで右派も左派も連帯することができてしまうみたいなところがイギリスではあったらしいのですね。そこは情動が働いていると。「環境が破壊される」というショックから、「許さん」という怒りやら悲しみやらといった感情をもろもろ持つ人がみんな集まったみたいな、そういうのがあったという話なのですけれども。だから、そこがある意味政治運動、政治の可能性としてはあり得る問題なのかなという感じがして、ただ、それは須川さんの一番最後の『はいふり』とかの話で出てきた、要するに曖昧なところが絡め取られるのではないかという問題にまさにつながっていくという話だとはすごく私も思います。だから、そこはどうすべきなのかなというのは、私も考えないといけないなというのはあります。
また、加速主義の話なのですけれども、これは結局スルニチェク、最近はスルネックという訳の方が支配的かなと思うのですけれども、と共著者のウィリアムズはマルクス主義的な見方をしているわけです。ですので、下部構造を何とかすることで、上部構造を変革するといった議論が根底にあるように思います。つまり民主主義というのは資本主義と相関してつくられているものなのだから、資本主義を何とかすれば民主主義は良くなるはずだと、そういう発想があるのではないでしょうか。ただ、興味深いのは、ではどうするのかというと、政治が頑張るという話だから、経済構造を何とかするために上部構造を変えていくぞという話になってわけですね。
そうすると、そこで悪い左派の反復になっているのではないかということを、指摘されてしまうという感じになるわけです。要するに元々マルクス主義者というのは下部構造が重要だと言っているにもかかわらず、下部構造を変えるために政治の上部構造を変えるみたいな話をしてきたのだけれど、スルネックとウィリアムズの議論では政治運動で何とかしようみたいな話になっていて、それは失敗した道なのではないのかというのが、彼らに対する、たとえばマッケンジー・ワークとかの批判で、それはそうだなと思うのですよね。ですから、民主主義にならないのではないかという鵜飼さんの指摘なのですけれども、彼らからすれば、何にせよ下部構造を変えなければダメだという話なわけだから、加速を通じてそこを変化させていこう、となっているわけです。でも、そうすると、そのわりには上部構造の運動の話が多くて、下部構造の話が手薄なのではないかという批判がおきていて、それが技術という話をもうちょっと真面目に考えた方がいいのではないかという話につながっているということだと理解しています。
だからこそ法的規制の話うんぬんかんぬんというのは、彼らからするとあまり関係ない話になってしまっていると思うのですけれども、ただ、私が個人的に思ったのは、「自由の実現(=欲望充足)に対する(法的)規制」という話なのですが、これはちょっと面白いなと思うのですね。法学部にあってという話だったのですけれども、先ほどからネオリベの話をしているわけですが、例えばフーコーなんかによると、ネオリベにおいては法的なものが重要ではなくなっていくという話になっているのですよね、基本的には。だから法的なものという、つまり本来権力がそれを通じて行使されているはずのものがどういうふうに今機能しているのかという話を考えた場合に、もう権力の核心はここではないのだ、みたいな話がフーコーの統治性論で、それはリベラリズムがまさにそれなのだという話なのですけれども、仮にそれが今の権力の在り方とすると、それに対する対処法というのが二つあると思うのですね。
つまり何かというと、一つは、いやいや、やはり法を作ってそういったネオリベに対抗するぞという話で、その一方で、でもそんなことをやってもネオリベに負けるのだから、ネオリベのやり方を何とかかんとかこちらの方へ持っていこうとするという話がある。つまりそれは法とは違う形で考えようという話があって、それが恐らくまた情動という話に返ってくるという話になるのかなというようにちょっと思ってはいます。だから、そこは法学部的な問題というよりも、権力と法の関係というのをどういうように考えるべきなのかという問題が多分あって、それを鵜飼さんがどう考えているのかというのを知りたいなというのはあります。
こんなところでしょうか。まだ多分論点があるとは思うのですけれども、それはおいおい話しながらということで。
今度は須川さんの議論なのですけれども、ハイブリッドリアリティと情動的リアリティは一緒か、違うかみたいな話ですけれども、これはどうなのでしょうか。私が考える情動的リアリティというのは、情動的リアリティがあって、そこが基となって、そこに「いわゆる」現実みたいなものが取り込まれていくというふうに考えるという話なのですけれども、ハイブリッドリアリティというのは、「ハイブリッド」という言葉からも、どちらかというと両方が等分というか、イコール?という感じなのではないかと。その辺はどうなのでしょうか。それを須川さんはどう思っていらっしゃるのか伺いたいです。
私が情動的リアリティという言葉を使う際には、情動的に作られるリアリティの方に全てが包摂されていくという発想があるので、だから、結局例えば聖地巡礼とかをして、そこで何か新たな物語をつくっていくとか、つまり沼津に行ったら『ラブライブ!』の延長上に沼津での経験が全て展開されていくみたいな話なのですね。そういうのが情動的リアリティかなとちょっと思っていて。沼津とかは分かりやすく、そこら中にキャラがいるのでよりわかりやすく情動が触発されるのですが、これは『ユリイカ』にも書いたのですが、例えば『けいおん!』というアニメがあるのですけれども、それの劇場版でロンドンに行くので、ロンドンで『けいおん!』の聖地巡礼とかもするわけです。僕は懐かしいのと研究の必要上、わりとロンドンに行っているのですけれども、毎回ロンドンで、その『けいおん!』の聖地巡礼みたいなことをやってしまうのですね。例えば、大英博物館とかに行って、ロゼッタストーンの写真を撮って、「りっちゃんのお墓だよ」というキャプションと共に妻に送ったら「何のことか分かんない」と言われて、「すいません。これ、『けいおん!』のネタです」みたいなことをやったりとかしています。まあ、そんな感じで、大英博物館とかに『けいおん!』キャラの「ねんどろいど」を連れて一緒に行く、みたいなことをやったりとかしたりする人も、わりとたくさんいるみたいです。そうすると、当然その『劇場版けいおん!』自体のシーンにおいては、大英博物館のシーンは限られているのですけれども、その中で、いろいろと、その限られたシーン以外のシーンを想像するようなことが多分あるのですよね。

川村覚文「声優−キャラ・ライブという例外状態 : その条件としてのオーディエンスの情動と主体」(『ユリイカ』2016年9月臨時増刊号総特集:)
ですから、例えば映画のシーンではバラ・マーケットへ行ってカップケーキを食べているのですけれども、それ以外にバラ・マーケットでカキを食べたりとかしているかもしれないキャラを想像するということもできる。こういうのが情動的リアリティかなと思っているところがあって、そういうふうに自分の、要するにアニメを基につくられたリアリティがあるのだけれども、それがさらに増幅していくというのが情動的リアリティの可能性であるというふうに考えていて、そこに聖地巡礼とかがなされるというところの意義はあるのではないかなと思っています。
「オタクの生成にジェンダー差はあるのか」ということなのですけれども、もちろんあるだろうし、ないだろうというところもあるのではないか、と私は思ってます。先ほども申しましたけれども、結局、情動という問題を考えた場合、情動的なショックが生じやすい環境というのは、ジェンダー差があるとは思いますが、情動そのもののレベルにおいては理論上「ない」という話に多分なるのではないかと思うのです。でも、情動が触発された後に欲望が生まれてくるわけだから、その欲望がどこに引っ張られるかということになると思います。そこで、ジェンダー差が生まれてくるということになるのではないかなと、と思っています。そこが結局、例えばアイドルアニメとか、それが男性、女性にしろ、それはある種の性的搾取とか消費になるのではないかみたいな話があるのですけれども、それはそうでもある場合もあるし、そうでもない場合もあるのではないか、と考えています。つまり、情動のレベルでの議論でいくと、そういった問題には回収されないと思うのですが、そこから先、欲望がどう展開するのかという話になった場合において、この問題は先鋭化するのではないか、とちょっと思っています。
結局そこの問題というのは、例えば見た目が一致しているか、いないか問題とか、あるいは、ホログラムかそうでないか問題という話にも、多分、ちょっとかかってくる問題かなという感じがします。やはり声のレベルとかで考えている話だったら、恐らくその欲望の方向という問題においても、性的な問題に関わってくるかというと、そこまでかなという感じは個人的にはします。一方で、ビジュアルの問題になってくると、かなり関わってきてしまうところはあるのではないかなというのはちょっと思っていて、だからそこの問題は多分もうちょっと細かい議論が必要なのだろうなというのは常々思っています。
僕が『ラブライブ!』以前に、一番ハマったのはすでに話に出た『けいおん!』なのですね。『けいおん!』はアニメでハマっただけでなく、そのライブ、その時はオーストラリアで留学していたので全然リアルに行けてはいないのですけれども、『けいおん!』の声優ライブをめちゃくちゃ見ていたのですね。それで、『けいおん!』の方は多分『ラブライブ!』よりもさらにずれが激しいと思います、ビジュアル面に関して言うと。でも、ライブを見て、やはりこれは『けいおん!』の放課後ティーテイムそのものだと。豊崎愛生が歌っていると、「これは唯ちゃんだ」(笑)みたいな、そういうふうに声を通じて感じてしまうみたいな感じだったのですよね。情動的リアリティをめぐる考察は、これが取っかかりなので、そうなってくると、個人的にはやはり性的欲望とはちょっとずれているなというのは常に思っていた感じです。だから、この辺の問題は、もう少し突っ込んで考える必要はあるかなと思うのですけれども。
これはでも、ホログラムの話はどうなのでしょうか。例えば「声優の身体が可視化されない」はそうだと思うのですけれども、初音ミクとかはどう考えたらいいのでしょうか。初音ミクは多分男性ファンがたくさんいると思うのですけれども、ホログラムライブ、多分それは、あれはやはり元々そういうものだという話だから、うまくいっているのでしょうか。
それでここまでの話は最初の四章に関わる話なのですけれども、それとは別にもう一つ、五章に関わる話なのですが、やはり政治の問題が関わってきます。『ガルパン』にしてもそうだし、あと、例えば『ラブライブ!』とかですらそうです。神田明神は要するに国学の場所なんですね。だから、当然神田明神は国学に限らず神道の問題に関わってくるから、よくよく考えたら政治の問題に関わってしまうのですけれども、そういうことを考えた場合に、当然絡め取られる可能性がありますよね、というのはすごく思います。結局情動というものが、そこからいろいろなものが創発する領域である以上、どちらに転ぶか分からないわけです。なので、それが曖昧なまま例えば自衛隊とかに絡め取られていくというのは当然大きな問題としてあると思います。
ただ、その中にあって可能性が二つあるのではないかと思うのは、絡め取られたとしても、その後に、やはり違うのではないかと途中で思う可能性があるのではないかというのと、もう一つは、歴史意識の撹乱みたいなのが生じるのではないか、ということです。これはもう少し分かりやすい話で、例えば聖地巡礼とかに行くとしますよね。その時に、例えば「ブルーマーメイド」は基本的に日本が第二次世界大戦をやらなかった世界線の話なんですね。ただ、当然そうすると、天皇制はどうなっているのかとか、憲法はどうなっているんだとか、いろいろな問題が本来はあるのですけれども、それらの面倒な事柄はすっ飛ばしておいて、日本が第二次世界大戦とかをやらなくて発展したらどうなるかみたいな話なわけです。その上で、地球温暖化で日本の大半は水没してしまったみたいな世界線なわけですけれども、しかも空を飛ぶ技術はないみたいな、そういう話だったりするわけなのですね。そういう世界観のもとで『はいふり』の聖地巡礼に行った場合に、その人はアニメの世界がリアルなわけですが、一方でその聖地そのものは当然常識的な意味でのリアルな世界大戦を経験した後の歴史の世界線に存在するものなわけだから、そこにある種の齟齬みないなのが、真面目なオタクであれば起こると思うのですよね。そういった抵抗とはいかないかもしれないけれども、歴史意識のかく乱みたいなのが起これば、もうちょっといいかもなと思っているというのがあって。
あとは『艦これ』の多様性があるのではないかという話は、それはまさにそうだと思います、私も。だから、あれはあくまでそういうことがあるかもしれないという話であって一例ですから、どちらかというといろいろな可能性が、つまり『艦これ』のせいですごいガチ右翼になっていく人もいると思うのですね、一方で。かといって、そうではない人たちもいて、そうではない人たちがいたとしたら、こういうのが一例としてあるのではないかという話をしたという感じです。だから多分須川さんがおっしゃったように、いろいろな可能性がありますし、まさに多様性があるというわけですので、そういった中から私の物語が紡がれていくというのは、まさにそうだと思っています。そして、そこからどういうふうに展開していくのかというのは、多分それぞれなのだろうと思っています。
すみません。ちょっと私の応答が長かったですね。
全体討論
(崎濱) はい。ありがとうございます。そうしましたら、順番に鵜飼先生からの応答、その次に須川先生からの応答で、時間が許すようであればご質問、あるいは、またさらなる応答という形で進めたいと思います。
では、鵜飼先生、お願いします。
(鵜飼) はい。ありがとうございました。多岐にわたる点に応答を頂いているし、ほぼ実は私も意見は一緒だなというところがありますので、そういうところは飛ばして、気になった点のみを拾わせていただくと、AI支配の話からですよね。
(川村) はい。
(鵜飼) あれなんかは、まさにリスク社会論。つまりアルゴリズムに任せろといった場合、アルゴリズムが暴走したらどうなるのですかみたいな問題になりますよね。まずそこの問題が一つです。もう一つは、アルゴリズムの管理者自身は排除されると思っていないわけですよね。
(川村) はい。
(鵜飼) そこは私は滑稽だなと思うので、自分がアルゴリズムに乗って排除されたら、あなたは受け入れますかというふうな議論があり得るかと思うのです。
だから、そもそも民意は実体化できるのでしょうかと、データ化できるのでしょうかというふうな感じの問題提起するのがよさそうです。つまり選挙の、Aさんがいい、Bさんがいい、Cさんがいいとかいうのは、それなりにデータ化できるかと思うのですけれども、多くの方は要するに選挙に興味ないですとか多様な意見があるわけですよね。そこまで拾えて、あるいは、仮にその選挙で民意の十全な出現が可能であるならば、もう次の選挙は要らなくないかという感じになるわけですよ。つまり選挙というのは、ある意味で不誠実で、それが文句のある、文句を言える余地があるから、また次、ではやろうという感じの繰り返しになるわけですよね。毎回毎回、一回でも十全なる民意が出現したのだとなった場合、果たして僕らはそれに耐え得るのかというところがあって、そういった感覚をAI民主主義を語る方たちはお持ちになっていないかなという印象はすごくあります。
あと、ロトクラシーの話。おっしゃるとおり、集団性みたいなことにこだわりというか、その視点があるのだというふうなことで考えざるを得ない。僕もロトクラシーは厳しいと思うのだけれども、なぜ厳しいのかというと、ロトクラシーはかなり同質性が高い社会でないと無理ですよね、明らかに。となると、現状は日本社会というのは川村さんの見通しでもそうだと思うのだけれども、同質性が崩れていっていて、よく言えば多元的になっていく段階の中で、くじ引きで決めてやろうというのは厳しそうです。そこがまず根本的に違っていて、古代ギリシャのアテナイみたいに数万人のしかも男性だけで同じ知的レベルの中で選ぶのは可能かもなのだけれども、現代社会では条件的に苦しそうだというのがまず答えです。
(B)の川村さんのお答えについて、保守派というか自民党支持というだけではなくて、根本的に社会に対する保守的な感覚ですよね。
(鵜飼) これは非常に面白い説で、要は現状に対する満足度が高いというか、確かに政治とか何だとか、個別のものに対しては満足度は高くないかもだけれども、生きているということ自体に対する満足度とかはそれなりにあるのではないかなというのは、やはりちょっと感じさせられますよね。
特に僕も川村さんも同じ頃に留学していたからよく分かるのだけれども、東アジアの他の地域の方とかというのは、基本そこで就職というか、生活を懸けて行っているわけですよね。僕らは基本的に戻ってくるのが前提なので、そこの構えがもう違いますよね。それはちょっと感じさせられるなというところがしょっちゅうあって、とはいえ、「やはり日本の方は日本社会が好きでしょう」というふうに言われてしまうと、うっとなります。私たちの内なる保守性を見透かされた感じがします。
(C)のコノリーのところも大変勉強になる応答を頂きまして、ありがとうございます。これについては特になくて、(D)もないです。
(E)のところで、最後、逆に質問を投げ掛けられる形で、法みたいなものでこういったところにどう介在する、権力との関係でという点です。これは確かに非常に難しい問題で、うかうかと言えないところなのですが、確かに、多分僕はある意味では川村さんと同じような感じで、法自体が権力の基盤として排他的に特権的な地位を持っているのだということは、ちょっと想像しづらいなとは思うところなのです。ただ、その意味では、その法というふうなものの重要性は失われていっているような気がするのだけれども、それが現状、21世紀社会の中でどこまで覆されるのかというのは、私も逃げになりますけれども、ちょっと分からない。
確かなのは、勤務先もそうで、法学部が安定的に人気なのはあきらかで、偏差値的な意味で。それが日本社会は非常に根強いだろうなと。それを権力といえるかどうかはちょっと微妙なのだけれども、そういう順位付けが本学であれ、恐らくここ東京大学であれ、変わらないというのは、これはやはりそこまで踏まえた上での権力性かなというところは、この〔共通テストから一週間後の〕時期になると考えさせられますよね。
すみません、こんなところで。以上です。
(崎濱) 鵜飼先生、ありがとうございます。
続いて、須川先生から応答をお願いいたします。
(須川) はい。いろいろとありがとうございました。川村先生のセクシャリティとか思考というものがいろいろな体験で、理解できたので面白かったなと思っているのですけれども。情動と欲望の差というのが、ジェンダー差というのは情動の場面では不問になるというのは分かりました。
やはりどうしても解決できない身体の問題で、声があると実在性というか、身体性が出てくるので、それは接着剤みたいな感じで機能できるから、やはり欲望の方にいくのだろうなと思うのですけれども、でも、うつろな身体というのですかね、中身のない身体に対してどうやって情動は機能するのかなというふうになると、もうちょっとやはり考えなければいけない問題だなと思って聞いていました。
初音ミクの話が出たのですけれども、ミクと、あと、男性のボーカロイドもいますよね。
(川村) はい。
(須川) それもやはり元の声をやっている声優さんの声があって、それがあるので、どうしても実在論というか、本当らしさというのが接続してしまうのだろうなと思うのですけれども、では、あれが機械音になったらどうなのかとか、ホログラムプラスAIの本当にデジタル音みたいな、それで情動が生成されるのかなとか、そういうのも、今話を聞いていて考えなければいけない問題なのかなというふうに思ったのですね。
今、結構ハイブリッドリアリティの話があって、あれはメディア研究の枠組みで出た言葉で、実際、私は2.5次元空間を説明する際に他の言葉が見つからなかったのであれを使ったのですけれども、やはりリアリティと虚構、ファンタジーというのが混交している状態、だから、それが50:50なのか、60:40なのかというのは、その人の認識によるので、認識を基準にしているとどうしても理論化できないのですよね。なので、情動論を切り口にしてみると、それがうまく言語化できていいなというふうに思ったのですね。
だから、どういうふうに有効化できるのかなというふうに今結論は出ていないですけれども、可能性としてはとてもあるというのは一方であって、それから言及されたように多様性もありますよね。それを理論の枠組みで理解するのと、私がアプローチしている実証データの方にうまく接続できないところにジレンマがあって、実際、聖地巡礼とかもそうですけれども、文化実践している人たちは、いろいろな無意識に――例えば先ほどの『艦これ』とナショナリズムの話ではないですけれどもーー自分は意識していないのだけれども、「やっていることは右翼だよね」みたいなものは結構あったりして、それを自覚できないところが実は怖いというか。ナチズムのコスプレの話とかでもよく議論されていますが、文脈を理解せずに、やりたいからやってしまうみたいな文化実践している人の、他から見た、結果的に生じてしまう政治性みたいなのをどうやって理解すればいいのかなというか、その回路を説明するのに情動論はどういうふうに機能するのかなとか、そういうのがいつもぐるぐる回っている感じなのですね。多分私の中で、ちょっと情動論は精神分析に近いなというものがまだあって、実際は全然違うところから出ているのですけれども、それは私がもともと映画研究をやっていたからなのですね。
私は修士が映画研究だったので、その時に精神分析の映画研究を散々読まされて、それが絶対機能しないと思っていて、それでカルチュラル・スタディーズのテレビ研究にいったというのがあったので、だから今、そこにまた、精神分析ではないですが、同じように欲望の前に存在するような情動で考えているというのは、結構そこに戻るような感覚がまだあるのです。だから、そこで自分としては精神分析の限界を知って精神分析的な映画研究に対して批判するということがあったので、これからそれをどう応用していけばいいのかなというのは結構思索的というか、今おっしゃった疑問にまた疑問で投げ掛けなければいけないという感じはします。
ただ、先ほど言ったように、すごく有効な議論になるのではないかなと思っているので、その先というのをもう少し一緒に考えていきたいなというふうには思いました。
(崎濱) 須川先生、ありがとうございます。
(川村) ではちょっと、再応答します。
ありがとうございます。精神分析の話は興味深いというか、映画研究はもともと本当に精神分析の影響が強かったですよね。
(須川) 昔はそうでしたね。
(川村) 情動論の話でいくと、基本的に情動論には二つ系譜があって、一つは明らかに精神分析です。つまり欲動と情動を同じものとして理解するという話であって、ジョディ・ディーンはこの系譜にあると言えます。
そして、もう一つは、これはドゥルーズの議論で、その背後にはスピノザの議論があります。ドゥルーズ、スピノザの系譜で情動を理解するという議論です。ご存じのようにドゥルーズというのは、そもそも精神分析を批判した人であるわけですよね。つまりアンチオイディプスという形で、欲望というのは否定して生まれるものではないのだという。精神分析は基本的に抑圧という否定があって、それから生まれてくるのが欲望であるという話になっているわけですが、だから、まず欲望というのは、その否定の契機のあとに生じるのだ、というのが精神分析の主張なわけです。このような否定によって欲望が生じつといった議論に異議をとなえたのがドゥルーズで、その延長上にあるのが情動の話なので、その意味でいうと、スピノザ−ドゥルーズの系列の情動論は、精神分析をむしろ批判している理屈なのだと思います。

Jodi Dean. Blog Theory: Feedback and Capture in the Circuits of Drive. Cambridge: Polity, 2010.

Brian Massumi. Ontopower: War, Powers, and the State of Perception. Durham: Duke Uni Press, 2015.
ただ、一方で日本の文脈が錯綜しているのは、ジョディ・ディーンの情動論とドゥルーズ系の情動論というのが交ざって議論されているところがあって、私もあえて交ぜようとして議論してみたのですけれども、第五章では。ただ、それで何かジョディ・ディーン的なものを超えて情動というのを考えるべきなのではないかというのを第五章に書いたつもりだったのです。つまり、情動そのものの可能性みたいなものを考えようという話をしたつもりだったのです。
ですから、つまりそこの関係をどう考えるかがまず一つあって、さらにその先をどうするのかというのは、やはり考えなければいけない。この二つは、やはりやらなければいけないと思ってはいます。今、須川さんがおっしゃったように、それはむしろ私も考えていきたいなと思っていて、一人で考えてもしょうがないので、仲間を求むという感じではあって、今、須川さんが一緒に考えていきたいとおっしゃったので非常にそれはありがたいなと思ったのですけれども、本当にぜひよろしくお願いしますという感じです。
もう一つ、例えば意識はしていないけれども、いつの間にか右翼になってしまっている問題はやはりあるじゃないですか。それは要するにパフォーマティブな問題だと思うのですけれども、それこそジジェクが「イデオロギーはパフォーマティブに機能するのだ」という話をしていて、それは精神分析の議論なのですけれども、情動論はそれをどう考えるのかというのが、やはり問題として恐らくあるのではないかと思います。パフォーマティブな形でやっているということが、いつの間にか、意識していなくても何か染まっているみたいな話になるという問題を、情動でどう捉えるべきなのかなというのは、先ほどの精神分析との関係性で、考えざるを得ない問題かなとちょっと思います。
もう一つ、先ほどの鵜飼さんの、満足度の高い社会問題なのですけれども、これは恐らくサブカルが関わってきて、なぜかというと、それこそ10年ぐらい前、「自分は日本社会に対して大して不満はなくて、この先そんなに豊かにならないだろうから、でも貧しくても楽しく生きていける社会でいいのではないか」みたいな議論があったと記憶しています。それで、その根拠が、コンビニに行ったら安い物がいっぱいあって便利だし、私生活ではアニメとかを見て満足できるしみたいな、そういう話だったわけです。多分これは、今、この何が抵抗力になっているのかという話に結構関わってくる話かなとちょっと思います。
だから、やはりサブカルが強いからというのは、これはロバート・ダールとは全然違う話になってしまうけれども、でも、そういうふうに何かある種、自分の世界に自足して生きていけば、自分の周りさえ良ければいいみたいな世界でやっていけるから、大して何も考えないみたいなところがあるわけです。確かに台湾だったら中国が攻めてくるかもしれないから、何とかしなければみたいな話で留学するとかが普通にあるわけです。彼らはそういう発想でいつもやっているし、中国にしろ韓国にしろ、やはり自分たちを取り巻く状況が良くないからという理由で留学し、その上で海外で安定した生活を築こう、みたいな意識は普通に強かったと思うのですよね。でも、それが日本人は欠けているという話で、日本人は満足度は高い。なぜかというと、確かにそれを言われてみると、サブカルがあって、そこでハッピーだからという話になってしまうこともなくはないかなというのはちょっと思うところです。それがいいことなのか、悪いことなのかというのは、結構どうなのだろうなという感じではありますが。それは、当然、見た目以上に政治がうまく機能しているという話が背後にあるのかもしれないけれども、その辺はどうなのかなというのは、つまりサブカルが社会の満足度に貢献していて、それが結局社会の保守性というものに寄与してしまうのではないかという問題というのは、どう思われますかという感じです。
(崎濱) ありがとうございます。このまま議論を続けてもいいのですが、いったんここで編集者である水野さんからもしコメントがあれば、お伺いしてみたいなと思うのですが、いかがでしょうか。
(水野) 政治認識とか不確実性でいうと、N党が議席を取ったり、参政党の問題とかもあったりとかして、より不確実性が増している側面があります。アメリカでトランプが大統領になるみたい状況と比べると、日本はマシではありますけれども、状況は結構悪化しているような感覚は何となくあるかなと思いますね。
兵庫県の問題などを取り上げられていたのですけれども、本の編集の段階ではこの問題は浮上していなかったのですが、情動論と政治的言動の関係で言うと、編集していて思い当たったのは「反ワク」(=反ワクチン)の問題です。コロナウイルスに対する政治的対応について、情動論的に扱う上で一番意義深い問題なのかなと感じたりしていました。「意外と日本は大丈夫」という感覚もある中で、しかしやはり状況はやや悪くなっているのではないか、という感覚があります。
初音ミクに関して言うと、声優さんとかなり切れていると思うのですよね。それも結局音声が素材というか、本人がしゃべっているというわけではないというところがすごく大きい気がします。初音ミクのライブは2.5次元の声優さんのライブなどとは結構違うのかなと思いました。
アニメーションの3DCGとかで踊るのが、男性向けのアニメコンテンツだと少ないというのは確かにそうだなと思うと同時に、最近だと、バーチャルYouTuberとかだと男性向けで3DCGのライブも結構あったりして、その差はなぜあるのかなというのは結構気になっています。
(崎濱) ありがとうございます。今のお話にもし応答があれば。
(鵜飼) 僕はないです。
(川村) そうですね、僕はVTuberを須川さんがどう見ているのかというのを知りたいですけれども。
(須川) VTuberは後ろに身体があったりするので、やはりまだ人間の範疇かなというふうに思っているのですね。つまり身体性や実在性に結構接続してしまう。あれがもし例えばAIだったりしたらどうなるか。キズナアイなどはAIという体でしたけれども、基本いるじゃないですか。
(川村) はい。
(須川) 声優さんもいるし、身体もあるしという。ないとどうなるのかというのは、すごく考えるのです。全く、今、多分生成AIで何でもできてしまう時代になって、でも、それはリファレンスが必ずあるのですけれども、ないものは今まで失敗してきたのですよ。バーチャルアイドルは知っていますか。
(川村) はい。伊達杏子とか。
(須川) そう。伊達杏子、ご存じですね(笑)。あれは全然ウケなかったではないですか。
(川村) はい。
(須川) というのは、まだ空虚なのですよ、中身が。ですので、何かリファレンスがないと、どうしてもそういう受入態勢はなかったのですよね。それが、もしかしたら今だったら多分あるかもしれないのですけれども、そういうデジタルネイティブの人たちにとっては。でも、どうなのだろうなというのはまだ解決せずにいますね。やはり身体があるということ、本物がいるみたいなというところの実感というのが情動をかき立てるのではないかなと思っていて、全く何もない、中身のない、本当に単なるアバターにかき立てられる情動はあるのかという感じですね。
(川村) でも、映画とかで、Siriみたいなものに恋するみたいなものがあるじゃないですか。
(須川) はい。
(川村) それに近いですよね、そういった意味でいうと。だから、あれをどう考えるかというのにもちょっとかかってくるかなという感じは。
(須川) 『攻殻機動隊』の第2期ですかね。でも、あれはAIのサイボーグとは違う話、違うのかな。
(川村) どの話ですか。
(須川) AIのサイボーグに恋してしまう男性の話で。
(川村) はい。ありますね。
(須川) あれは随分昔の話で、まだ実現していなかったから物語が成立しているのですけれども、今実現してしまうではないですか。ということはどうなる?
(川村) そういう話は結構あるではないでしょうか。最近だと、『アイの歌声を聴いて』だったか、ご存知だとは思いますが。
(須川) 『アイの歌声を聴かせて』。
(川村) そうそう、『アイの歌声を聴かせて』でしたね。『イヴの時間』をつくったのと同じ方の作品。あれは完全AIという話ですよね。それ以外にも、それこそ今では国会議員になった赤松健さんが描いた『A・Iが止まらない!』という漫画が昔ありましたけれども。
(須川) うーん。
(川村) ご存じないですか。
(須川) はい。
(川村) 『ラブひな』や『ネギま!』を描く前に発表されていたのですけれども。
(須川) そうなんですか。
(川村) そう。それは自分でAIをつくって、理想の女性なんだけれども、それがいつの間にか実体化してしまって、人間になってしまうという話。
(須川) ああ、そういう映画がありましたね。
(川村) うん。割と好きで、全巻持っているのですけれども、その漫画は。
(須川) また告白が(笑)。
(川村) そう。面白いなと思って。そういうのを突き詰めた結果、自分は2次元しか好きではないみたいな話になるということがあるのでしょうか。フィクトセクシュアルという話をされている人が若手とかでもいらっしゃるけど、そういう話につながっていくのかな。ちょっと、この辺は僕も全然考え切れていなくて、でも、VTuberはやはり身体があるからなのではないかというのは、ちょっと僕には分からないです。
(須川) やはり垣間見える身体を楽しむという回路があるので、例えばおじさんが美少女をやっていて、アバターのすきまにおじさんが見えるのが面白いところで、そういうところの享楽というのはあるので、それが完全に誰もいないアバターだったら、面白さはどうなのだろうかとか、分からないです。すごく純度が高くなって、それこそ恋愛対象になるのかもしれないですけれども。
(川村) そうなのですよね。その時に持っているそういう感覚というのは情動なのか、欲望なのか、何なのかという問題があるかなという感じがしますけれどもね。
(須川) サブカルの問題があったと思うのですけれども、サブカルは機能していますか。日本はサブカルなのだろうか。サブカルチャー。
(川村) サブカルチャーという言葉が難しい。そもそも、サブカル対オタク問題みたいな議論というのは、よく起こりますよね。サブカル愛好者とオタクは違うのだみたいな。つまりサブカルというのは、どちらかというと文学的な方向に行っていて、一方でオタクというのはアニメとかゲームとかに行くので、サブカルとオタクは違うのではないかみたいな話です。確かにカルチュラル・スタディーズ的な発想でいくと、要するにメインカルチャー、サブカルチャーという話で、サブカルチャーというのは、そういうメインではない、労働者階級の人々が受容するのがサブカルチャーで、それはやはりメインの支配階級のカルチャーとは違うのだみたいな話がもともとあってということだと思うので、それはオタクとは当然違うわけですよね。ただ、日本でのサブカルチャー自体もちょっとそれとは違うのですよね。サブカルという言葉を広めたのは、宮台真司さんだと思うのですけれども、『サブカルチャー神話解体』などで。この本などを通じて、すごくサブカルチャーという言葉がはやったかな、広まっていったかなと思うのですけれども、しかしその中には本当にいろいろなものが入っていると思います。そういった意味ではサブカルが日本で強いのかというと、それはある種のオルタナティブ教養主義みたいなものを指す言葉になるわけですが、サブカルは強いのかといわれると、「うん、まあね」ではありますよね。
(須川) はい。
(川村) どうですかね。
(須川) そこがやはりアメリカでいう意味のサブカルチャーとはちょっと違うということで、サブカルが強いと言うときに、どのサブカルかは。
(川村) そうですよね。
(須川) でも、アメリカの例とかを見て、DEIが廃止されるふうですけれども、ちょっとDEIが行き過ぎてしまったではないですか、ハリウッドとか、ブラックウォッシングとかがかなり問題になりましたけれども、ああなってくるとどのぐらい抵抗できるのかなというのはちょっと思います。トランプ政権でそれを貫けば、いやいや、DEIは大事だよねという感じで貫けば、「おお、ハリウッドはすごい」とかと思いますけれども。それこそサブカルチャーの力と思いますけれども。今、この状況で、やはりハリウッドも資本主義で動いているので、どのぐらい抵抗できるのかなというのは結構注視しているところで、どのぐらい表現が変わってくるのか。だって、やはり『STAR WARS』は女性に対する批判とかがすごかったではないですか。DEIが称揚されていても。
(川村) はい。
(須川) だから、実写版の『リトル・マーメイド』もやはりそうですけれども、それがトランプ政権になって、もっと抵抗力が強くなってくるのですね、あれをやれば。けれども、どのぐらい耐えられるのかというのはちょっと考えています。
(川村) 確かに。だからサブカルの政治性というのが、日本と欧米だと結構変わってきてしまいますよね、その意味で言うとね。
(須川) はい。
(川村) そこをどう考えるのかというのはちょっとあるなというのは思うのですけれども、どうですか。
(鵜飼) 多分、私なんかはサブカルの定義とかというのは、さほど知見がある人間ではないですけれども、明らかな文化的な多様性はありますよね。僕みたいに九州に住んでいるといえば、九州は九州の文化があるし、福岡は福岡の文化があって、そういう意味のサブカルなのではないのですか。それが多分社会の厚みというところにすごく日本社会があるような気がします。あとは、それこそ私たち3人ともイギリスに住んでいたからよく分かるのだけれども、イギリスは地方都市といってもそんなに特別なものがなさそう、例えば熊本城のような形でローカル性を体現するような、そういうのはないではないですか、基本的に。
(川村) ふむ。ウェールズやスコットランドとかに行くのはどうでしょう。
(鵜飼) はい。そこですが、食文化を含めての多様性とかというのは、やはり日本はあるなというのは、僕みたいに田舎に住んでいるとやはり思いますよね。それが多分、ちょっと表現はあれなのですけれども、社会の構えとしての余裕という意味ではまだあるかなという気はしますけれどもね。あまり、急に振られてしまったので、気の利いたことが言えないのですけれども。
(川村) いやいや。
(鵜飼) あと、では関係ない話をすると、声の話が四章に出てきますが、僕はすごくこれに興味があって、僕がこの事例でぱっと思いつく例で言うと、第一次世界大戦中のクリスマスの時に、兵士がみんなでクリスマスソングを歌うみたいなエピソードがありますよね、塹壕戦の最中で。それとかはある種のヨーロッパのカルチャーとしての集団性が、たとえ総力戦で敵と味方に分かれたとしても、共通文化があるみたいな感じで、恐らく川村さんの議論からすると、多分評価するべきという感じの事例の気がしているのですよね。
あるいは、この間で言うと、EUにおけるイギリスが離脱する時に、イギリス代表が議場から出ていく時にみんなで「蛍の光」を歌うのですよね。それは多分ある種の情動的なもので、歌が自然に状況に出てきて、そんな感じのエピソードとしてまとめられそうです。たとえ誰かしらの意図があったにせよ、歌声は情動的な産物ではないでしょうか。
ただ、日本の場合というのは例えばで言うと、正田邸が取り壊しになる時に保守主義的な指向をもつ女性たちがそこを囲んでいて、同じようなエモーショナルなシーンになった時に彼女らは何を歌うのかというと、「君が代」を歌う。多分、川村さんとしてはそれは駄目だと思う。ただ、それはどこの軸が川村さんの評価になるのか。それは、さっきの「何となく右翼」みたいになっていくというふうなことなのか、とはいえ、やはり集団性はある種の暴力性みたいなものを持っていて、これはコントロールできなくなってしまうということを川村さんが危惧されているのか、その辺の使い分けというか、意識というのはどの辺にあるのかなというのは四章の話を聞いて、ちょっと疑問として私は出させていただきたいなというふうに思いましたけれども、いかがですか。
(川村) なるほど。基本的な話としては、情動に触発されて保守主義的な女性が出てきてという話はあると思うのですよね。一つポイントは、保守主義的な女性にさせられているわけではないわけですよ、彼女たちは。勝手にそうなってしまっているというところがあって、そこを利用するというのが権力という話だと思うのですね、基本的には。つまり権力というのが、もはや何かをさせるのではなくて、勝手に出てくるものを利用するというのが権力の在り方で、そうすると、先ほどの法がうんぬんという話につながっていって、やはり法とかで権力を握るみたいな話は全然なくなっていって、その上で、そういう情動によって権力の在り方が新しくなっているという問題があるということだと思うのですよね。
それは要するに一方で裏返しの反面というか、そこに、同じ情動の中に、情動的な権力によって利用されるということに対する抵抗の可能性もあるのではないか、ということをまず議論したいというのが、この情動論の、情動を巡る政治の議論の大前提の議論なのですよね。
(鵜飼) あれは、保守主義的な女性たちも抵抗だと思っているのではないですか、多分。正田美智子さんが生まれ育った家というのを行政が壊そうとしているのだけれども、いや、私たちの神聖なる家ですみたいな感じで、抵抗のソングとして「君が代」を歌っているのではないかな。
(川村) もちろん、そうだと思います。でも、その中で、それがまた右翼に利用されるみたいな話になっていくわけですよね。だから、結局そういう、それこそまさにドゥルーズが言うところのミクロポリティクスというやつがあって、そこにめちゃめちゃ情動が利用されていて、今ある政治はほとんどミクロポリティクスが中心となっているという状況なのではないしょうか。だから、それは国民的な統合がなされるということがほぼほぼなくて、アメリカですらトランプ体制の状況というのは、全アメリカ人を統合しようなんてこれっぽっちも思っていなくて、結局ある種の情動によって利用できる集団だけを利用してやろうという話なのではないでしょうか。まさにミクロポリティクスしかないという話だと思うのですよね。そこをまず考える必要があって、そこに対する抵抗の可能性も情動にあるのではないかという議論をしようというのが、この本の大きな構えなである、と考えられるかもしれません。
もちろん、いや、そんなのでは駄目だと。「もう一度大きなマクロポリティクスを再興せよ」みたいな議論もあると思います。それがジョディ・ディーンの基本的なスタンスだと思います。しかし、それは結局ミクロポリティクスには負けてしまうのではないか、という危惧が根幹に生じてしまうようにも思えます。というもの、これだけミクロポリティクスをやるテクノロジーというのがすごく充満していて、そうすると、そのテクノロジーに全部先回りされているのだったら、マクロポリティクスをやっても無駄なのではないか、という話になってしまうわけですよね。
そういった意味で言うと、ミクロポリティクス的なテクノロジーというものをどういうふうに抵抗する側が利用するかという話をせざるを得ないと思うわけです。だからこの本としては、テクノロジーという話をしましょうという話になっているわけです。
でも、逆にそうすると、やはり須川さんがおっしゃっているような実証的な問題というのが結構重要になってくるのかもしれないなと思うわけですね。そうすると結局、ここでは、こういうのとこういうのがありますみたいな話を地味に重ねるということが結構重要なのではないかという。つまり、地道に重ねることが重要なのではないかという話になるかなとも思ったりするのですが、それはある意味ラトゥールというか、アクターネットワーク的なものになるのではないかとちょっと思いましたが、でもそこに情動という問題をどういうふうに考えていくかという話は、まだないようにも思います。つまり、情動はそういった現状のミクロポリティクスとテクノロジーの関係というものを考え直すという意味で有効ではないかというのが、この本の趣旨なのです。
だから、正田美智子邸を取り囲む女性のミクロポリティクスをどうするかというのは、マクロポリティクスだけでは駄目だろうという話にはなると思います。だとして、しかしどうしたらいいのでしょうか。どう考えるべきなのかなというのは、ちょっとパっとは思いつきません。でも、それはそれで置いておいて、それが何か大きな力にならないようにしておくということが重要かなという感じはしますけれども。つまり、正田美智子邸のところで歌を歌っている女性をどうこうするというよりかは、そういう人がいても大丈夫というふうにするという。
情動を基にした権力という話で、ブライアン・マッスミという人が存在権力という話をするのですけれども、彼の議論は要するに先制というのが重要だという話なのです。プリエンプティブ(preemptive)というのが重要で、それは抑止とか制限とは違うのだという話で、なぜかというと、抑止とか予防とかというのは起こらないようにしようという話なのですよね。でも、先制というのは起こることは前提だと。起こってもいいけれども、起こった後にそれをどうする、それが変なことにならないようにするのが先制だという。そのために、その起こる場というものを最初からやり変えておこうという話なのですよね。それは環境というのを変えるのだという話なのですけれども。それが先制権力をやっているのだったら、抵抗先制権力は違うように場を変えるしかないのではないかという話に多分なるかなという感じがします。つまり、ミクロポリティクスが起こる場というのをどうするかという話です。
(川村) だから、ちょっと今思いましたけれども、そういった意味で言うと、やはり起こるのだけれども、その起こるものをどうするか。起こらないようにするということではなくて、起こるけれども、どうするかという話をするしかないかなというのはちょっと思いますよね。だから、「知らないうちに右翼になっている人問題」だったら、それはしょうがないという話で、そういう人が出てくることを見据えた形で考えるしかないのかもしれません。
(鵜飼) 天皇とかが年頭にあいさつをする時に旗とかを振っていて、まさに情動が満ちあふれているようなオーディエンスの方たちいるではないですか。まさにリズムが同調しているというか、あれも多分川村さんの話を聞いたら、あれも旗を振ってしまうやつはしょうがない。そのエネルギーをどう使うかというところで。そこを例えば皇居前広場をみんなできれいにしていただくとか、エネルギーを環境の方に使わせるとか、あるいは、ちょうど募金箱とかを出しておいてみんなが募金するとか、そういう感じで何か。
(川村) 旗にモーターを付けておいて、振ったら発電するとか、そういう。
(須川) 自然エネルギー。
(川村) そうそう。
(崎濱) 最後に私からも質問させてください。今の話に少し関係があるかと思うのですけれども、鵜飼先生のレジュメの最後に書かれている「情動があるだけマシか?」という点について私も考えてみたいと思っています。今、情動があるとすれば、そこから結果的に右翼的な振る舞いをしている人がいて、それは、そういう存在がいることを前提として考えなければならない、また、考えられるような議論を組み立てるべきだというお話だったと思うのですけれども。考えてみたいのは、そもそも情動があまり喚起されないような状況があった場合、そこから政治的な可能性はどのように開かれ得るか、ということです。最初の一撃を加えないと情動が起こらないのだとしたら、どうすればよいのか。そしてもし、その一撃が起こりにくい領域というのが仮に日本社会にあるのだとすれば、そこのところをどう考えたらいいのかということを疑問に思いました。
というのは、いわゆる政治的無関心みたいな話につながってくるのですが、最初に述べたように私は沖縄のことを研究していまして、「沖縄問題」というのは過剰に情動を刺激するトピックでありつつ、でも、刺激がない時には逆にすごく静まりかえるという極端さを伴っています。何もなければみんな沖縄のことなんか忘れてしまう。質問をまとめると、情動が喚起される前提条件というのはどういうものなのか、そのことと政治的無関心についてどのように考えればよいのか、ご意見をお聞きしたいです。
(川村) 『白い砂のアクアトープ』や『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』とかを見るというのはどうでしょうか。これらは沖縄をテーマにしたアニメですけれども。こういったものを見て、聖地巡礼とかで南城市とかうるま市とかに行ってもらって。
(崎濱) なるほど。
(川村) 南城市は『白い砂のアクアトープ』というアニメの聖地になっているのですよ。沖縄に僕はしょっちゅう行くのですけれども、空港に行くと、パネルがバーンと置いてあって、その前で写真を撮るみたいな、そういう感じ。
(須川) また、告白(笑)。
(川村) そう。いや、僕ではないですよ。僕ではなくて、撮りなさいとなっているという話ですよ。僕はパネルしか撮っていませんから。だから、沖縄のメディアに対する露出はやはり限定的ですよね。
(崎濱) はい。
(川村) 場合によって情動を触発するような要素がバーンと出てくるという話ですが、でも、日常的にそういうことがあるかというと、多分そうでもないですよね。『ちゅらさん』や『ちむどんどん』といった朝ドラがあったけれども、こういう作品はそれほど情動を喚起しない。『ちむどんどん』自体は失敗してしまったし。でも、それに対してオタクのミクロポリティクスに訴える作戦というのはあるのではないでしょうか。
(須川) 私の学生の卒論のテーマが「沖縄のラップミュージック」なんです。
(川村) 沖縄でラップと言えばコザですね。
(須川) そうそう。何か、そういうものがやはり沖縄の持続的な問題、結構リリックにいっぱい課題とかを盛り込むラップなのですけれども。
(川村) そうそう。たとえば「This Is America」というものを改編して、「This is OKINAWA」という歌を歌っていたりして。
(須川) 彼はAwichさんを中心にそういうジェンダー問題とか黒人の問題をやっているのですけれども、そういうのが可能性があるのではないかという結論を彼は持っていて。
(崎濱) それこそ、いわゆる意味でのサブカルチャーの抵抗力というところですよね。
(須川) そう。それはどうなのですか。沖縄では結構すごくはやっていますか。私はあまり知らないのです。
(川村) はやっているというのは、どういう意味ですか。
(須川) ラップミュージックは誰もが知っているような。
(川村) そういうわけではないけれども、ローカル的にはすごい。先ほど言ったコザという場所ですが、コザは元々音楽の町という話で。
(崎濱) そうですね。基地の町であるが故にアメリカのラップカルチャーの影響がダイレクトに入ってくる。
(川村) そう。アメリカのカルチャーがそのまま入ってくる。
(崎濱) 先ほど、サブカルチャーが抵抗権力として存在し得るかどうかという話がありましたが、沖縄においてはわりと、いわゆるカルチュラル・スタディーズの枠組みが適用しやすい部分はあるだろうな、と思います。逆に日本本土において、それを考える難しさが大きいなという感触があります。
(川村) そうなのです。沖縄内部においては、やりやすいと思うのですよね。沖縄内部においては分かりやすく、それこそ、ディック・ヘブディジの『サブカルチャー』みたいなのがすごく適用しやすい状況にあるのだと思います。だからこそ、その中でよりぐるぐる回っているのだけれども、日本全土では全然そういうことが循環しないから、沖縄の人は逆にフラストレーションがたまっていくという状況がある、という話だと思います。

D. ヘブディジ『サブカルチャー: スタイルの意味するもの』山口淑子訳、未来社、1986年
(須川) そうですね。
(川村) はい。
(須川) 全国的に番組が結構あったでしょう、ラップバンドの。
(崎濱) はい。
(川村) はい。
(須川) あれがあったことによって、ラップミュージックというのが日本の若者に浸透して、その中に沖縄のローカル性をすごく持ったラップミュージックというのが存在感があるという議論なのです。
(崎濱) なるほど。
(須川) 「ちょっと待ってよ」と私は思っているのだけれども。そこまで頑張って主張しているのは素晴らしいと思うのですけれども、それがやはり先ほどの疑問に対してちゃんと応答できているかというのは。それは常に沖縄の問題をみんなに考えさせられる、情動喚起するのではないかみたいな、情動という言葉を使わないですけれども、喚起するのではないかみたいな論で行っているのですよ。彼は当事者だし、当事者といっても沖縄出身というだけですけれども。
だから、アニメなどは期間限定だったり、配信はありますけれども、やはりピークがあってまた下降していくいくけれども、ラップミュージックは場所を問わず、期間を問わず、常にみんなが意識するということですけれども、どうなのでしょう。
(崎濱) 先ほどから言及されている日本の保守性というのは、政治的イデオロギーとしてどうこうというより、現状に対する満足度の高さというのがあるのではないか、という議論になっていたと思うのですね。ですが日本にも局地的に、沖縄も含めて、階級問題も見えやすくて、だからこそ対抗的権力としてのサブカルチャーというものが生まれる場所というのがあると思うのですね。例えば川崎とか大阪、あるいは、いわゆる在日カルチャーなどもそこに入ってくると思うのです。でも、ではそれが全体的に波及力を持ち得るかというのがやはり難しい問題としてあるよなというのはすごく感じるのです。
そういう抵抗権力のホットスポットのような場所以外で、情動みたいなものが喚起されるきっかけは日本社会の中にどの程度あるのか無いのか問題というのは、考えてみたいポイントです。ぬるぬるとしか変化しないし、変化してもまたぬるぬると現状に戻っていくという日本社会の特徴といいますか。
もう長時間になりますので、最後に簡単に一言ずつ、もう一度コメントを頂いてみたいなと思うのですが。川村先生、鵜飼先生、須川先生という順番でお願いできますか。
(川村) 本当に今日はありがとうございました。いろいろと自分の思考が整理されて、本当によかったなというように思います。最後のミクロポリティクスの問題とかというのはそういうふうにはっきりと言語化していなかったので、自分はそういうことを言おうとしていたのだなということを改めて認識しました。あと、やはりこれは問題なのではないかと指摘されることは確かにそうだなと思うことがたくさんで、それを考えていきたいなと思います。
あと、もう一つ、忘れていましたけれども、ネトウヨの話は実は他のところで、英語論文として共著で書いています(Satofumi Kawamura and Koichi Iwabuchi “Making Neo-nationalist subject in Japan: The intersection of nationalism, jingoism, and populism in the digital age” in Communication and the Public Vol.7, Feb. 2022)。
(川村) この論文も日本語とかに訳して、みんなに読んでもらえたら本当はいいかなとは思ってはいるのですが。
あと、今日は私が自分のオタク経験を告白した会でした(笑)。
(崎濱) 鵜飼先生、お願いします。
(鵜飼) はい。僕も同じ感想になってしまいそうです。やはり整理されたタイミングが絶妙で、現代社会の地図となるご高著でした。読者としてもすごく勉強になる本ですし、今回機会を頂いて、同じ本を何回も3回も4回も読むのは久しぶりだったので、貴重な経験になりました。
あとは、やはりコノリーの議論に関して、おっしゃったところというのは政治学の人間も読むべきという印象を強く持ち、惜しむらくは、もう少し早く出ていれば僕の2月の本で言及できたかなと思います。今後もお互いに機会があるならば、分野横断的に、こういう本がありますよなんて言って紹介できればいいかななんて、思いました。
やはり、こういうのは楽しいですね、単純に。日々生活に追われてしまうので、今回内容として面白かったのはもちろんですが、経験としても面白かったなというところでした。
すみません、感想になっていますけれども、そんなところです。
(崎濱) ありがとうございます。須川先生、お願いします。
(須川) はい。今日は本当に私も楽しかったです。いろいろと新たな発見などがありましたし、あと、自分のポピュラーカルチャーとどう接続していくかということのヒントをいっぱい頂いたので、これからまた学生と議論して、そのフィードバックを川村先生に聞いていただきたいなと思っております。本日はありがとうございました。
(崎濱) 本日は本当にありがとうございました。