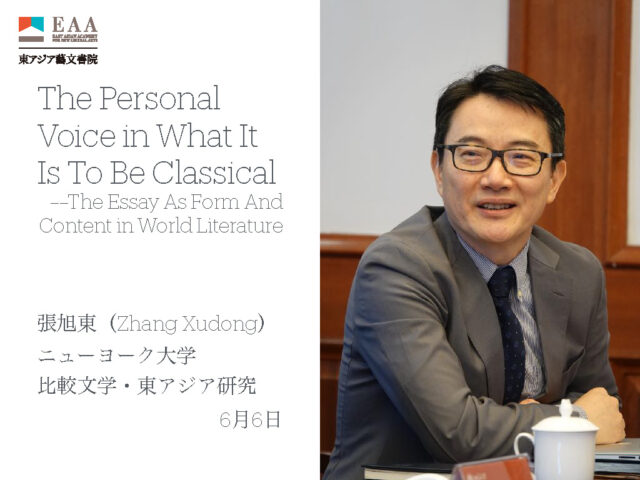
2025年6月6日(金)、EAAの主催で学術フロンティア講義「30年後の世界へ——変わる教養、変える教養」が駒場キャンパス18号館にて開催された。第八回は、ニューヨーク大学の張旭東氏が「古典」における個人的な声――世界文学の視座から散文の形式と内容を捉え直す」と題として講義を行った。
張氏は、「散文」(prose)という文学形式を軸に据え、近代中国文学における近代性と古典性の複雑な絡み合いについて論じた。小説とは異なり、変化性や多様性を特徴とする「散文」は、個人の断片的な声を表現しうるものであり、目まぐるしく変化する世界の様相を映し出す可能性を備えているものであるという。

張氏は、魯迅の「散文」《花のない薔薇》を取り上げ、古典性がいかにして近代的な情感表現の中に立ち現れているかを論じた。同作では、国家に対する辛辣な批判、激しい憤慨や絶望が、古風な文体を通して表出されている。その語りには、社会の対立と衝突、経済構造といった近代的・西洋的な概念が包摂される一方で、道徳的な怒りや伝統的な価値判断も滲み出ており、どこか古典的な響きが感じられる。
さらに張氏は、魯迅の「散文」と嵇康の《與山巨源絕交書》との類似性、そしてフランス啓蒙時代の哲学者の文章との連続性を指摘する。そして、主体的・個人的な声を担う近代的な語りと、個人性を抑えた古典時代の語りとの混交についての議論を深めた。
魯迅と嵇康の「散文」に内在する政治的批判性に関する張氏の指摘を受けて、報告者は次のような疑問を持った。「散文」は現代の政治社会といかに対話しうるのだろうか?特に、全体主義に覆われた社会において、「書く」という行為に必然的に伴う被傷性(vulnerability)については、いかに考えるべきであろうか。

例えば、現代中国の政治・社会的文脈において、書くことは必ずしも無傷で自由な営為とは言えない。政府を批判する文章を書いたがゆえに、国家による弾圧や拘禁、さらには亡命を余儀なくされる作家は少なくない。異性愛規範から逸脱する文学的表現もまた、制度的に周縁化され、抑圧されてきた。このような政治状況において、直接的な感情の表出を特徴とする「散文」は、魯迅の語りに込められた政治的批判性を手放すことなく、特定の感情が暴力的に抹消される文学の場に応答し、介入する可能性を持ち得るのだろうか。すなわち、変化性、多様性、そして社会的変化を鋭敏に捉えるという特性を活かすことで、「散文」は、語りえぬ情緒や想像力をそこに宿らせ、オルタナティブな抵抗の可能性を引き出すことはできるのだろうか。

報告・写真:魏韻典(EAAリサーチ・アシスタント)
リアクション・ペーパーからの抜粋
(1)「個人的な声を通して人類普遍的な真理を語る」ことが個人化が進んだ現代においてどのようにあるべきなのか、考えたいと思いました。
魯迅が当時の社会について個人的な激しい怒りをもって散文を書いたとき、古典のような道徳的重みを帯びているというのがとても興味深かったです。その人の個人的経験から出発したものの、全人類の心を打ち震わす、という現象はとくに芸術において見られると思います。古典が不滅の輝きを持っているのもそうしたことに由来するのだろうと思います。
私はアンリ・ベルクソンを研究しているのですが、彼の文学論でもほとんど同じことを言っています。曰く、最初から少数の読み手を対象にしてはならない。個人の存在の深みから発出した文章は人類全体に呼びかける、と。第一次世界大戦期を共に生きた魯迅とベルクソンが同じ原理を語っていることは注目するべきだと思います。それは単なる「時代精神」的な叫びなのか、それとも時代を越して存在する人類の在り方なのか。
わたしは後者だと信じています。個人化が究極に突き進んだ現代においてこそ求められる思考なのだと思います。スティーブ・ジョブズがその異常なこだわりで発明したアイフォンは、瞬く間に世界人類に受容されました。これが「個人的な声を通して人類普遍的な真理を語る」ではなくて何でしょうか。
ただし、個人的な声から発する普遍的な思想は、それ自体としてはただの思想ですが、人類にとって有益でも悪でもありうると思います。悪の最たる例は全体主義です。どのようにして共通善をこの資本主義の実社会で実現させるか、その枠組みが求められているように思えます。
– 教養学部(後期課程)・4年以上
(2)一番印象に残ったのは、魯迅の文章が「古い」と「新しい」を同時に抱え込んでいる、という点でした。「個人の声」を強く打ち出しながらも、その表現にはどこか古典的な節度や重みがあるというのは、たとえば「与山巨源绝交书」のような作品に顕著に表れています。激しい怒りをぶつけているのに、古い文体が取られ、自分から見ると言葉選びにも品格があるように感じました。そこに、単なる感情の爆発ではない、伝統との深い関わりが感じられました。講演の中で「古典の中の近代性」「近代性の中の古典性」という話がありましたが、魯迅の文章はまさにその両方を体現しているように思います。新しさを求めながら、完全に古いものを手放せない——むしろその「しがらみ」こそが、彼の文体の魅力なのだと実感しました。
– 大学院総合文化研究科・大学院修士課程








