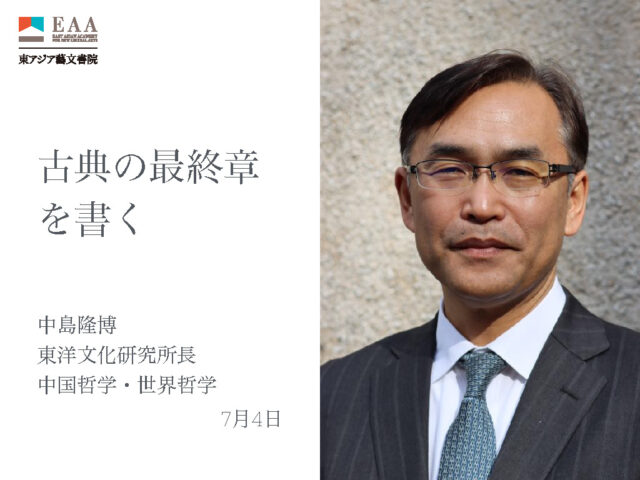
2025年7月4日(金)、第12回学術フロンティア講義「30年後の世界へ――変わる教養、変える教養」が、駒場キャンパス18号館ホールにて開催された。今回は東洋文化研究所長の中島隆博氏を講師に迎え、「古典の最終章を書く」と題した講義が行われた。

講演は、「一生をかけて十三経を読み続けた人は本当に幸福だったのだろうか」という問いかけから始まり、AIやインターネット技術の発展によって知識のあり方が変容する中で、かつて「博覧強記」を中心として捉えられてきた教養が徐々に変わりつつあることを指摘した。中島氏は、「考える」という行為は孤独の中で一人で行うものではなく、他者との友情の中で行われる共同の思惟であることを強調した。つまり、西洋近代が理想としてきたデカルト的な「完全無欠な個人(integrity)」の背後には、他者との関係の中で影響を与え合い、傷つき、変化していく「親密性(intimacy)」の次元が常に存在していたのだ。こうした「他者」に関する議論は、人間とAI、人間と動物との関係にまで拡張された。中島氏は、AIや動物を単なる道具や支配—被支配の関係で捉えるのではなく、真の「他者」として向き合い、その他者との関係の中で自己を変容させていく過程で複数の自己を発見していくことが必要であると述べた。結局のところ、他者との関係を通じて共に思考する場を開いていくことこそが、現代において重要な課題であるというのである。
さらに中島氏は、これまでのように博覧強記に代表されるインテグリティ(integrity)の観点から古典に向き合うのではなく、古典とのインティマシー(intimacy)の中で関係を築きながら共に思索していくことの重要性を説明した。そして、カスリス(Thomas Kasulis)の「古典とはその最終章が常に読者によって書かれるものである」という言葉を引用し、「これから私たちが『古典の最終章をどのように書き継いでいくのか』こそが、現代の教養が私たちに投げかける最も根本的な問いなのだ」というメッセージを伝えた。講演後のフロアでは、「共に思考する」ということは果たして無条件で可能なのかという問いをはじめ、現代社会の中で共に思考する共同体をどのように築いていくことができるのかなどに関する活発な議論が交わされた。

2025년 7월 4일(금), 도쿄대학교 EAA 주최로 학술 프론티어 강의 「30년 후의 세계로 ― 변화를 담는 교양, 변화를 여는 교양」 제12회가 고마바 캠퍼스 18호관 홀에서 개최되었다. 이번 강의에서는 도쿄대 동양문화연구소 소장 나카지마 타카히로(中島隆博) 교수가 「고전의 최종장을 쓰다」라는 제목으로 강연을 진행했다.
강연은 ‘13경을 평생 읽은 사람은 과연 행복했을까?’라는 물음을 던지며, AI와 인터넷 기술의 발전으로 지식의 존재 양식이 변해가면서, 과거의 ‘박람강기(博覽强記)’ 중심의 교양이 점차 변해가고 있음을 짚으며 시작되었다.
먼저 나카지마 교수는 ‘생각한다’는 것은 고독 속에서 홀로 이루어지는 것이 아니라, 타자와의 우정 속에서 이루어지는 공동의 사유임을 강조했다. 근대 서구가 이상으로 삼았던 데카르트적 ‘완전무결한 개인(integrity)’의 이면에는, 타자와 관계를 맺고 서로에게 영향을 주고받으며 상처받고 변화해 가는 ‘친밀성(intimacy)’의 차원이 언제나 함께 존재한다는 것이다. 이러한 타자에 대한 논의는 인간과 AI, 인간과 동물의 관계로까지 확장되었다. 나카지마 교수는 AI와 동물을 단순한 도구나 지배–피지배의 관계로 바라보는 것이 아니라, 진정한 타자로서 마주하고, 타자와 관계를 맺으며 스스로를 변화시켜 가는 과정 속에서 복수의 자신을 발견해 가는 것이 필요하다고 설명했다. 결국 타자와의 관계 맺음을 통해 함께 사유의 장을 여는 것이야말로 오늘날 중요한 과제라는 것이다.
나카지마 교수는 나아가 이제까지처럼 박람강기와 같은 완전무결성(integrity)의 관점에서 고전을 대하는 것이 아니라, 고전과 친밀성(intimacy)의 관계를 맺으며 함께 사유해 나가야 한다고 주장했다. 그는 토마스 카술리스(Thomas Kasulis)의 “고전이란 그 마지막 장을 독자가 항상 써 내려가는 것이다”라는 말을 인용하며, 앞으로 고전의 최종장을 어떻게 써 내려갈 것인가라는 고민이야말로 오늘날 교양이 우리에게 던지는 가장 근본적인 질문이라는 메시지를 전했다. 강연 후 플로어에서는 공동으로 사유한다는 것이 과연 아무런 조건 없이 가능한지를 묻는 질문을 비롯하여, 함께 사유하는 공동체를 현대 사회 속에서 어떻게 만들어 갈 수 있을지에 대한 구체적인 실천 방안을 묻는 등의 활발한 논의가 이어졌다.
報告・写真:洪信慧(EAAリサーチ・アシスタント)
リアクション・ペーパーからの抜粋
(1)私は専攻分野の基礎演習で、これまでの古典を読解する授業をとっています。その授業では決められた文献をみんなで講読しながら、それぞれが考えたことや疑問に思ったことについて議論します。その中で私は、全員が同じものを読んでいるのに、一人一人全く違うことを発想し多様なコメントをすることにいつも刺激を受けています。ここから活発な議論と個々の思考の高まりが可能になると感じています。このことは、すでに存在している文献や古典がいつの時代の誰にとっても同じように存在するのではなく、読まれることによって関与され、読者と共に要求し合う姿を表しているのだと感じました。こうした能動的で親密で寛容的な古典との関わり方、あるいは周りの人と共に取り組む議論への向き合い方は、これまで行われてきた厚い議論を未来に生かし、さらなる発展を叶える上で非常に重要になると思いました。– 後期課程(教養学部 3年)
(2)「傷がつけられてはじまる」という言葉が、私たちが教養を得るうえで必要なものを非常に的を射て説明していると思った。
この講義は「古典」をメインテーマにしているが、あまり自分にはなじみがないので、ほかのことで考えてみたい。
私たちは、普通、「傷がつかない」ように生きている。授業であっても、自分が興味のある/ある程度精通している授業を中心にとる。サークルであっても、普通は中学高校の延長線上にみている。
その中でも「傷がつけられる」行為というのがやはりあって、特に発表なんかは無条件に傷がつく行為なのではないのかと思う。教師からある程度のテーマを決められて、それについての文献を読み、発表の準備をして、容赦ないフィードバックをもらうという行為がそうである。
サークル活動であっても、自分が知らない世界に踏み込んで、かつ真剣に取り組んでみればまた同じようなことになるのではないか。
だから、私が特に思ったのは、思想的なことだけではなくても、まずは体を動かすことから始めてみてもいいのではないかということである。– 後期課程(教養学部・文科三類・3年)








