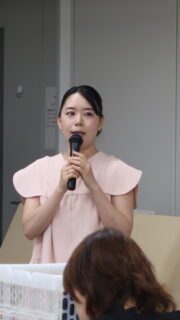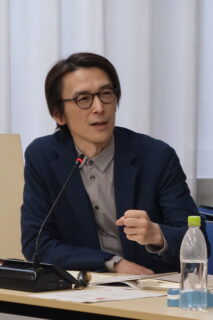2025年7月18日、東京大学東洋文化研究所大会議室にて「時間の中の民主主義——鵜飼健史著『民主主義はいつ成立するのか』公開書評会」が開催された。
2025年3月に刊行された『民主主義はいつ成立するのか』(岩波書店)の著者である鵜飼健史氏(西南学院大学)をお招きし、ご著書に込めた思いを語っていただいた。評者として、宇野重規氏(本学社会科学研究所/政治学)・白井聡氏(京都精華大学/政治学)・國分功一郎氏(本学総合文化研究科/フランス現代思想)をお迎えした。多岐に亘る議論を捌く難役である司会は、川村覚文氏(大妻女子大学/文化批評理論・メディア研究)がお引き受けくださった。
本書は、政治学における王道のテーマである「民主主義」を正面から取り扱った一冊である。「時間」という切り口から民主主義を論じた本はまだそれほど多くないが、鵜飼氏の説明によれば、近年注目を集めているテーマということだった(例えばThe Oxford Handbook of Time and Politics(2024)、高橋良輔・山崎望編著『時政学への挑戦』(2021)など)。
「時間」とは一般的に、過去・現在・未来から構成されるものであると考えられている。過去に規定されたり、あるいは未来を見越して選択・決定をしたり、といった形で、現在を生きる我々は少なからず「時間」に縛られている。そして、そのような縛りは、現在の政治的決定に何らかの影響を与える。例えば、ジャック・デリダが言うところの「来るべき民主主義」という概念や、宇野氏が指摘したようなハンナ・アーレントの言う「約束」という概念に象徴されるように、「未来」という時間軸は、他者への想像力に基づく倫理的な民主主義を鍛え上げる上で、一定の効果を持っているだろう。あるいは、「過去」についても、それを強く意識する、あるいは敢えて断ち切ることによって、現在という時間軸を拘束する力を持っている。
しかしそれは、本当だろうか?と鵜飼氏は投げかける。過去に思いを馳せ、未来のために良かれと思って行動しても、それは結局いま・ここを生きている我々の意思決定に基づいている、あるいはいま・ここが出発点となる想像力の範疇に収まっているという事実は見逃せない。つまり、どれほど慎慮(本書のキーワードの一つである)を心がけても、その限界は常に露呈し続ける。言い換えれば、その限界ぎりぎりの臨界点に「慎慮」を保たせようとすることが、「民主主義」の成立条件なのかもしれない。
印象深かったのは、「慎慮」と「民主主義」の関係性に関する議論の中で、民主主義の性質として「遅れて到来するもの」という点を指摘した宇野氏・鵜飼氏に対して、白井氏が、確かにそうかもしれないが、しかしそのように「後手」を踏んでは負けてしまう、と応答したことだ。昨今の政治状況を見れば、日本のみならず世界的に、民主主義が危機に瀕している(あるいは、民主主義そのものが常にそのような「危機」を宿命的に抱え込んでいる?)と感じる人は、少なくないだろう。日本に即していえば、民主主義はしばしば「改憲か護憲か」という対立軸で語られるが、そもそも解釈改憲が幾度も重ねられてきた日本においては、民主主義以前に、それを規定しているはずの憲法が、あるいは立憲主義が、すでに死んでいるのかもしれない、という國分氏の指摘が反芻される。
また、昨今のポピュリズム的な政治動向について、「上から目線」で啓蒙を図ろうとする知識人の戦略ミスを指摘した白井氏の議論も、大変興味深かった。啓蒙という方向ではなく、なぜそこに大衆は惹きつけられるのか、どうすればそのような状況に介入することができるのか、ということを考える必要があるという白井氏の指摘には、深く共感した。議論の最後で司会の川村氏が、ネオリベラリズムは「先手必勝」=「先制」を常に意識している、というブライアン・マスミの議論に触れたことも、大変示唆的であった(マスミは「情動」論の先鋭的な論客である)。「民主主義」をめぐる「時間」を扱ったこの日の議論の主題が、「慎慮」に始まり「情動」に終わったことは、単なる偶然ではなかったと思う。
本書評会は、平日にもかかわらず、学内外から約20名の聴衆が参加くださった。会社員の方やNPOで活動されている方など、いわゆる“アカデミア”外の方に多くご参加頂けたことは、今回特筆すべきことの一つであろう。本書及び登壇者への注目はもちろん、参院選を控えた金曜日の開催ということも影響していたかと思われるが、それに留まらず、日本社会における「政治」の変節に際し、「民主主義」を再考しようとする人々の思いを感じた。

報告者:崎濱紗奈(EAA特任助教)