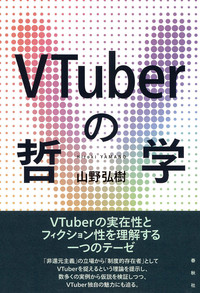2025年7月19日、東京大学駒場キャンパス18号館ホールにて、「Virtualの存在論——虚構、リアル、情動(山野弘樹氏×川村覚文氏対談)」が、対面・オンライン(Zoom)のハイブリッド形式で開催された。本企画は、昨年度より開催してきた「情動と政治」シリーズの第二弾である。第一弾として企画した「『情動、メディア、政治 ——不確実性の時代のカルチュラル・スタディーズ』公開書評会」に続いて、今回も川村覚文氏(大妻女子大学/文化批評理論・メディア研究)にご登壇頂いた。対談相手には、『VTuberの哲学』(春秋社、2024年)の著者である山野弘樹氏(千葉工業大学/哲学)をお迎えした。というのも、第一弾の際に川村氏と須川亜紀子氏(横浜国立大学/メディア研究)のディスカッションの中で、声優ライブが喚起する情動について触れられた際、VTuberの場合はどのような情動が喚起されるのだろうか、という話題が出たという背景がある。ポール・リクール研究をはじめとしてフランス現代思想に造詣が深く、なおかつ創成期のVTuber研究の重要な一角をなしておられる山野弘樹氏にご登壇をご快諾頂けたことは、幸甚であった。
VTuberとは、対談で川村氏が指摘したように、マンガ・アニメ・動画・メタバース空間など、既存及び最新の技術の交錯地点に立っている存在(媒体)である。そのような存在であるところのVTuberのコンテンツを視聴するということは、その実どのような体験なのだろうか。それは、山野氏が指摘したように、バーチャル/リアル、という二項対立では決して捉えられない体験である。VTuber自体は、確かにバーチャルな存在ではある。しかし、VTuberは我々と同じ地続きの日常を生きている存在でもある。一例として山野氏は、VTuberが語る日常のエピソード(今朝コンビニでサンドイッチを買った/満員電車に乗って大変な思いをした等々)に触れた。そのエピソードに触れた時、視聴者の側で喚起されるイメージとは、どのようなものだろうか。それは、VTuberという仮面と「中の人」、という二つの要素に明瞭に切り分けられるものではなく、あたかもVTuberがそのままの姿・かたちで我々の生きるこの「リアルな」世界の中を動いて活動している様子が想像されるのではないか、と山野氏は指摘する。
このことは、川村氏が『情動、メディア、政治』の第4章で『ラブ・ライブ!』や『ウマ娘』を具体的に分析しながら明らかにした、声優によるライブコンサートで生じる情動のあり方に関する議論に接続できるだろう。声優自身がキャラクターに扮して劇中の歌を歌うコンサートに、(声優自身は、実はキャラクターには似ても似つかないのにも関わらず)なぜ人々はあれほど熱狂するのか。川村氏によれば、観客は、声優が発する声(まさにキャラクターそのものの声)によって情動が喚起され、キャラクターそのものが現前しているかのように感じることができる。それは決して錯覚(あたかも現前しているように感じる)というものではなく、むしろ、情動に支えられたキャラクターの現前そのものの体験、というべきものである。
だが、VTuberと声優ライブには、次のような違いがある。前者は、アニメルックを伴うバーチャルな存在が日常と地続きの世界を生きている存在として視聴者に体験されるのに対して、後者は、生身の人間がアニメ作品の世界を生きる存在として体験される。この違いを、両者の決定的な差異として捉えるのか、それとも、これを同様の体験として捉えるのか。前者の立場をとれば、我々生身の人間が生きているこの世界に「リアル」の重点を置くという立場が前提とされるだろうし、反対に、後者の立場をとれば、リアルとバーチャルの、あるいはリアルとフィクションの境界を前提とせずに、存在について思考することになるだろう。当日の議論としては、山野氏はどちらかといえば前者の立場で議論を進め、川村氏は後者の視点から議論を展開したことが興味深かった。
左から順に、山野弘樹氏の著書『VTuberの哲学』(春秋社、2024年)、川村覚文氏の著書『情動、メディア、政治——不確実性の時代のカルチュラル・スタディーズ』(春秋社、2024年)
対談後、フロアやオンライン参加者から多くの質問が寄せられた。例えば、声優を「神をその身に降ろす巫女」、VTuberを「神そのものの顕現」と解釈する視点など、対談での議論をさらに深化させるコメントが届いた。(話が横に逸れるが、筆者は拙著で沖縄における神観念について検討したことがあるが、沖縄の宗教的シーンにおいては、神をその身に降ろす存在=カミであるという認識のもと、巫女と神が別々の存在というよりは地続きの存在として認識されている。)
今回の対談で浮かび上がった、リアル/虚構という二項対立図式ではない世界の体験のあり方、あるいはその認識方法は、単にVTuberという特定の存在・事象にまつわるものではなく、様々な情報技術の発展に伴い、わたしたちの生活のあり方や存在様式そのものが変容していく有様を思考する上で、一つの指標となるだろう。

報告者:崎濱紗奈(EAA特任助教)