2021年7月12日、東洋文化研究所第一会議室にて、高橋哲哉氏(東京大学名誉教授)と中島隆博氏(EAA院長)のダイアローグが開催された。オリンピック開幕が目前に迫る中、四度目の緊急事態宣言が発令された直後ではあったが、最新の注意を払い環境を整えた上で、対面での開催に踏み切った。
ダイアローグ・シリーズでは、対談相手となる先生方に、幼年期から現在に至るまでの研究者人生を語り起こして頂いている。こうした貴重なお話を拝聴するには、オンラインだと少し味気ない。とりわけ今回のダイアローグは、高橋氏と中島氏の年来の友情があってこそ実現したものであったので、対面方式での開催が叶ったことは幸いであった。
高橋氏は1956年、現在の福島県いわき市(当時の平市)に生まれた。福島県内を転々とした経験やお父様の思い出を、一つずつしっかりと確かめつつ、懐かしそうに語ってくれた。「もはや戦後ではない」の掛け声に象徴されるように、高度経済成長期の右肩上がりの時代だった。その発展の波が地方都市にも押し寄せる中、海や山の近くの小さな町で楽しく過ごした幼年時代であったという。
そのような中、後に哲学、とりわけヨーロッパ哲学を志す原点となった本がある。ソクラテスやニーチェを少しずつ齧り読みし始めた折、当時中学生だった高橋氏の印象に強く刻み込まれたのは、『世界の旅』という写真全集に収められたフランス・ブルゴーニュ地方のヴェズレーという町であった。特に高橋氏を魅了したのは、夕日に照らされ佇むサント・マドレーヌ寺院の姿であった。ヨーロッパに対する憧れは、文学によっても醸成された。中でもドストエフスキーに惹かれ、そこに漂う存在論的態度は、後に哲学を専門する一つのきっかけを作った、と高橋氏は振り返った。
その後、大学に進学した高橋氏はフランス語を第二外国語として学んだ。入学直後、坂部恵先生の講義の初回に、先生がミシェル・
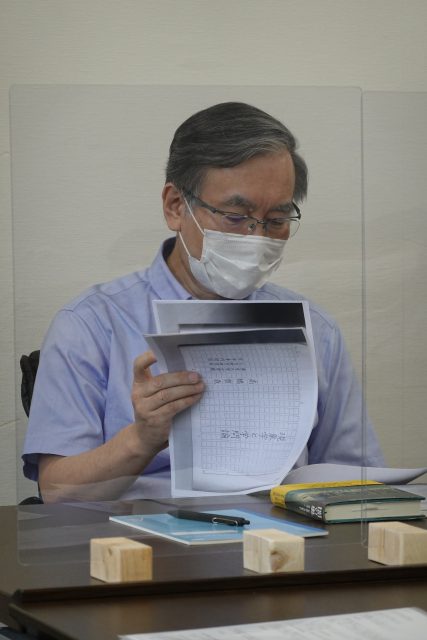
1992年秋から1994年春までの期間をフランスで過ごした。帰国後は映画『ショア』(クロード・ランズマン監督)の上映や、加藤典洋氏との間に繰り広げられた「敗戦後論」論争、そして慰安婦問題や靖国問題を中心とする歴史認識問題といった事柄に深く関与していった。ひとことで言えば「政治」的であるこれらの事柄に関わるに際して高橋氏が重要視したのは、次のことである。「表現不可能なものの表現」という思想的問題を前に「(証言を)聞く」という態度を貫くこと。「判断不可能なもの」「決定不可能なもの」というアポリアを突き詰めた上で、それにもかかわらず「脱構築不可能なものとしての正義(justice)」を求めること。

デリダの議論を踏まえて、不可能としか言えないようなアポリアを引き受けつつも、実践的には決定しないということは不正になる、と述べた高橋氏に対して、カール・シュミット的な決断主義と、アポリアを踏まえた決断はどのように異なるのか、と中島氏が問うたスリリングな場面もあった。これに対して高橋氏は、決断という契機の只中に決定的な要素としてそこにある「他者」、そして「私における他なるもの」すなわち予見不可能な到来するもの、の重要性について論じた。
ほかにも、「敗戦後論」論争や沖縄の米軍基地の県外移設をめぐる論争についても多くのことをお話頂いたが、その多岐にわたる議論の詳細については、今後発刊予定のブックレットを是非ご覧頂きたい。

ダイアローグの最後、「今後の哲学的展望は?」という中島氏の問いかけに対し、高橋氏は次のように応答した。研究を志した早い時期から、いわゆる「哲学」という枠を定めること自体に問題・限界を感じてきた。重要なのは「哲学」という枠組みの中で「哲学」について研究することではなく、「哲学」を実践的営みとすることである。その実践とは、様々な出来事や概念、そうしたことの可能性の条件を常に問い返していくことに他ならない。
フッサールにおける「責任」論を出発点として、自身も「責任」そして「他者」という問題系に深く関与してきた哲学者・高橋哲哉氏の信念に触れた、貴重な三時間であった。
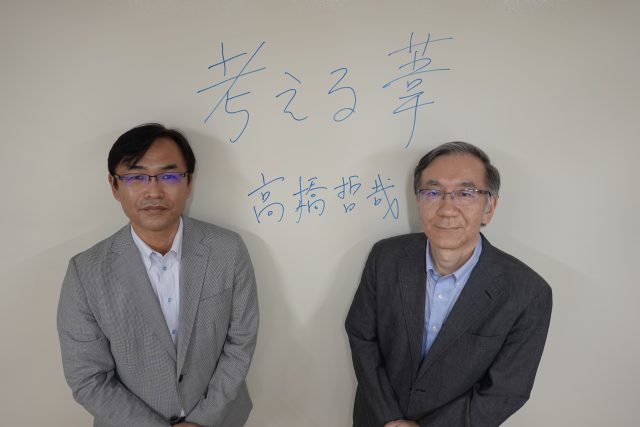
報告者:崎濱紗奈(EAA特任研究員)
写真撮影:立石はな(EAA特任研究員)










