2025年3月21日(金)13時より、第8回EAA研究会「東アジアと仏教」が開催された。今回は、今回は柳幹康(東洋文化研究所准教授)が司会のもと、伊丹(中国人民大学講師)による「林羅山と医学知識:『本草綱目』を手がかりに」と題する研究発表が行われた。当日の参加者は、対面・オンラインを合わせて8名であった。
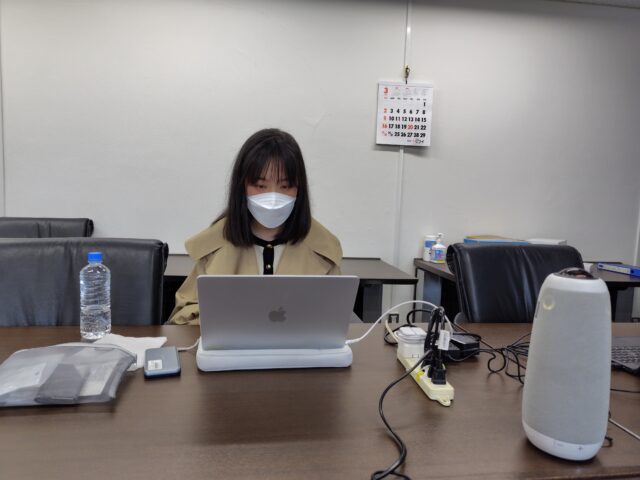
250321130353002
林羅山は近世初期の幕府儒官として知られており、幼少期には建仁寺に入って禅僧のもとで学ぶなど、仏教との深い関わりを持っていた。しかし実は、彼は医学にも強い関心を抱いていた。本発表において伊氏は、当時、医学知識が秘伝的な伝承から一般社会へと広がりつつあった背景に着目し、林羅山が講釈や著述を通じてその普及に貢献しようとした点に注目した。とりわけ『本草綱目』を具体例として、羅山がどのように医学知識を学び、活用したのかが考察された。
従来、林羅山と医学の関わりについては、彼が長崎で『本草綱目』を入手し、幕府に献上したことが医学史上の重要な出来事として知られてきた。しかし伊氏は、羅山の医学への関与はそれ以上に深いものであったと指摘する。発表では、『羅山林先生集』に収められた年譜、賦、書簡等を詳細に分析した成果が示され、羅山が多数の医師と交流を持ち、幅広い医学書を読んでいたこと、さらには医師に向けて医学知識を伝えたり、医学書の注釈を著したりするなど、相当な医学的素養を備えていたことが明らかにされた。また、彼が自らの知識を文学作品や随筆、注釈に積極的に応用していた点も示された。
とりわけ『本草綱目』との関係は顕著である。伊氏は、林羅山がこの書物をどのように学び、自身の著作活動に取り入れたのかを、いくつかの具体例を挙げて紹介した。たとえば、羅山は『本草綱目』序文の注釈書として『本草序例』を執筆し、さらに内容を抜粋して本草辞書『多識編』を編纂している。また、『徒然草』の注釈書『野槌』や、仮名草子『怪談全書』などにも、『本草綱目』の記述を反映した医学的知見の痕跡が認められる。
このように林羅山は、仏教、儒教のみならず、医学に対しても深い造詣を持ち、その知識を多様なかたちで展開していたことが示された。発表後の質疑応答では、羅山の医学知識についての先行研究、また彼の知識がその後の知的潮流に与えた影響について活発な議論が交わされた。
本研究会を通じて、林羅山の知的活動の多面性と、学際的な視点の重要性が改めて浮き彫りになった。今後も、思想・学問・文化が交差する場としての羅山の再評価が期待される。
報告者:伊 丹(EAAフェロー)








