この記事はイベント後半の報告です。前半についてはこちらをご覧ください。
5分間の休憩を挟み、会は後半に移った。司会による簡単な紹介の後、前島志保氏による発表「座談会というスキャンダル――談話的公共圏の成立」が行われた。現在の日本のあらゆる文字媒体に広く見られる座談会形式記事の歴史や社会的評価・役割の変遷から、このスタイルがいかなる言説空間の構築に寄与したかを明らかにするものである。
前島氏は最初に、これまで文芸誌・総合雑誌を中心に研究されてきた、昭和初期における座談会形式記事の流行についての定説を再検討する必要性を指摘。会話形式の記事としては文学誌では合評会記事があったが、様々な話題に関するものとしては婦人雑誌と当時呼ばれていた女性向け雑誌が取り入れ始め流行し、その後、『文藝春秋』が「座談会」という名前を付け広めたということを示した。座談会記事形式はコストパフォーマンスに優れた編集手法として広まっていったが、婦人雑誌では積極的に使われたのに対し、総合雑誌では取り入れが遅れ、使用範囲も限定的だったという。発表では、この差の背景を文体・記事形式自体の内在的要因に求める見方が採られた。

この時期の座談会形式記事のテクストで採用された文体は口語敬体だったが、この文体の定着にも歴史的な文脈がある。口語体は明治20年代に口語敬体と口語常体の2つに収斂し、第一次国定教科書で採用されて以降、雑誌の主要な文体になっていく。その過程で、次第に口語敬体は子ども・女性の文体として、口語常体よりも一段低く位置付けられていった。また、談話体の記事は明治期にも存在していたが、このスタイルもまたジャーナリズムのヒエラルキーの中で低位に置かれるようになった。婦人雑誌は「女性的」とみなされるようになった文体と内容、記事形式を引き受けることで、女性向けの媒体としての性格を強めていった。
次いで「透明な文体」の成立として、文体と事実との緊張関係が注目された。当初は、使用されている文体の如何にかかわらず、談話形式の記事にはあくまで談話であることを明示する書き方が採られていたが、1910年代にはそれが消滅。同時に、口語敬体が談話体であるという認識も広まる。つまり、文体の媒介性が後退し、「表象するもの」と「表象されるもの」の転倒が生じるようになったのだ。「談話形式で書かれたことは全て話された事実である」と無意識に受け取れるような状態になったことと関連し、様々な批判も受けるようになっていった。
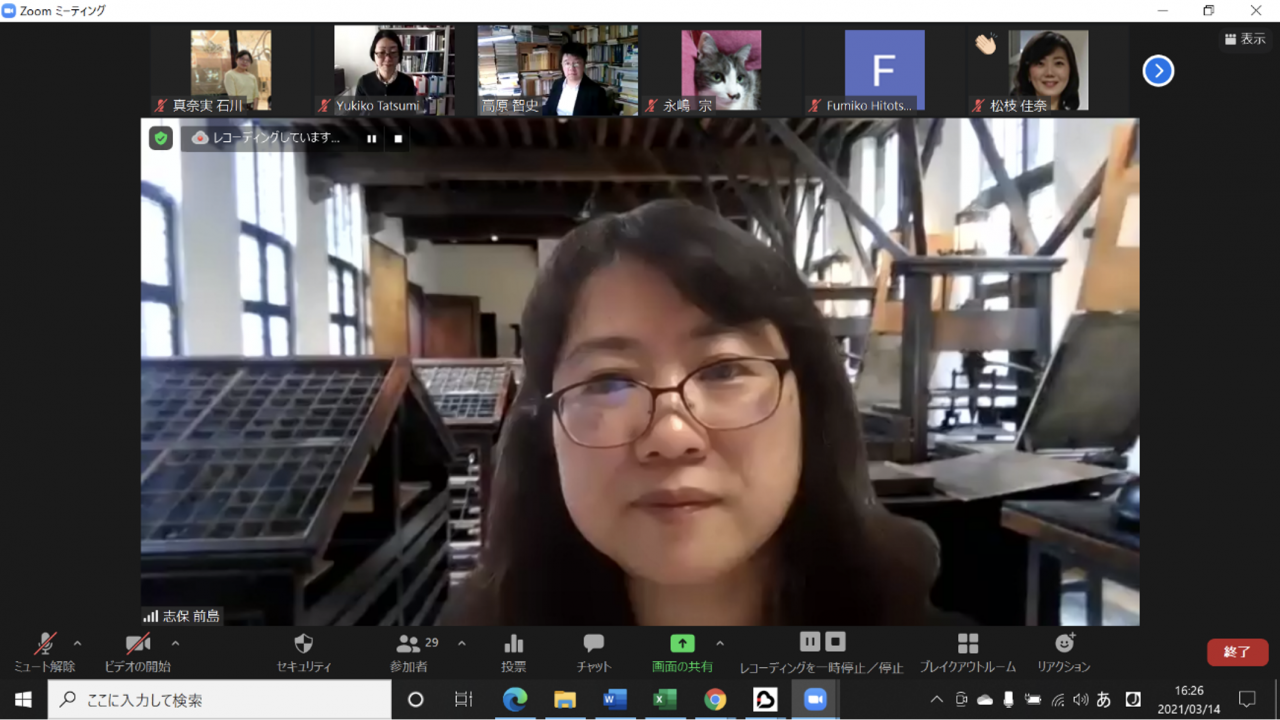
口語体の定着以降、総じて談話形式の記事は、文体・内容ともに周縁的、「女性的」、異端の文体による記事であった。しかしその文体はやがて広がりを見せ、男性を婦人雑誌の読者として呼び戻し、座談会が流行した頃には、「男性的」とみなされていた『改造』『中央公論』などの総合雑誌をも侵食することにもなった。その意味で婦人雑誌における談話形式の記事(特に座談会形式の記事)は、編集や参加者の選別などにおいて限界はあったものの、性差・年齢・地域・階層の差を越え様々な人々を言論の空間に巻き込む、一見「民主的」な場を提示していた、と結論付けられた。
フロアからは、談話体形式の記事が「女性化」したという内容について、より詳細な説明を求める質問があった。議論はその後の懇談会でも続き、明治期の座談形式の記事と昭和期の座談会記事との違い、座談会記事形式の世界的な広がり、日本語の言文一致運動とロシアにおける近代的文体の成立との比較、ロシアとヨーロッパおよび北米の出版界のつながり、さらには、それぞれの地域における近代的な出版・報道文化および印刷文化の展開を世界史的な視野から考え直す必要性などが、活発に話しあわれた。

三回目のリモート開催となった今回の研究会は、ロシアの事例を介して、東アジアと欧米のジャーナリズムの展開を横断的に考察する視野を拓く契機となった。また、前回に引き続き、京都、北海道、韓国、ドイツといった遠方からの参加者も増え、オンラインによる開催の強みが活かされた。と同時に、対面開催による自由闊達な議論と交流の再開を望む声も出た。両方を活かした形で会と議論を重ねていければと思う。
文責:永嶋宗(東京大学大学院総合文化研究科博士課程)
報告文監修:前島志保(総合文化研究科准教授)









