11月の広州は気候がきわめて快適である。中山大学人文高等研究院と東京大学東アジア藝文書院(EAA)による共同企画「文人与芸術」学術文会が、2025年11月6日から10日にかけて中山大学にて開催された。本企画は「文会」と名づけられているように、一般的な意味での学術会議とは一線を画し、むしろ伝統的な文人雅集の形式に近い。例えば一つの枢要な関心は「人」そのもの(人間性や、人の在り方、世界といかに向き合うかなど)に置かれ、学術世界の外部に広がる、生活と接続したような思想や芸術を多面的に探究することを目指している。

今回の文会には日中両国の研究者が集い、7日には密度の高い学術討論が行われた。まず渠敬東氏(北京大学教授)と曹家斉氏(中山大学教授)の挨拶に続き、陳少明氏(中山大学)が「芸術と命名」をテーマに、文字・言語および“意味付与”の行為が芸術(とりわけ中国の文脈において)にいかに示されているかを論じ、観念芸術などの特質を再考した。石井剛氏(東京大学教授)は、清代考証学における「古」(戴震)の概念に着目し、のちに王国維によって「古雅」という美学範疇として明確化された経緯を踏まえつつ、当時の知識人の文史的素養や考古学の発展を考慮に入れ、文史の枠を超えた美学的趣味の可能性を提示した。朱天曙氏(北京語言大学教授)は清代画家金農を取り上げ、書・画・詩が統合された文人芸術における禅意のあり方を論じた。柳幹康氏(東京大学准教授)は白隠の禅画を素材に、仏教思想(史)的観点から悟りや利他修行を改めて検討した。星野太氏(東京大学准教授)は、中国学界ではまだ広く知られていない書家・陶芸家である北大路魯山人を「坐辺師友」という概念から考察し、人と自然万物との別様の関係性を提示した。本ブログ報告者の丁乙(北海道大学講師)は近代中国美学の発展枠組を再整理しつつ、近代日本美学の展開を参照し、近代中国が東西の学問を平等に位置付けた点を強調した。鄧小南氏(北京大学・中山大学教授)は宋代書法の多様な資料を提示し、技法や様式などに注目するのではなく、これらを宋代史研究の重要史料として位置づけた。従来は文献から推測するしかなかった歴史的場面が、これらの資料によって再構成され、書の作品は新たな「身分」を獲得することになる。また、胡妍璐氏(中山大学講師)は琵琶曲「十面埋伏」の生成や発展過程を中心に、歴史と芸術作品の新たな関係を示し、さらに現場での演奏を通じて、会場を歴史的情景の中へと誘った。最後の総合討論では潮田洋一郎氏(EAA名誉フェロー)から日中間の美術の相違について指摘がなされ、活発な議論が行われた。


8日には、会場を塱頭村へ移し、祠堂建築と文化園の見学を経て、明代の大儒・陳白沙の読書所に由来する「春陽台」劇場にて、渠氏が講演を行った。「遠望不離坐外」という視点から、北宋山水画の名作・范寛《溪山行旅図》について極めて詳細な解説を試みた。西洋絵画とは異なり、中国絵画の構成と叙述は「気」(気運や気勢)の流動なしには語れず、それらのリズムのあわいに、人境・道境・神境が形づくられる。夕刻には唐寅などの作品をめぐって議論を行った。その後、張瑞図など重要作品の鑑賞も続けられた。
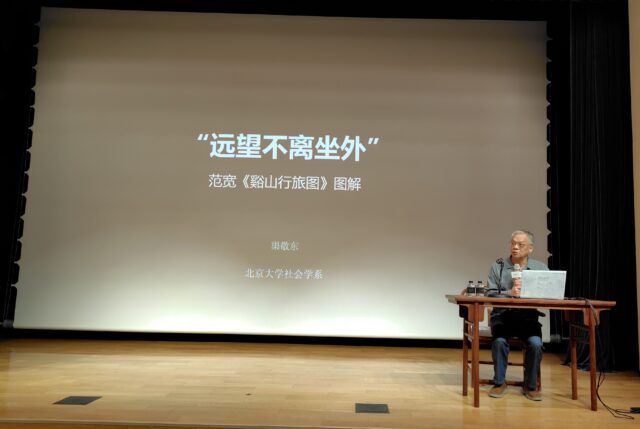
9日には栄宝斎を訪れ、「何以山水(What is Shan Shui)」展を鑑賞することで、20世紀中国山水画の代表的大家と現代の若い芸術家の作品の対話を通し、中国独自の社会文脈において「山水」が担ってきた意味と役割を新たに考え直す機会となった。その後、瓷青紙を用いた貴重な唐代写経などを実見し議論を深めた。その後、光孝寺・六榕寺での実地調査を終え、温かく湿った広州の夜風のなか、今回の名実ともに「文会」と呼ぶべき催しは幕を閉じた。綿密な文献調査のみならず、細やかな会話の端々から、さらには生活の具体的な場に身を置くことで、文人と芸術のより立体的で多元的な可能性を、五感を通して味わうことができた。

報告者:丁 乙(EAAフェロー/北海道大学講師)








