2025年5月14日、EAA本郷オフィスにて第28回藝文学研究会が開催された。本ブログ報告執筆者の崎濱紗奈(EAA特任助教)が、「情動論の現在」というタイトルで提題を行った。EAA本郷オフィスでは毎年度、一つのテーマを定め、それに関連して各々が自らの専門的見地からプロジェクトとしての研究を進めていくというスタイルを採っている。今年度は、崎濱が昨年度より取り組んできた研究テーマである「情動」を共通のトピックとして検討することが、4月に行った準備会の場で決定された。
「情動」とは、直感的に理解できるようでいて、実はそうではない、少し複雑な概念である。「情動」はしばしば「感情」と混同され議論されてきた。そのような議論の枠組みを否定することが目的ではないが、しかし今回の研究会では、わたしたちの間では「情動」をもう少し厳密な概念として定義することを確認し合った。
「情動」とは、存在論的な背景を持つ概念である。昨今現代思想で盛んに議論されている「情動」論は、その主たる論客であるブライアン・マッスミが、フランス現代思想を代表する哲学者であるジル・ドゥルーズの研究者であることもわかるように、「情動」概念は、マルティン・ハイデガー以降の存在論的な発想の延長線上に成り立っているものであることを理解する必要がある(※当然、それは連綿と切れ目なく続いてきたものではなく、批判的な省察を繰り返すことによって断続的に引かれてきた「延長線」である)。
「情動」論の一番の眼目は、カント的な超越論的理性を中心に統合された近代的な人間像及び人間中心主義を根本から批判することにあると言える。なぜ「情動」論がそのような立場を採るのかと言えば、その理由は明白である。それは、現在の我々の生活を根底から基底している、もはやインフラとも言うべき「プラットフォーム資本主義」において、いかなる権力が働いているのかを明らかにするため、そして、その権力に対抗するためにいかなる戦略が必要かを構想するためである。「情動」論が持つ切迫した問題意識は、従来の権力論はもはや現状に対して有効な批判的介入を行う能力を失っている、という見立てに基づいている。
従来の左派的言説は、支配者/被支配者という二項対立に象徴されるような二分法的な権力観を結局は前提としてしまい、支配権力への抵抗/からの解放を目的とした権力批判が繰り返されてきた。こうした発想は、権力の「被害者」であるにもかかわらず、それを「正しく」認識できていない「大衆」に対して、「啓蒙」を行おうとする。例えば、昨今のトランプ現象に象徴されるような(あるいは日本の文脈で言えば「ネット右翼」と呼ばれる言説に代表されるような)動向にジョインしていく「大衆」に対して、その情報源が「フェイク」であることを指摘したり、そのような「フェイク」に騙されないためのメディア・リテラシーを身につけるよう教導しようと試みたりする。もちろん、こうした試みが全く功を奏していないと言うつもりはないし、それが必要となるシーンもあるだろう。だが、こうした啓蒙主義的な左派の態度(左派にも色々あるが、ここでは「自由―民主主義」を支えるエリート的なリベラル勢力を想定しよう)が纏っている“上から目線”な態度が「大衆」から忌避され、左派が啓蒙しようとすればするほど、「大衆」たちは逃げていくといった状況が、実のところもう何十年も放置されてきたのではなかったか。
「情動」論において、「情動」が「感情」とは異なるものとして峻別される理由も、こうした問題意識に根ざしている。なぜなら「感情」とは、すでに姿・かたちを与えられた状態であるという意味において、「理性」と対立するものではないからだ。これに対し「情動」とは、「感情」が成立する以前の潜在的・潜勢的領野において駆動するものであると言える。さらに踏み込んで言えば、潜在的・潜勢的領野から、何らかの姿・かたちを帯びたもの(「感情」はその一例である)が「創発」(偶然性に満ちた潜勢的領野から、何かが突如生まれ出ること)するための一つの契機となるもの、それが「情動」である。先に述べた「トランプ支持」「ネット右翼」といった現象に即して言えば、それは、それを支持する人々が明確な理性や感情を持って動いた結果であるのではなく、情動によって創発された一つの姿・かたちに過ぎない。こうしたプロセスを経て出来した現象に対して、啓蒙主義的な態度をいくら示しても、そもそもの潜在的・潜勢的領野にうまくアプローチできていないのであれば、それはその場しのぎであるとすら言えない、虚しい方法になってしまうのだ(もちろん、理性が完全に死したわけではないから、このような方法も全く無効になった訳でもないだろうが)。崎濱は、沖縄のいわゆる基地問題をめぐる言説を分析するために、「情動」論から学必要性をここ数年ずっと感じてきた。
世界を潜在的・潜勢的領野と、それが顕現した領野との関係性において捉えるというコスモロジーは、「東洋」の思想・哲学的伝統からすれば、何も新規な物ではない。朱子学を専門とする田中氏(東洋文化研究所)、仏教学を専門とする柳氏(東洋文化研究所)からは、それぞれの見地から、ハイデガー以降の存在論において議論されてきたことはどのように解釈され得るかについて、非常に興味深い指摘がなされた。ディスカッションの中で浮上してきたのは、「情動」と「倫理」をめぐる問題だ。「情動」論においては、倫理的な態度は峻拒されるように見える。なぜならそれは、伝統的な左派のお家芸(「正しさ」を設定し、その統制的理念に対して漸近することを目指す態度)であり、そのお家芸がゆえに権力批判をし損なってきた、と考えるのが「情動」論の立場だからだ。だが、権力批判を行い、世界を「望ましい」方向に変えていくという志向性は、本当に放棄してしまってよいのだろうか。そもそも、そのような志向性を放棄してしまったら、「情動」論が向かう先はどこにあると考えればよいのだろうか。朱子学や仏教学とは、そもそもそのような志向性を実現化するために連綿と続いてきた思想的伝統であった。次回以降の研究会においても、この問いをめぐって検討を重ねていくことになりそうだ。
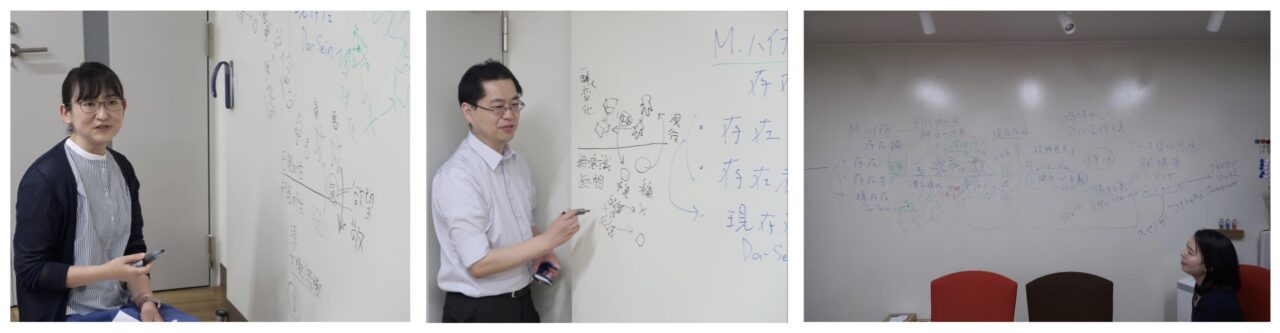
報告者:崎濱紗奈(EAA特任助教)








