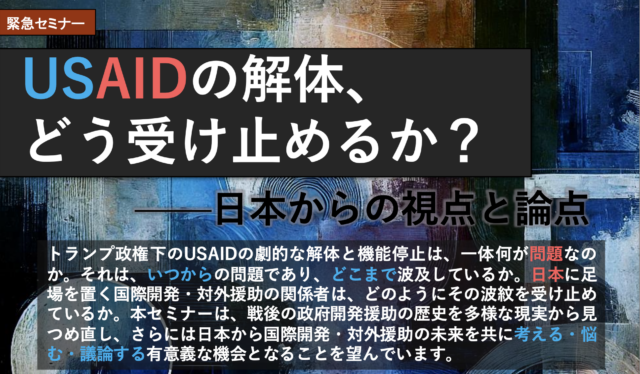
1、本セミナーが開催される背景
「USAIDの解体、どう受け止めるか?——日本からの視点と論点」と題されたセミナーが2025年4月19日(土)に法政大学市ヶ谷キャンパススカイホールにて開催された。国際開発学会「開発論の系譜」研究部会、法政大学大学院メコン・サステナビリティ研究所、東京大学東アジア藝文書院「開発と文学」研究会の三者による共催である。
第二次トランプ政権の発足以来、その一挙一動が世界に大きな波紋を広げる中、特に米国国家開発庁(United States Agency for International Development、USAID)の実質的な解体と再編の動きは開発援助に関わる人たちに衝撃と混乱をもたらしている。現場の声を集め、共有することの重要性を痛感した企画者と講演者は、当初情報を広く発信するシンポジウムを構想したものの、状況の流動性と情報の錯綜を考慮し、まずは有識者が信頼できる環境の中で意思疎通を図り、問題の軸足を定めることを優先した。そのため本セミナーには「チャタムハウスルール」を適用し、参加者も個人的なネットワークや限定的なグループ発信を通じた招待を中心とした。それにもかかわらず、当日は100名を超える対面参加者が集まり、関心の高さがうかがえた。
現在進行形で変化し続けるUSAIDの再編と解体の混迷が深まる状況の中、本セミナーは以下のように、「現状の把握」「論点の理解」「日本への含意」という三部構成で展開された。
趣旨説明‥汪牧耘(東京大学)
【第Ⅰ部】現状の把握
「最近の国際援助協調と米国の動向」 馬杉学治(国際協力機構)
「医療・保健分野の視点からみる援助現場の現在」 稲場雅紀(アフリカ日本協議会)
【第Ⅱ部】論点の理解
「経済・財政にみる援助の位置づけと国益」 米山泰揚(国際開発学会所属(元世界銀行駐日特別代表) )
「日本のODAの事業仕分け再考」 松本悟(法政大学)
【第Ⅲ部】日本への含意:対談・ディスカッション
※ プログラム・登壇者紹介はこちら
本セミナーは、政治、経済、外交の単一の視点からは捉えきれないアメリカの政策動向と影響を国際開発援助という切り口から理解する試みである。USAIDの劇的な解体と機能停止が引き起こす問題の所在と波及範囲、そして日本を拠点とする国際開発援助関係者がその影響をどう受け止め、対応していくべきかを考える機会となった。
以下は、本セミナーの各講演者の発表およびディスカッションをまとめたものである。なお、文中意見にわたる部分は報告者個人のものであり、講演者や報告者の所属する組織の見解を表明したものではない点にご留意をお願いしたい。
2、現状の把握と論点の理解:揺らぐ国際開発援助の風景
USAIDで起きていること—「沼地の水抜き」の衝撃
アフリカ日本協議会の記事「トランプ政権、USAIDの解体・国務省統合の方針を議会に通知」が示すように、1月の「米国対外援助の再評価と再編成」大統領令から3月末の実質解体宣言まで、USAIDの解体と再編は疑問を多く含むものであった。米国政治では以前から使われていた用語ではあるが、トランプ大統領が選挙活動中から殊更言及していた「ディープステート(深層政府)」「ドレイン・ザ・スワンプ(沼地の水抜き)」「ディスマントル・ザ・フェデラル・ビュロークラシー(連邦官僚制度の解体)」という国内向け3Dとでもいうべき政策理念の下、USAIDの契約の86%が打ち切られることとなった(参照)。特に地理的にはウクライナ、コンゴ民主共和国、エチオピアなどが削減幅の上位に挙がり、アフリカが上位10カ国中5カ国を占めた(参照)。分野別では難民支援や財政支援が比較的継続される一方(参照)、農業、ガバナンス、保健医療分野が大幅に削減される傾向が明らかになった(参照)。そして、本セミナー開催直前にUSAIDを含む対外援助の見直し期間の30日間延長が伝えられ、その過程はまさに現在進行中といえる(参照)。
この政策の端緒はトランプ第一次政権でも試みられたが、当時は議会などの動きで実現は食い止められた。その後のバイデン政権時代に保守系シンクタンク「ヘリテージ財団」が「プロジェクト2025」を起草し、次期共和党政権が取り組むべき政策の青写真を描いた。これにはトランプ第一次政権に関係した多くの人物が協力していた。その中の第9章はMax Primorac(ヘリテージ財団シニア・リサーチ・フェロー、元USAID幹部)がUSAID改革の必要性を明記していたものの、解体までは言及していなかった。「プロジェクト2025」はあまりに極端な提案が多かったため、トランプ氏は世論を念頭に同プロジェクトへの関与を否定したが、後に自ら「プロジェクト2025」の路線を継承している「Agenda 47」という選挙公約集を発表した。但し、その中でもUSAIDの解体については言及されておらず、寧ろ教育省の解体が言及されていた。そういう意味では、USAIDの解体は最初の標的ではなかったようだ。
トランプ大統領を取り巻く様々な人物の関与がUSAIDの解体への政策転換の要因となっていると考えられる。いずれの人物もトランプ大統領への忠誠を誓う保守系で知られる。特に重要な役割を果たした人物として、Stephen Miller(元・ホワイトハウス政策シニアアドバイザー・スピーチライター)、Peter Marocco(元・国務省対外援助部長、元USAID 副長官)、Marco Rubio(国務省長官)、Elon Musk(政府効率化省を主導)などがいる。直近では、対外援助削減幅を巡り、ルビオ国務長官と意見相違があり解任されたとされるマロッコ氏の後任には、政府効率省のJeremy Lewinが国務省の対外援助部長代行に就任した。対外援助政策に関わった経験はない人物だ(参照)。
USAIDを始めとする対外援助の大部分が打ち切りとなったと推測される理由として、「ある国に支援しているにもかかわらず、特定国と合同軍事演習を行っている、これはアメリカの利益に反する」、「無駄な支援に使われている」といった指摘があるようだが、事実だったとしても全体から見ればそれらは少数の事例にすぎない(参照)。しかし、こうした印象深い少数事例が、SNS上の拡散も手伝って、結果的にアメリカの対外援助全体への批判につながった。また前述の人物を中心に個人的に強い働き掛けもあったであろう。トランプ第二次政権は小さな政府を目指し、政府予算を大幅に減らすことを目標に掲げたため、予算規模も小さい対外援助の削減から試行的に始め、国民の反応を伺いながら成果の早期アピールを念頭にした「拙速な判断の結果」もあったのではないかと思われる。今後、USAIDは国務省傘下への一部機能移管が進められ、グローバルヘルス、食料安全保障、災害支援に特化した形で再編されるとの報道もあるが、状況は常に変わっている。また米援助機関の一画である米国国際開発金融公社(DFC)を中心に他援助機関との統合も計画されているとの報道もあるが、これも流動的だろう(参照①、参照②)。
現場の混乱—突然切られる生命線
こうしたUSAIDの組織再編が、どのような影響を及ぼしているか。本セミナーでは、健康・保健分野からの考察が示された。東南アジアのある国で、USAIDの資金により、当該国の大手の事業系NGOを担い手として2024年10月から始まった全国結核検査プロジェクトの突然の廃止は、現場の混乱を如実に物語っている。この事業は、その対象国の国家結核プログラムの3分の1を占める大規模なものだったが、これが突如終了し、200人のフルタイムスタッフと5,000人のコミュニティヘルスワーカーの雇用が失われたのである。この悲劇は次のように始まった。トランプ政権発足5日後の1月25日、USAIDから突然「アメリカの資金を銀行口座から動かすな」というメールが届いた。当該NGOの事務局長は担当者に問い合わせたが一切返答がなく、その後、2月7日に「サスペンション(停止)中だが、人命救助の緊急人道援助は例外とする可能性がある」と国務省から連絡があった。しかし、最終的に2月26日「レビューの結果、案件を廃止する」という一方的な通知で、この事業が幕を閉じた。現場職員の離散とともに、長年築いてきた信頼関係を一瞬で断ち切るような冷淡さと屈辱感を、当該NGOのリーダーたちは永遠に心に刻んだであろう。
深刻な影響を受けるのが2003年にブッシュ政権で始まったPEPFAR(大統領エイズ救済緊急計画)である。当初13カ国だった対象国は、同計画の責任者として国務省におかれた歴代の「グローバルエイズ調整官」による立て直しや統合により、現在55カ国に拡大し、2024年一年間で約2,060万人のHIV治療を支援している。USAIDの解体を受け、世界のエイズ対策資金の67%を占めるこのプログラムの停止と見直しは、治療中断によるHIV感染者の免疫低下と結核やその他の日和見感染症の発症増加、耐性ウイルスの発生、薬価高騰など、連鎖的な危機をもたらす懸念が示された。それに対し、国連合同エイズ計画(UNAIDS)は2029年までに最大630万人がエイズ関連死する可能性があると警告。一方、医学誌「ランセット」の論文による試算では死者77万〜293万人増、新規感染443万〜1075万人増という予測も出ている(参考)。特に1月20日のトランプ大統領令では多様性・公平性・包摂性(DEI)政策の禁止や「極端なジェンダーイデオロギー」禁止が明記され、LGBTQコミュニティなど社会的に脆弱な立場にある人々への支援も危機に瀕している。
そのような大きな影響を及ぼすUSAIDの解体を見ると、米国の「好意」に途上国が甘えてきた結果だ、などと批判する声もあるだろう。しかし、話はそれほど単純ではない。「援助依存」に見える現象は、アメリカのその時々の政治的主張や都合により、途上国を「依存」させるか「自立」させるかという動きが繰り返される歴史の結果でもある。PEPFARの最大の弱点は一国主義的アプローチだと指摘されているように、USAIDの解体は、多国間機関を通じた援助の重要性を再認識し、一国主義を克服するきっかけになることが望まれる。「援助効果に関する釜山宣言」や「アディスアベバ行動アジェンダ」など、21世紀に入って以降営々と積み重ねられてきた、援助の在り方に関する多国間での合意を軽視せず、様々な蓄積を活かすための施策が必要であろう。
「中国が空白を埋める」という言説の再考
医療・保健分野だけにとどまらないUSAIDの影響は、援助業界の在り方にも地殻変動をもたらしている。本報告の執筆時点では、資金の凍結等により、世界中で17万人以上の雇用が失われ、そのうち5万人以上は米国内である。この厳しい状況下で、多くの援助分野の専門家がコンサルティングという新たな道を模索しているが、そのコンサルティング市場も急速に飽和状態へと向かいつつある。同時に、これまで組織内で培われてきた専門知やノウハウの散逸という深刻な課題も浮かび上がってきている(参照①、参照②)。
USAIDの撤退に伴い「中国がその空白を埋めるのではないか」という推測が広がっているが、データを見ていきたい。2002年から2021年の間の国際支援(政府開発援助(Official Development Assistance、ODA、参照)+その他公的資金)の実績(コミットメント・ベース)を比較すると、中国の支援額はアメリカを超えているが、その多くは政策金融機関からの商業条件によるローンであった。ODA要件を満たすものはわずかである。
アメリカの援助はほとんどが無償(グラントで)、教育・保健・人道・民主化支援等に使われているが、これらはODA要件を満たさない、商業金利による融資に適さないものである。それに対して、中国の対外支援は主に中国開発銀行や輸出入銀行を通じたローンで、中国企業が関与する大規模インフラや資源開発に向けられている。中国がアメリカの肩代わりをする事案もありえるが、マクロ的に見ると、現状の予算構造では中国が米国の援助を代替することは難しいと考えられる(参照)。
途上国の現場からの報告でも、実際に現場において中国政府がUSAIDの解体を受けて資金を大量かつ積極的に投入しているという確認はできていないようだ。中国の対応はむしろ慎重であり、先進国の責務と異なり、途上国として「自ら約束したことをきちんとやる」という姿勢を示している。にもかかわらず、「中国がこの空白を埋めたらまずい」という論理が、アメリカが自らの援助を復活させる正当性を主張するために利用されるという状況をより注意深く見る必要がある。
援助削減の世界的潮流—財政と効率の観点から
USAIDの解体・再編をきっかけに注目されるようになった米国援助の量的縮小・質的変化だが、それは孤立した現象ではなく、伝統的な欧州ドナー国を中心に始まった動きの一環として位置付けられよう。ドイツ、フランス、イギリスなども援助削減の動きが見られ、特にイギリスは、財政再建・国防予算拡充等を掲げ、GNI比0.7%目標を0.5%目標に切り下げた後、数値目標を廃止したほか、ドイツも連立政権の下で予算編成を見直している(参照)。歴史的に見ても、米国の援助は過去に二度大きく削減された。ベトナム戦争を挟む1960年代末から70年代にかけて、また、日米貿易戦争や冷戦崩壊を挟む1980年代末から90年代にかけての時期である。特に冷戦後の時期においては、欧州勢を含め、「援助疲れ」と言われる現象が生じた。その後、2001年の同時多発テロを契機に援助は急増し、近年ではコロナとウクライナ戦争の影響でさらに増加していた。足元における援助大幅見直しの動きを理解するには、こうした歴史的変動を踏まえた上で、底流にある国際政治・経済の変革の理解が必要だろう。各国を取り巻く事情は多様であるが、コロナ危機・ウクライナ戦争以来の財政難、先進国内に流入する難民への支援拡大による援助予算の変質、中国をはじめとする「新興国」のキャッチアップが国際社会の在り方そのものに変容を迫りつつあることなどを挙げることをできよう。
では、財政的困難を解消する観点から、援助削減は有効であろうか。財政と援助の関係についても冷静な分析が必要だ。「援助削減で財政問題が解決する」という声も聞かれるが、援助予算は国の歳出の1〜2%程度にすぎず、日本の場合、政府債務(GDP比250%)に対してODAはGDP比で最大0.5%程度にとどまる(参照①、参照②)。財政再建のためには、拡大傾向にある社会保障費などの大きな支出項目の見直しが必要であり、GDP比1%未満の水準にある援助予算の削減だけで、防衛費の大幅増(GDP比1~2→3~5%)実現は困難である(参照)。多くの先進国で高齢化の更なる進展に合わせ、医療・年金・介護関連予算が増加せざるを得ないる現実を踏まえると、援助予算見直しだけでは財政再建に遠く及ばず、可能な範囲で国民生活への痛みを抑えつつ、巨大化する社会保障費の見直しを図ることが急務である。
一方、こうした予算削除の背後にある深層のロジックは、効率性への追求である。さらに言えば、それは「無駄」に対する理解に帰結するものであろう。米政府効率化省との安易な比較はできないが、政府開発援助の予算削減に関して、日本国内でも常に議論がある。なかでも、2009年の民主党政権下での事業仕分けは、「無駄」をめぐる議論の複雑さを示す事例として重要な教訓を残している。
当時、「税金の無駄遣いの根絶」を掲げ、5,000以上ある予算項目の中から447事業を対象に公開の場で行政事業の必要性を検討した。外務省案件では「国際機関の任意拠出金」「無償の箱物1/3」などがテーマとなり、2010年度予算で9,692億円の削減、1兆269億円の歳入確保などの成果があった(参照)。事業仕分けの注目すべき点は、「立証責任が必要性を主張する側に求められた」という逆転の発想だった。また「予算を増やす」だけでなく「予算を減らす」ことも議会の仕事という認識の変化をもたらした。一方で、透明性向上のために公開で実施したことが「劇場化」を招き、本来の目的が歪められるリスクも生じている。
事業仕分けが手続きを踏んだ議論であったが、それによって生まれた「意図せざる結果」がある。すなわち、効果・効率性を求めた結果、「無駄と言われないよう、効果測定がしやすいものを事業にしていく動き」が生まれ、国益という名の下に政府開発援助の政策目標を定める理路が浮き彫りされた点である。例えば、援助の目的が「貧しい人たちを支援する」という本来の目標から、「日本企業のためになる」「国際社会で日本の立場を支持してくれる」といった表現が案件概要書に明記されるようになった。日本の事業仕分けの経験はUSAID解体という「劇薬」とは手法は異なるものの、ODAのあり方が国内政治の力学のなかで形作られている側面、そして行政改革の意図せざる結果を考える上で示唆に富む。


3、日本への含意:試練の時代を生き抜く
新しい「言葉」を求めて
USAIDの解体と再編に揺らいでいる国際開発援助の現場風景を、日本はどう見ているのか。USAIDの解体による直接な影響は、現時点ではJICAの事業に対して確認されていない。JICAとUSAIDの援助の仕組みの違いもあるだろう(例えば、JICAは直接政府の人材育成や能力開発、経済インフラ整備支援等を行うが、USAIDはNGOや民間セクターを通じた支援が多い)。ただ、JICAとUSAIDが同じ分野で事業を実施している場合、今後の状況次第では間接的な影響が生じる可能性はある。USAIDがNGOや現地政府職員の人件費を補填していた場合で事業停止となれば、同分野の人材が不在となりかねない。これからは開発パートナーとの連携を図りながら、現場のニーズをしっかり把握し、できることは何かを常に考える必要がある。
日本の政府開発援助(ODA)関係者の間でも、USAIDの解体を対岸の火事では全くないと受け止めている。現代社会の中で生きていくことによる剥奪感が高まる中、援助批判は国が持つ心情的・資金的余裕のなさを分かりやすく表してくれる場である。USAIDへの批判は、日本への政府開発援助批判につながる可能性はすでにうかがえる。「日本のJICAに相当する」USAIDの解体が報じられるに従いSNS上では「次はJICA」といった投稿が見られるようになり、そのような状況に援助関係者は直面している。本セミナーの総合討論では、ODAの重要性に一定の理解を示しつつも、それだけでは有権者から支持を得ることが難しいとする議員を取り巻く現実に目を向けるべきとの声が上がっている。また、内閣府の世論調査では、30代から40代の特に男性に「ODAを減らせ」という意見が多い傾向がある(参照)。前述した日本の事業仕分けの例で示されたように、国民・市民との対話は簡単ではない。ODAに対する審査と議論は、透明性を保つために公開した途端「劇場化」する可能性が高い。実際、日本の開発協力大綱改定をはじめとし、公開的な政策議論の意見交換会では、批判的な意見の者の参加は安定して一定数見られるものの、より広い聴衆、特に若年層に関心を持ってもらうことが大きな課題と感じているとの意見も聞かれた。
今日、ODAは「無駄」や「海外ばらまき」と批判・指摘されることもあるが、それは、どういう事実をもとに、誰の立場からの解釈に基づく主張であろうか(参照)。「無駄」はある意味で「結果」に対する表現であり、その「結果」もまた時間をおいて検証しないとわからないものである。そして、どこまで時間をとり、どこまで検証するかによって、得られる「結果」も変化するのであろう。例えば、国内でも、大都市住民を中心に、地方交付税は「無駄」が多いと評されることがあるものの、国民全体のソリダリティや日本のナショナルミニマムを支える重要な仕組みである。予算編成において、「無駄」は存在しない。「無駄」ではなく、「何が優先すべき政策目的か」という議論をすべきである。
もっとも、各国の事例を見ても、ODAに対する監視の厳格さと防衛予算のチェックの緩さの対比が著しい(参照)。ODAだけが問題あるというより、不透明な領域はそもそも評価の対象すらなれない、いわゆる批判の構造的非対称性の問題がある。ODAの是正は、政治のビジョンを実現するための公共性の構築——国境を超えた課題・需要の連動、その優先順位と資源の再分配——を担うものだとすれば、その理路は、「わたしの税金を無駄に使うな」という私的所有の意識に根差した個人の不満を解消するものになり難いと理解できよう。
本セミナーでは、こうした対話の難しさに対して、援助の意義を伝える新たな「ナラティブ(物語)」の構築が課題として取り上げられている。ディスカッションにおいて、USAIDの解体・欧州主要ドナーによる援助の削減の中で、「ブレないことの価値」(愚直に日本らしい現場での協力を続けることの価値)という表現で日本のODAの強みを再評価できるのではないかとの意見が挙げられた。シンガポールのシンクタンク、ISEAS ユソフ・イシャク研究所の調査によれば、ASEAN加盟国他による日本への信頼は高水準を維持している(参照)。開発協力が必要だと思う理由に関して、内閣府調査でも「国際社会での日本への信頼を高める必要があるから」という項目への支持は高い(参照)。国際環境が目まぐるしく変化するなか、「愚直だけども続けていること」への価値が高まると考えられる。
一方、日本の国会議員たちは、有権者に対してODAの役割を短く伝える「言葉」を求めているという。その一つの方法として、対外援助が日本への直接的影響を示すアプローチが指摘された。例えば結核対策の中断が多剤耐性結核を生み出し、それが海外から移住する人々などを通じて日本にも影響を及ぼす可能性がある。また、これまで、米国はインドなどのジェネリック薬企業に対して、PEPFARで必要なエイズ治療薬を定期的かつ大量に調達していたので、ジェネリックのエイズ治療薬の値段は安価に保たれていた。しかし、今後アメリカが薬を買わなくなると、これらの治療薬の値段は、今よりもずっと高額になるだろう。日本人が個人輸入しているHIV予防薬(PrEP)も値上がりするなど、一般の日本人の生活にも関わる問題として説明できる。このように、結果的に自分の利益につながっているという、言ってみれば「合理的利他主義」の言説は有力かもしれない。
他方、そればかりで応答すると、国際開発援助に理想や使命感をもつ若者をこの世界から遠ざける可能性が懸念されている。本来重層的な国際開発援助の意味を単一なナラティブに回収されないよう、常に豊かな解釈的資源を用意することは、その複雑さを理解する上で重要に違いない。戦後日本の復興・経済成長は、国際社会からの支援(LARA物資、ガリオア・エロア資金、世界銀行等)に助けられたことを忘れてはならないとの指摘もあったように、国際開発援助の意味を近視眼的に捉えるのではなく、自らの歴史の流れに思いを馳せ、芽吹きゆく成果を見守る余裕を持ちたいものである。
エコシステムの救済と再生
最後、本セミナーで提示された「エコシステム」の考え方は興味深い。USAIDの解体は長期にわたって蓄積してきた国際開発援助のエコシステムを破壊するものとしたら、破壊されないエコシステムを長期的に構築できるかを研究と実践、あるいは、特定の依存関係に限定されているエコシステムを今から変革させる準備が求められているのであろう。
第二次トランプ政権の登場によって、一気に顕在化した国際開発援助のエコシステム自体の問題にどう対応するか。アメリカの援助が途切れた時にヘルスシステムが崩壊するような脆弱な国々の存在が浮き彫りになったとき、その人々を助ける緊急的な課題がある。と同時に、自分たちの税収をどう増やし、限られた資源で最低限のヘルスサービスをどう提供するかを考え直す機会でもある。本セミナーで指摘されたように、PEPFARの構造的弱点はその「ユニラテラル(一方的)」な性格——対象55カ国が米国によって一方的に決定され、実施も米国NGOやコンサルタントが中心となり、政策も共和党と民主党で大きく分断されている——にある。それに対して、グローバルファンドのような多国間機関は複数国の拠出による資金レジリエンスがあり、政策も多国間・多セクターで形成されるため、一国の政権変化の影響が緩和される利点がある。
ところが、ワシントンでの恒例の「春の会合」の開始を目前に控えた4月23日、米財務長官であるScott Bessent氏は国際金融協会(Institute of International Finance)で講演し、IMF・世銀に対する米国政府のコミットメント継続を表明する一方、ブレトンウッズ両機関に対し、設立以来のミッション(マクロ経済運営の適切な監視(IMF)、経済成長・貧困削減の促進(世界銀行))に一層注力すると共に、気候変動対策など本来ミッションに沿ったものとは言い難い取り組み(ミッション・クリープ)の見直しを求めた(参照)。米国が加盟する国際機関に対する米国政府のレビューは8月まで続くものの、今後の米援助政策の動向を占う上で、注意すべき動きと言えよう。
USAIDの例に示されるように、国益、安全保障、イデオロギーなどといった国家の視点に立つ「援助の必要性」のレトリックは、結果的に行政組織の肥大化と援助の変質につながる側面がある。そういう意味では、中央省庁から、さらに言えば「東京中心主義的」な議論から脱却し、地方も含めた包摂的な関係性が重要となる。敢えて国際会議を東京以外の地方都市で開催し、その地方と国際社会の関係に光を当てつつ、地方からの情報発信を行うことをはじめとし、国際開発援助のエコシステムを新しい生き方から再建するきっかけにもなりうる。
さらには、行政の論理に回収しきれない、「助ける/助けられる/助けになった」という人の日々の生に関わる営みを、一人ひとりの実感・実践レベルで考えることである。第二次トランプ政権の「無毒化」ではない形で、USAIDがもたらす危機を、国際開発援助を私たち一人ひとりの実践、言ってみれば国際開発援助を民衆化する契機に活かしても良かろう。その際、政府開発援助で蓄積された多様な経験もまた、生かされるコモンズとして輝くかもしれない。

本セミナーの参加者は、国際機関、日本政府、NGO、企業、大学などといった多様な背景を持つ。議論が熱く、セミナーは予定時間より1時間半も大幅に超えた。こうやって共有された時間は、アメリカの動向を理解するだけではなく、日本における国際援助に関連する行政・学問・市民の関係性を紡ぐ、紡ぎ直すきっかけになることを切に願っている。強靭な国際開発援助のエコシステムは、単一の仕組みを超えて、国内と国外、過去と現在、思想と実践の無限に絡まり合う相互依存の積み重ねによって潤うものと考えられる。
最後に、お忙しい中、本セミナーでのご登壇をお引き受けくださいました馬杉学治様、稲場雅紀様、米山泰揚様、松本悟様、また、セミナーの設営にお力添えいただきました木口由香様、玉井(黒川)美恵子様、松原直輝様に、心よりお礼申し上げたい。
企画者・報告者:汪牧耘(EAA特任助教)
写真:玉井(黒川)美恵子
※ その他の参考資料:
・DEVEXのUSAID関係サイト:https://www.devex.com/focus/us-aid
・CGDのUS Development Policy関連サイト:https://www.cgdev.org/topics/us-development-policy
・USAID同窓会:https://usaidalumni.org
・アフリカ日本協議会による医療・保健分野関連の動向報告:https://ajf.gr.jp/globalhealth/
 会場からの眺め
会場からの眺め








