人新世と呼ばれる今日の環境危機に対処するため、2023年に北米・ヨーロッパ・日本の研究者が連携して発足した研究グループ「環境美学ワーキンググループ(A Working Group on Environmental Aesthetics = WGEA)」は、国際共同研究「ヨーロッパとアジアの環境美学:批判的比較(European and Asian Environmental Aesthetics: A Critical Comparison)」を開始した。WGEAの第3回国際研究会にあたる本会議では、これまでの欧米圏を中心とした研究成果を踏まえつつ、アジア独自の美学的役割や環境美学の可能性に焦点を当て、環境危機の理解における美学の意義を根本的に再考することを目的とした。
初日(4月23日)は、東京大学人文社会系研究科にて開催され、WGEAの中心メンバーである Sean McGrath 氏(MUN)、Uwe Voigt 氏(Uni Augsburg)による挨拶を受けて開会した。近代西洋の自然観や風景論と東洋美学との接続点となりうる哲学者 F・W・J・シェリング(1775–1854)に関する若手研究者によるフォーラムが行われ、報告者は中島新氏(Bonn University)、中村徳仁氏(三重大学)であった。
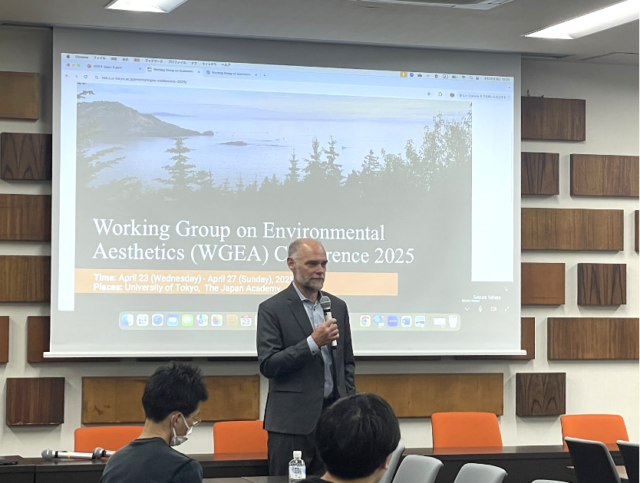


その後、Russell J. Duvernoy 氏(King’s Univ. College)は「美学的経験」をキーワードに、東西の美学を概観しつつ、「betweeness」といった本会議を通底する重要な概念を提示した。また、Lorenzo Marinucci 氏(東北大学)による基調講演では、従来下位感覚とされた「嗅覚」に注目した美学的アプローチが提起された。


24日(於日本学士院)には、WGEAの中心メンバーである 小田部胤久氏(放送大学)が、日本的視点から東洋美学の枢要な概念である「気」について論じ、また Uwe Voigt 氏(Uni Augsburg)は「感覚麻痺」の観点から環境破壊をめぐる議論を行った。禅の研究者 Jason Wirth 氏(Seattle Univ.)は、人新世における禅の意義について、丁乙(北海道大学)はゲーテと宗白華に注目し、東西の自然観を比較した。さらに、日本における環境美学の先駆的若手研究者である 青田麻未氏(上智大学)は「生花」に焦点を当て、その理論的展開と美学的示唆について基調講演を行った。



25日(於日本学士院)には、Leila Michelle Vaziri 氏(Uni Konstanz)が20世紀の詩歌を題材に、「care」の問題を中心とした美学・生態・倫理の交渉的関係について発表した。
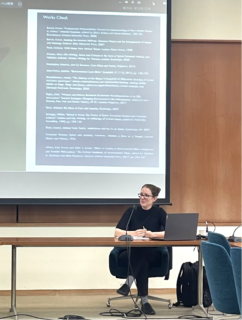
続く二つの基調講演では、檜垣立哉氏(専修大学)が廣松渉を中心に据えて生態学的な歴史観を論じ、納富信留氏(東京大学)は、日本における「世界哲学史」プロジェクトの紹介とともに、プラトン思想に見られる「真・善・美」の図式における美の位置づけについて、幅広く考察を行った。また、ドイツからは Philipp Höfele 氏(University of Freiburg)がオンラインで参加し、「自然の模倣」というテーマのもと、従来の美学的枠組みにおける倫理的側面について検討を加えた。


26〜27日には東京大学東洋文化研究所で会議が開催された。26日の午前中は若手研究者によるフォーラムIIが開催された。まずAnh-Thu Nguyen氏(立命館大学)が、近年目覚ましい技術発展をとげているビデオゲームのヴァーチャルツアーを取り上げ、そこでプレイヤーがヴァーチャル・ツーリストとしてどのように世界を体験するかを分析した。続くHu Sheng氏(名古屋大学)は、中国の戦場について様々なメディアによって記録されたものの中でも、とくに写真を取り上げてそこに戦場がどのような風景として表現されているかを、具体的な例をあげながら検証した。午後のセッションでは、Joachim Rathmann氏が(Uni Würzburg)デジタル時代において自然や超越したものへの畏怖が失われているのではないかという疑問から、近代から現代に至るまでの自然への畏怖についての概念の変遷を明晰に報告した。次に、八幡さくら氏(一橋大学)は新潟県越後妻有地方で開催されている大地の芸術祭の例から、アートを通して自然に人がどのように再接続しうるのかを、作品事例を分析しながら検討した。午後の休憩を挟んで、東洋文化研究所所長の中島隆博氏(東京大学)から挨拶が行われ、本会議開催の成功を祝った。

最後のセッションは、Laura Fumagalli氏(Uni Augsburg)は、否定美学(negative aesthetics)の様々な概念を検討しながら、それが自然環境の問題に果たす役割を検討した。最後にアーティストでもあるStefanie Voigt氏(HEX Hochschule)が日本文化の絵馬に注目して自身が制作した絵画作品を紹介しながら、日本文化の動物への関心について語った。
27日は、まずBarry Stephenson氏(MUN)がゲーリー・シュナイダーのエコロジーについての詩を紹介しながら、自然と宗教の関係について報告が行われた。次に、Tomoki Sakata氏は(Uni Bamberg)、より良い環境のためにはどのように自然をコントロールすることができるかについて、庭の垣根などの具体的な事例を挙げつつ、様々な哲学者の議論を引きながら現象学的に分析した。Georg Gasser氏(Augsburg)は、自然の中に見出される様々な奇跡についてこれまでの美学理論においてどのように説明されてきたかを追いながら、自然の美的経験の核にその奇跡の発見があると報告した。会議の最後に、Sean McGrath氏(MUN)が谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』を引用しながら、影や暗さを賞賛することが、ドイツロマン主義とも共鳴していることを指摘し、東洋と西洋の美的議論の共通項について更なる議論の展開可能性を提示した。

最終日の28日午前中には、WGEA共同研究の今後の計画や方向性についてメンバーが討議した。議長のMcGrath氏によって、メンバーからの様々な意見が集約され、今後もオンラインと対面を合わせた会議の継続を行うことで、さらにこれまでの環境美学研究を推進していくことが確認された。午後には高尾山へのエクスカーションを行うことで、自然と文化の融合した日本の風景を実地調査することができた。
今回の東京会議開催において、日本の様々な研究者との研究交流を経て、環境美学研究の更なる展開を見定めることができた。全日程において質疑応答はもちろん、会議の合間のコーヒー・ブレイクや休憩時間にも参加者同士で活発な議論が行われた。本会議を通して、地球環境や環境問題といったグローバルな視点だけでなく、身体や文化、生活に根差した美学のあり方を見据えて、今後も研究活動を進めていくことが重要であると参加者全員が確認した。最後に、互いの研究を相互発展させていくために、今後も様々な研究者と協力しながら、環境美学に関する共同研究活動を継続させていくことを共同研究メンバー同士で誓い、会議は盛況のうちに閉幕した。
報告者:丁乙(北海道大学)、八幡さくら(一橋大学)








