中島隆博先生に連れられてハンブルクのビアホールに入り、ひとの顔を優に凌駕する巨大なジョッキを手にしたとき、私は奇妙にも森鷗外のことを思いだしていた。日本近代で最高の知性(少なくともそのひとり)である鷗外が20代の後半をドイツですごしたのは有名なはなしだが、そこでかれがビールにかんする研究をしたことはあまり知られていないように思う。たとえば「Ueber die diuretische Wirkung des Biers」(ビールの利尿作用について)[★1]という論文のなかで、鷗外は水や(炭酸の抜けた)ビール、ワインなどを比較しながら、ビールを飲むとトイレが近くなる原因はアルコールにあると指摘している。「独逸日記」によると、この論文を発表した鷗外は学会で拍手喝采を浴びたらしい[★2]。1887年のことだ。
私の専門は中国哲学で、いわゆる中華圏への渡航や長期滞在の経験はあるのだが、じつはそれ以外の国家を訪れたことは一度もなかった。もちろんヨーロッパへの渡航も今回が初である。なので、私にとってドイツにかんする認識や印象はきわめて限られたものだった。じっさいその大半は、鷗外とビールと観念論、あとはせいぜいポルシェとバウハウスとファスビンダーによって構成されていたといえる(あと移民問題とケバブ人気もあった)。
そんな私が今回派遣してもらえることになったのは、おそらくユク・ホイさんの翻訳を多少やっているからであったと思う。そこを念頭において、Winter Institute ではホイさんの『中国における技術への問い』(邦訳はゲンロン、2022年)を起点に、若干の論点を提示することにした[★3]。
具体的にいえば、それは地域性の規模をめぐる問いである。近代的なテクノロジーによる世界の均質化に抵抗するべく、ホイさんは多様な宇宙技芸(cosmotechnics)にもとづく技術多様性を提唱している。宇宙技芸とは、技術を認識するための新しい枠組みであり、いわば技術をそれ単体で理解するのではなく、むしろそれが生まれた地域の宇宙論(自然観や時間の観念)や、その使用者である人間をめぐる思考との関連性のなかで包括的に捉えようとするものだ。
宇宙技芸という枠組みを提示するひとつのメリットは、議論を立てやすくする点にある。つまりこの概念を用いることで、技術多様性というきわめて困難な課題に取り組むにあたり、宇宙論の多様性から議論を始めることができるようになる。それは、具体的になにを開発すればよいかというエンジニアリングの問題に議論が終始するのを防ぎ、(ホイさんの考えでは)より根本的な哲学的アプローチを可能にする——もちろん、開発の問題が重要でないと言っているわけではまったくない。
もうひとつここで特筆すべきなのは、宇宙技芸のプロジェクトが地域性を非常に重視することだ。それはホイさんが、マルティン・ハイデガーに従い、近代的なテクノロジーを西洋哲学の必然的な帰結とみなしていることと密接に関連している。西洋的な宇宙技芸である「科学技術」としての近代テクノロジーに対して私たちがなすべきなのは、それを加速させることでもなく、ただ拒むことでもない。むしろ地域性に彩られたいにしえの宇宙技芸を再発見し、現代の状況において再発明することなのだ。
ただ問題なのは、そもそもここでいう地域性が、一体どれほどの規模で想定されているかである。かりに宇宙技芸をつうじて地域性を考えるなら、ある程度体系的な宇宙論や技術論、ひいては(ホイさんに従えば)道徳の思想が必要になる。じっさいホイさんはギリシアと中国をじつにうまく比較しているわけだが、おなじことが周辺の国や地域にも可能だろうか? たとえば日本を含むアジアの国々にとって、自分たちの宇宙技芸を考えるにあたり、中国というかつての文明の中心に還元されないようにするのは至難のわざだ。とすると、かれの議論が提示する条件は、地域性を非常にマクロなものにしてしまうのではないか?
こうした問題意識のうえで、今回の発表では、appropriation という概念——異なる文化のあいだに生じる、改変をともなう模倣——を(しばしば言われるように「文化の盗用」としてではなく)地域性が発揮する力として解釈すること、そしてそのたえまない応酬(re-appropriation/co-appropriation)のなかに、宇宙技芸や地域性そのものを細分化させる可能性を捉えることを提案した。その際、シンガポールの芸術家であるホー・ツーニェンの作品や、私自身が行なっている中華料理の哲学をめぐるプロジェクトを導入した。
さいわい、私の発表には好意的な見解や重要な質問を寄せていただいた。ホイさんの知名度の高さに助けられた側面も少なからずあったように思う。げんに、今回知り合った先生方や大学院生のなかにはかれの読者が多くおり、それが交流の糸口になったこともしばしばだった。そのおかげもあって帰国後もつながっている友人がふたりほどできたし、目下そこから中国での新しい仕事の可能性が生じるなどしている。そういう意味でも、いろいろと実りの多い経験となった。
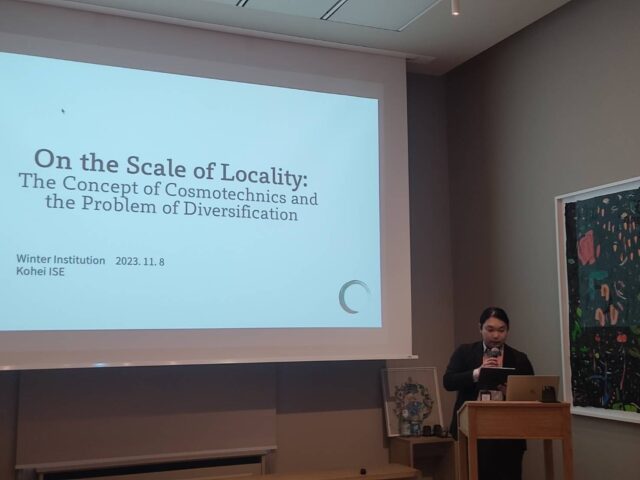
とはいえ、こうした成果を踏まえたうえであえて言うと、私にとっては、とにかくハンブルクへ渡航して数日間滞在したことそのものから、つまりは研究所の外での時間から得た学びこそがきわめて重要だったように思う。
『芸術と宇宙技芸』という本のなかでホイさんは、芸術の役割とは、まったく異なる認識や感性へと私たちを導くような「エピステーメーの革命」であると述べている[★4]。この定義にはじつにラディカルな発明や変革への期待が込められている。だがそれと同時に、多少なりとも些細なかたちではあるが、私自身は偶然性に開かれた観光もまた、こうした革命の端緒となるのではないかと考えている。
たとえば Winter Institute の初日の夜、ハンブルクの名所をまわるナイトクルーズが企画された。会場へ行くタクシーは事前に予約されていたのだが、午後に電車がなぞの機能停止を遂げたせいでタクシーの需要が急増し、一台来れなくなってしまった。私は、國分功一郎先生とヴィクトリヤさん、そしてボン大学から来たふたりの研究者とともに New Institute のまえに取り残されてしまい、急きょアルスター湖のそばにある「Tipsy Baker」というバーへゆくことになった。これは、インフラの維持すら困難になっているというドイツの問題を端的に思い知らされた出来事だったが、その結果私は思わぬ学びを得ることになる。
Tipsy Baker で当然のようにビールをパイントグラスで注文した私は、ふとビールのそばに小さなショットグラスが添えられていることに気づいた。ボン大学のラリッサさん——彼女は先述のふたりの友人のひとりだ——によると、それは「シュナップス」と呼ばれる蒸留酒で、ビールの「チェイサー」として嗜むものだという。一般的に、日本でいう「チェイサー」は酒のあいだに挟む弱い酒や非アルコール飲料をあらわすが、これはアメリカ英語の用法を踏襲したものであり、イギリス英語ではまったく逆の意味をもつ。つまり弱い酒のあとに飲む強い酒のことをチェイサーと呼ぶのである。シュナップスにはホワイトラムに似たおいしさがあり、それ自体十分に印象的だった。だがそれ以上に、この蒸留酒は、「チェイサー」という語が普段とはまったく逆の意味で用いられるという小さな認知的革命によって私の心に深く刻まれたのである。
ところで、Winter Institute の最終日である11月9日は私の誕生日だった(そのため、ヴィクトリヤさんからはマジパンをいただき、戀さんには帰りの空港でシュナップスを買ってもらった)。なので、当然その日は私にとって重要な意味をもっているわけだが、じつはドイツにとっても特別な意味がある。なぜならベルリンの壁が崩壊したのは1989年の11月9日だからだ。かつて誕生日の朝に狂喜乱舞するドイツ人の映像をニュースで見かけたとき、幼少期の私はちょっとした感動を覚え、ドイツへの素朴な好感を抱いたのだった。
けれども、プログラムの一環で訪れたハンブルク美術館のなかでラリッサさんにこのはなしをしたとき、彼女は少し困惑したような複雑な笑みを浮かべた。というのも、たしかにベルリンの壁崩壊は記念すべき瞬間だが、ちょうどその半世紀ほどまえにあたる1938年の11月9日に、のちのホロコーストにつながった全国的なユダヤ人襲撃事件が起きたからだという。「クリスタル・ナハト」(あるいは「水晶の夜」)と呼ばれるその出来事については、むろん私も知っていた。だが11月9日に結びつけられたとき、それは幾重にも入り組んだドイツの歴史的経緯を喚起する象徴となった。もちろん、そこから翻って11月9日という日への認識がすっかり変わってしまったこともまた、言うまでもない。
何らかの物事にかんして、これまでとはまったくちがう見かたや感じかたを不可逆的にもたらすこと。作品をつうじてそれを実現することが芸術の役割であるなら、思考によってその体験を引き起こすことが哲学に課せられたひとつの使命にほかならない。私はそう信じている。今回のハンブルク滞在は、小さな認知的革命の契機に満ちた知の観光であり、それによってこの信念を、また私自身は思想家としてなにをなすべきかを再確認させてくれるものだった。


★1 森林太郎『鷗外全集 第二十八巻』、岩波書店、1974年、505−553頁。
★2 森林太郎『鷗外全集 第三十五巻』、岩波書店、1975年、154頁。
★3 今回の発表は、私の論文である「技術多様性の論理と中華料理の哲学」(『群像』2023年4月号)および「ユク・ホイと地域性の問題——ホー・ツーニェンの『虎』から考える」(『ゲンロン13』)の論点の一部をまとめたものなので、議論の詳細についてはそちらを参照してほしい。
★4 Yuk Hui, Art and Cosmotechnics (New York: e-flux, 2021). 同書はすでに私が全訳を終えており、現在編集を行なっている。邦訳は来年の春から初夏に刊行予定である。
報告者:伊勢康平(人文社会系研究科)








