中江兆民『三酔人経綸問答』、幸徳秋水『廿世紀之怪物 帝国主義』に続き、今学期の東アジア教養学「世界歴史と東アジアIII」の授業で、近現代日本の「古典」として3冊目に選んだのは鶴見俊輔『戦時期日本の精神史1931〜1945年』である。戦後に書かれた戦中の本としてひとつの橋渡しになるのに加え、ある人物をあいだに挟めば、系譜的にも繋がる気がしたのである。
その人物とは石川三四郎である。諸宗教の影響を受けつつ職業的宗教家からは距離を取った石川は、自分の葬儀には宗教家を呼ばないようにと遺言した。この点が中江兆民に似ていなくもない。幸徳秋水とは『平民新聞』でのつながりがあった。幸徳秋水は大逆事件で死刑になり、大杉栄は関東大震災直後に殺されたが、同じくアナキズムの系譜に連なる石川は生き延びる抵抗を組織した。大逆事件のあと日本を脱出して欧州に亡命生活を送り、後年アナキストの地理学者エリゼ・ルクリュの著作を日本語に訳した。そのような石川を鶴見は高く評価している。『戦時期日本の精神史1931〜1945年』でも、「明治後期の最初の社会主義者の生き残りであった無政府主義思想家」の石川が、戦時の著作でも国策に同調しなかったことが触れられている。
後藤新平の孫、鶴見祐輔の長男として生を享けた鶴見俊輔は、若い時期に「不良化」した。文部省の教育方針に自分を合わせることができず、日本を脱出してハーヴァード大学に学んだ。日米開戦後、アナキストの容疑で逮捕されて監獄で卒論を執筆、戦時交換船で帰国すると海軍の軍属として南洋に送られた。仕事には慰安所の設置もあり、「日本人であることをぬぎすてたかった」というが、自分の考えを表明しないことで生き延びた。戦後、『思想の科学』を舞台にアメリカ・プラグマティズムを紹介する一方で、戦争体験から戦後社会をとらえる方法を掴み出そうとし、「転向」現象や大衆文化の研究に従事した。ベトナム戦争に際しては、反戦運動に加わり、国家を超える市民のつながりに注目した。そのような鶴見が、1979年から1980年にかけてカナダ・ケベック州のモントリオールに滞在し、マギル大学での英語による講義をもとにした本が、『戦時期日本の精神史1931〜1945年』である。
「十五年戦争」という呼称の提唱など、本書で展開される日本の戦前・戦中をとらえる認識枠組みに今日の私たちが負っている部分は小さくない。転向の諸相を描き出す鶴見の視線は、もちろん批判的だが共感的なものも含んでおり、あるイデオロギー的な立場から断罪するものではない。今では物珍しくもないかもしれないが、あまり有名ではない人びと、普通に暮らす人びとに注目しての叙述も印象的だ。朝鮮や沖縄への眼差しや市民運動への着目は日本の鎖国性を揺さぶる。
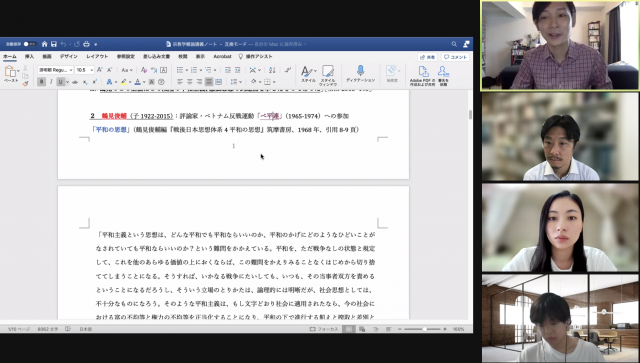
本書で取り上げられるトピックが多様であるぶん、参加者の議論の展開も興味深かった。1人の参加者は、戦前の日本で左翼を弱体化するのに用いられた転向の手法は、植民地時代の朝鮮半島においても用いられたことを紹介してくれた。その手法は、朝鮮戦争を経たあとの韓国でも受け継がれ、北朝鮮を牽制する目的で使われたという。「かくし念仏」の研究を志している参加者は、本書の「非転向の形」の章で岩手県の和賀(岩崎)のかくし念仏が紹介されていることから、この「地下信仰」についての内容を掘り下げてくれた。そして、地域的に限定された現象を、広い視野に置き直すためのヒントを得たようだった。もう1人、戦後日本の平和運動に関心のある参加者は、自衛隊の海外出動はしないことを決議した1954年の国会で父・鶴見祐輔が戦後の日本人は「平和愛好国民」であると演説したことを紹介した。そして、ベ平連に参加した息子・鶴見俊輔の「動的な平和観」と比較した。
「小国」の観点から普遍を問いなおす企てにおいても、鶴見俊輔は鍵になりうる人物である。彼はモントリオール滞在中に北米先住民モホークの居留地を訪れようとした。道中、米国領を通らなければならなかったが、ヴィザを持っていないので目的地にたどり着けない。戦前の逮捕歴のせいもあるのか、戦後に米国政府からヴィザ発給を拒まれたことが鶴見にはあった(結局彼がこの国の土を再び踏むことはなかった)。そこで族長たちが国境を越えて会いに来てくれた。彼らは「英国から渡ってきた白人にくにを奪われたが、自分たちのくにがそれで終わったと思ってはいない」。鶴見は「大国」批判の「小国」贔屓という類型の戦後知識人の1人である。
鶴見はアメリカに2つの姿を見ていたと言えよう。帝国主義的な戦争国家のアメリカと、抑圧の経験から自分の権利を見出していく活力をもったアメリカの市民社会の人びとと。そして戦後の日本にも、前者に同調する姿と、後者に連なる一群の人びとの姿とを見ていたのだろう。日本の外に出て日本を相対化して眺めることのできた鶴見は、アメリカが日本の「外」ではなく、日本もアメリカも「内」であると見える地点に立っていた(『期待と回想』)。
『戦時期日本の精神史1931〜1945年』岩波現代文庫の「解説」を執筆している加藤典洋は、マギル大学で鶴見の英語の講義を聴講していた1人である。「この人と会うことで、自分はやはり完全に変わった」とまで加藤は述べている(「ヒト、人に会う——鶴見俊輔と私」)。日本帰国後に「アメリカの影」で文壇デビューすることになる加藤の物の見方には、北米経験によって培われた部分もきっと少なくない。『北米体験再考』は鶴見俊輔の本のタイトルだが、加藤典洋が同じタイトルの本を書いたとしたら、鶴見俊輔が大きな位置を占めたのではないだろうか。
「日本の外に出て日本を相対化して眺めることのできた鶴見」と書いたが、彼は自分が内側に抱えている歪みを突き詰めた果てに、普遍的な価値を見出そうとする志向性も備えていた(「根もとからの民主主義」1960年)。これはおそらく加藤典洋が『日本という身体』において、「日本的なるもの」に対して批判的視座を得るには、外部へと逃れるのでは不十分で、内側に落ちきって出ることが必要だと述べていることに通じる。『日本という身体』は昨年度の「世界歴史と東アジアIII」読んだのだが、実は当時の受講生にここのくだりの意味を尋ねられ、なんとなくわかるようで、よくわからなかったのである。鶴見俊輔と重ねて読み直すことで、少し理解を深めることができたように思われる。
伊達聖伸(総合文化研究科)








