2021年7月14日(水)、EAAセミナー「東アジアからの批評理論」合同発表会が開催された。本セミナーは、EAAの石井剛氏(東京大学・EAA副院長)、張政遠氏(東大・総合文化研究科)、王欽氏(東大・総合文化研究科)が開講する大学院授業の共同企画である。近現代東アジアの思想・文学を専攻する大学院生5名は研究発表を行ない、石井氏、張氏、王氏はコメンテーターを務めた。

まずは張氏から本イベントの趣旨説明がなされた。その後、一人目の発表者王雨芊氏(東大大学院)は「柳田國男の『海上の道』から「一帯一路」の再検討」と題する発表を行なった。王氏は現在中国によって推進されている「一帯一路」というアジアからヨーロッパ、アフリカまで包摂する経済圏構想と、日本人・日本文化南方由来説を唱えた柳田國男(1875−1962)『海上の道』を比較し、文化交流における海の役割に注目した。王氏によれば、海上の道は文化の道でもあり、「一帯一路」と『海上の道』は多くの違いを含みながら、技術の移転、文化の伝播という点、ナショナリズムを背景とした点では一定の共通性が見られる。その後のディスカッションにおいて、『海上の道』と近代日本のナショナリズムや吉本隆明らの議論の関連、海の交流に特有な覇権性・拡張性、「一帯一路」と「改革開放」路線の違い、文化の伝播とその背後にある経済力の関係など、様々な問題が提起された。

次に崔高恩氏(東大大学院)は「日野啓三と朝鮮」というテーマについて発表を行なった。崔氏は現代日本の作家・評論家日野啓三(1929−2002)の「無人地帯」(『文學界』1972年5月号)を取り上げ、植民地朝鮮で幼少期を過ごし、戦後に韓国特派員やベトナム戦争取材という体験を持つ日野の作品において「朝鮮」の現実がどのように受け止められたかを論じた。崔氏にしたがえば、日野のテクストでは「故郷」であるはずの「朝鮮」は歴史の大きな断絶と連続のなかで確固たる固有名を持ちえず、むしろ故郷ではない、どこにも属さない異質な領域が見出される。そこで「越境」の新たな可能性が模索されているという。発表後のディスカッションでは、東アジアの近代国民国家の構築に見られた脱漢字の動きと対照的に、日野のテクストで漢語をあえてローマ字で表記することはむしろ国民国家を相対化する効果を持っているということが指摘された。ほかに近現代中国の言語政策、無人地帯における風土・歴史の問題も議論された。
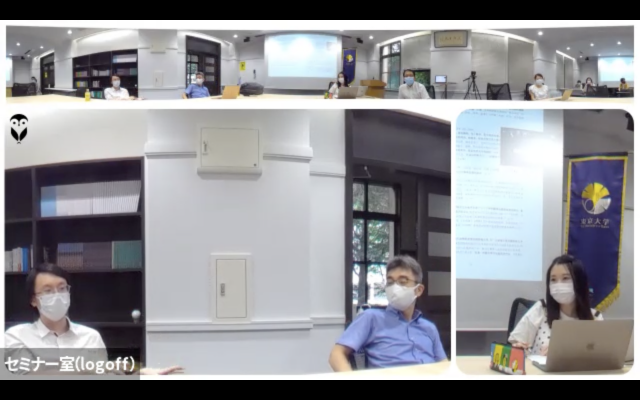
続いて朝倉智心氏(東大大学院)は「文芸理論の側面から見た梁魯「硬訳」論争」というタイトルで発表した。朝倉氏が焦点をあてたのは1929 に起きた翻訳をめぐる梁実秋(1903−1987)と魯迅(1881−1936)の論争である。この論争において、魯迅は中国を変革するための最後の希望を「硬訳」に託したのに対して、梁実秋は魯迅の翻訳がもはや「死訳」に近いものだと批判していた。朝倉氏は先行研究を詳しく整理しつつ、これまでの研究は論争のイデオロギー的な側面に着目したものが多いと指摘したうえで、あらためて梁・魯の文芸理論とりわけ言語観と美学を考察したいと述べた。ディスカッションでは、魯迅自身における二つの時期の翻訳、すなわち1920年代半ば以降の翻訳と日本滞在期の翻訳(『域外小説集』)に見られた方法上の違い、翻訳理論をめぐる論争と翻訳の実践との区別、翻訳理論による新しい中国語の創出などをめぐって討論がなされた。

合同発表会の後半は、胡婧氏(上智大学大学院)の「啓蒙の文脈における「近代性」批判―張君勱の「人生観」論を導きとして―」と題した発表に始まった。胡氏は、近代中国の知識人たちによるベルクソン哲学の「直観」概念の受容について、1920年代の張君勱(1887-1969)による「人生観」論を中心に考察している。「人生観」論や、張とベルクソンのインタビュー録などを分析する中で、西欧文明に直面し自己分裂や葛藤を抱えていた当時の中国の知識人たちにとって、ベルクソン哲学が「科学理性」と「心」との関係について考える手がかりであったと胡氏は指摘する。さらにそのベルクソンの「直感」概念が近代心学に吸収され、変容したものが、後の近代中国における直覚主義の礎になったと論じた。発表後の討論では、張君勱の論争における科学と人生観との関係や、「啓蒙」という言葉自体が孕む複雑性などについて議論が交わされた。

最後の発表を担当したヴィクトリヤ・ニコロヴァ氏(東大大学院)は、「想像としての中国――戦争の時代を生きた中国研究者を再考する」というテーマで報告を行なった。戦前と戦後の断絶性を前提とした日本における中国研究史に疑問を呈するニコロヴァ氏は、日本人中国研究者・実藤恵秀(1896−1985)が戦前から戦後にかけて展開した研究活動に光を当てることにより、戦前・戦後という二元論的な捉え方を乗り越えようと試みている。この研究では研究対象となる中国研究者の「中国認識」の検討が欠かせないため、今回の発表では実藤と竹内好(1910−1977)の中国観が取り上げられた。発表後のディスカッションでは呼称問題、すなわち「支那」あるいは「中国」と呼ぶのかという問題に議論が及んだ。こうした呼称問題は、研究者各々が研究対象地域をどう捉え、向き合い、そのうえで何を目指すのかを問う、分野を超えた共通の課題ともいえよう。ニコロヴァ氏が「想像する中国」という含蓄に富んだ発表タイトルをつけた背景には、こうした問題意識が少なからず絡んでいるという。
3時間に及んだこの合同発表会では、発表者たちの数ヶ月にわたる学びの成果や、授業で取り上げられたテクストの読みの深化を垣間見ることができた。石井氏、張氏、王氏のコメントや、参加者からの質問を通して得た示唆を、発表者たちがどう自身の研究に活かすのか、今後の進展が楽しみとなるような充実した発表会であった。
報告者:郭馳洋(EAA特任研究員)、片岡真伊(EAA特任研究員)








