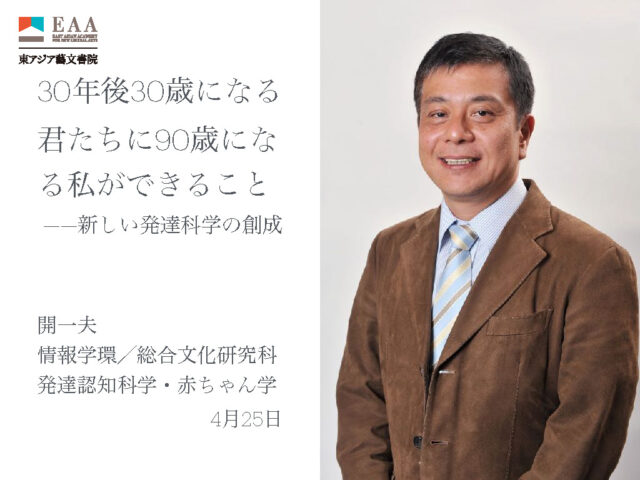
2025年4月25日(金)、 EAAの主催で学術フロンティア講義「30年後の世界へ——変わる教養、変える教養」が駒場キャンパス18号館にて開催された。第3回を迎えた今回は、開一夫氏(東京大学大学院情報学環・総合文化研究科)が「30年後30歳になる君たちに90歳になる私ができること:新しい発達科学の創成」と題して講義を行った。

「30年後、あなたが幸せになるために、いま何ができるのか?」という問いかけから幕を開けた講義は、「30年後、30歳になる人たちが幸せになるために、あなたが出来ることはなんでしょう?」という言葉で締めくくられた。講義においては、開氏が人工知能の研究を経て「赤ちゃん学」へと至った研究の歩みを振り返りつつ、現在取り組んでいる発達認知科学の研究を通じて「30年後の幸せ」に貢献しようとする試みが語られた。開氏は、現代の発達科学が直面している課題として、全生涯周期にわたる連続的なデータの不足、専門領域間の断絶、実験パラダイムの相違を挙げ、これらに対する自身の問題意識とアプローチを共有した。なかでも注目すべきは、分散型PDS(Distributed Personal Data Store)という構想が、研究データ活用のあり方に新たな可能性をもたらし、データという研究資源を未来のためにより豊かに共有する手段となり得るという点であった。

講義内では、開氏が行っている実験の紹介もあり、科学技術が赤ちゃんの発達に与える影響について考えるよい機会となった。また、これまでの技術発展が人間の知覚や学習メカニズムにどのような変化をもたらしてきたのか、そしてAI時代を迎えた現代において我々はいかにして技術と向き合うべきかを問い直す契機となった。講義後には、開氏が提示した分散型PDSモデルに関する質問や、テクノロジーと人間の発達との関係性をめぐる活発な議論が交わされた。

2025년 4월 25일(금), 도쿄대학 EAA 주최로 학술 프론티어 강의 「30년 후의 세계로——변화를 담는 교양, 변화를 여는 교양」제3회가 고마바 캠퍼스 18호관에서 열렸다. 이번 강의는 히라키 카즈오 교수(도쿄대학 대학원 정보학환·총합문화연구과)가 「30년 후 30살이 될 당신에게, 90살이 될 내가 할 수 있는 일: 새로운 발달과학의 창성」이라는 제목으로 강연을 진행했다.
“30년 후의 행복을 위해 지금 무엇을 할 수 있을까?”라는 질문으로 시작된 강연은, 히라키 교수가 AI 연구에서 ‘아기학(赤ちゃん学)’으로 전공을 바꾸게 된 여정을 소개한 뒤, 현재 자신이 하고 있는 발달인지과학 연구가 미래의 삶에 어떻게 기여할 수 있을지를 모색하는 내용으로 이어졌다. 그는 발달과학의 주요 과제로 전 생애에 걸친 연속적 데이터 수집의 부족, 분야의 전문화로 인한 각 영역 간의 단절 등을 지적했는데, 분산형 개인 데이터 저장소(PDS)라는 아이디어를 소개하면서 만약, 분산형PDS가 도입된다면 연구 목적을 위해 수집된 데이터를 폭넓게 공유할 수 있게 됨으로써 미래 세대를 위한 연구 자원이 더욱 풍부해질 수 있다는 가능성을 제시했다.
강연에서는 히라키 교수가 진행했던 실험을 직접 소개함으로써 기술이 영유아 발달에 미치는 영향에 대해 생각해볼 수 있었는데, 이는 AI 시대를 살아가는 우리가 기술과 어떤 방식으로 관계를 맺어야 할지를 성찰하는 기회가 되었다. 강의 후에는 플로어로부터 PDS 모델에 대한 질문과 함께, 기술과 인간 발달의 관계를 둘러싼 활발한 토론이 이어졌다.
報告者:洪信慧(EAAリサーチ・アシスタント)
リアクション・ペーパーからの抜粋
(1)発達心理学などの研究を見る度に、社会・経済的に成功する大人に育てる子育て法の確立と誰もが幸せになれる社会を目指すことがどうしても大きなパラドックスに見えて仕方がなかった。幼少期にどのような施しをすると子供が成功するのかという法則の発見が進む一方でそれは多様な人間の存在を否定しているようなマジョリティへの希求という側面もある。多様性を認めていく社会の動きとは裏腹に、子育てにはびこるピリピリとした空気は年々強まっていて、とても親になるには生きにくい世の中だとも思う。幸せは有限ではないということを我々の世代が身をもって示していくことで懐の広い社会にしていきたいと思った。(教養学部(前期課程)2年)(2)講義ののちに近くの方と話していて、実験には赤ちゃんの能力を測定するという側面があり、その結果が共有されることで被験者である赤ちゃんの将来の可能性が制限されてしまう可能性があるという意見を聞いた。それを聞いて、その意見に対するコインの両面として、私は発達認知科学的なアプローチにより、赤ちゃんの学習能力などをよりよく発揮する形で教育が可能になるのではないかと考えた。この授業の前回の国分先生のお話で、教養とは暇を退屈にしないための遊びの手段を増やすものであるというような議論があった。
今の子供たちがよりよく人生を楽しめるように、よりよい教養教育を行う(=よりよくさまざまなものを享受できるようになる)にはどうすればよいのか、という問いを考え出した。そのアプローチとしては、赤ちゃんが興味を持ち、自分でやってみたいと思う見せ方を特定したうえで、文学や絵画、茶や料理などの深いコンテンツを味わう動線を作っていくというものになるだろうと思う。(教養学部(後期課程)・4年以上)








