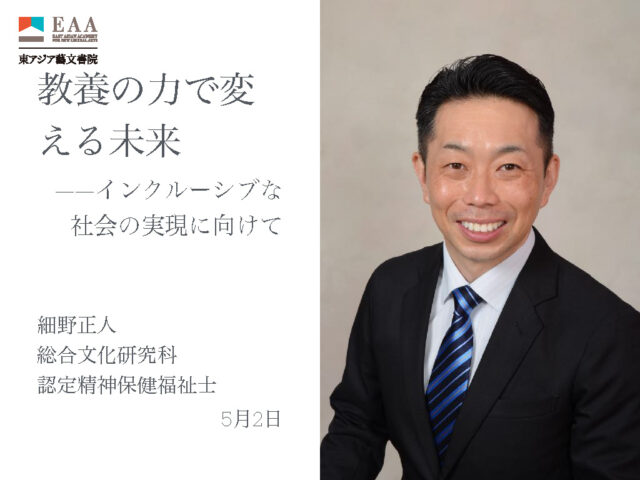
教養とは何かを考えるとき、それは単なる知識や学問の蓄積ではなく、人間としていかに他者と関わり、自己と向き合い、そして生を高めていくかという姿勢であると言えよう。教養を身につけ、より包摂的な社会を実現するために、2025年5月2日(金)より、学術フロンティア講義「30年後の世界へ——変わる教養、変える教養」の第四回が実施された。今回は、総合文化研究科の細野正人氏による講義「教養の力で変える未来:インクルーシブな社会の実現に向けて」が行われた。
細野氏は精神保健福祉の観点から、二つの臨床事例を通じて、精神疾患や困難を抱える人々への理解と支援のあり方について考察を行った。講義の中心となる主張は、インクルーシブな社会を実現するためには「教養としての福祉」を広く身につけることが不可欠であるという点にある。すなわち、他者への思いやりや多様性を尊重し、共感する力を涵養する必要がある。先進国(G7)の中で自殺死亡率が最も高い日本においては、今後、精神科医療にのみ依存するのではなく、コミュニケーションやエンパワーメントの役割が一層重要になると指摘され、また精神疾患に対する偏見を払拭し、早期発見・早期介入を促進するための啓発活動の強化も求められている。さらに、細野氏は、精神疾患や困難を抱える人々が回復を目指し、自分らしさを取り戻す過程における「パーソナル・リカバリー」の重要性を提示した。

講義は参加者に多大な刺激を与え、活発な議論や多くの質問を引き出す契機となった。身近に精神疾患や困難を抱える身近に知人に対してどのように対応すればよいのかなど、参加者からは積極的な質問が多数寄せられた。これらに対して細野氏は、自身の臨床経験を踏まえた実践的な助言を行い、参加者にとっては貴重な講義になっただろう。

講義を通じて示されたのは、教養とは他者を理解し、支えるための知識や態度であると同時に、時には自分には何もできないという現実を受け入れる力でもあるということだ。精神疾患や困難を抱える人々に寄り添う際、解決策を提示できない場面も少なくない。そうしたときにこそ、自分の正論を振りかざすより、自らの限界を認識し、それでも共に在り続けようとする姿勢こそが、深い意味での教養の表れなのではないだろうか。この「受け入れる力」は、支援する側とされる側の関係性を超えて、人間同士が共に生きるための基盤となるものである。

報告者:劉仕豪(EAAリサーチ・アシスタント)
リアクション・ペーパーからの抜粋
(1)教養としての福祉を身につけるとは、「自分らしさ」を尊重する手立てを学ぶことだと思いました。人間誰しも自分らしさを持っています。それは自尊心を強化します。逆に自分らしさを失った瞬間、自尊心は傷つけられます。自尊心が傷つけられると、自分に対しても他人に対しても、物に対してもセンシティブになり、メンタルが崩れ、講義であったようなシチュエーションに陥ってしまうのではないかと思います。つまり、自尊心に通ずる自分らしさを認識できなくなった瞬間に自分を見失い、普段であれば信じられないような行動に出るのだと思います。多くの人と相談して自己決定をするプロセスによって自分らしさは形成され、洗練されると思います。他人の自分らしさを尊重するにはまず自分の自分らしさをしっかりと認識していなければならないと考えます。その上で議論の中で「私はこのように考えるけど、あの人にはこういう考えもあるんだ」、「その視点を踏まえるとこういうことだな」と考えます。ここに他人の自分らしさの尊重が隠れていると思います。他人の意見を受け入れる、すなわち他人を尊重するということだと思います。これは自分の意見があってこその感情です。故に、自分の自分らしさを認識せずには他人の自分らしさなど尊重し得ないと思います。
ここで述べたかったことは、自分の自分らしさを認識するために教養はあるのだと思うということです。それは他人の自分らしさを尊重するためには、自分の自分らしさを認識していないからには何も始まらないと思うからです。(教養学部(前期課程)・2年)(2)自殺や精神疾患など、「『普通』の暮らしをしていれば起きない」と思われているようなことについて、教育現場や公的な場で話されないという現実はどのように捉えるべきなのか。確かにそうしたことについての語りはセンシティブで精神的に負担の大きいものになるため、話の中に出てくる人のためにも話を聞く人のためにも「慎まれている」と捉えることもできるかもしれない。しかしそれ以上に、自殺や精神疾患などが起きている現場が「異常」だと考えられていることがその大きな理由であり、問題なのではないのだろうか。「教養としての福祉」の第一歩は、こうした「異常」という判断と、それによる無意識的な排除を自覚し、やめていくことなのではないだろうか。細野先生のお話の中で「障害児から元気をもらった」や「大学生の相談内容が精神的なものになってきたことはいいこと」というお話が印象深かった。先生から、「思いやり」や「共感」という言葉で形容した上から目線の態度ではなく、真に向き合ったからこそ歩み寄ることのできる姿を感じた。自分がそうなれるのか、あるいはそうした意識を常に忘れずにいることができるのかはわからないが、「教養としての福祉」という志に少しでも近づけるようにしたいと思う。(教養学部(後期課程)・3年)








