仕事を終え日が暮れ、家路を急ぐ感覚をしばらく味わっていない。在宅勤務が続き、家にずっといながら、実は家にいないのではないかと感じるようになった。それはおそらく、私の中で自然と理想化された「家」と私の現実とが一致せず、何らかの不安を感じているからであろう。
私の父も母も「仕事」を好まなかった。家で好きな絵を描き、庭の手入れをし、動物を飼う。好きでもない「仕事」をするためにしぶしぶ家を出て、休日は自分たちの趣味で家を飾り、庭に手を入れ、ごちゃごちゃとした「混濁」を作り出していた。人生には不満を抱いていたようだが、自分たちの日常生活に没頭しているのは間違いなかった。母は家のことを、父は庭のことばかり考えていた。
大人になって私はふと、自分の育った家を思い出すことがある。今住んでいる家には「混濁」がまだない。やみくもに蒐集した本で散らかってはいるが、「こうしたい」という意思のもと生成された「混濁」が、少なくともまだないのだ。私の実家は、父が庭に無造作に建てた小屋や拡張された池、それに負けじと母が並べた植木鉢のせいで、ずいぶんごちゃごちゃとしていたが、その「混濁」こそが、わたしの「家」だった。
自分にとって、もっとも身近な存在である家が、私たちの習慣や伝統を形作り、感性や思考を構築する。私の「家」が、私の思考にどのように影響しているのか、私自身はわからない。なぜわからないかといえば、私が見えている世界そのものが、家をはじめとする日常生活から形作られた私自身の思考から成り立っているからであろう。私は日常生活に無頓着であるようで、日常生活は私の在り方を大いに規定している。
2021年9月10日(金)13:00よりオンラインで行われた、第4回「部屋と空間プロジェクト」研究会(第7回EAAブックトーク)は、大石和欣『家のイングランド:変貌する社会と建築物の詩学』(名古屋大学出版会、2019)をとりあげた。司会は田中有紀(東洋文化研究所)が担当し、主な書評は滕束君(EAAリサーチアシスタント)が担当した。
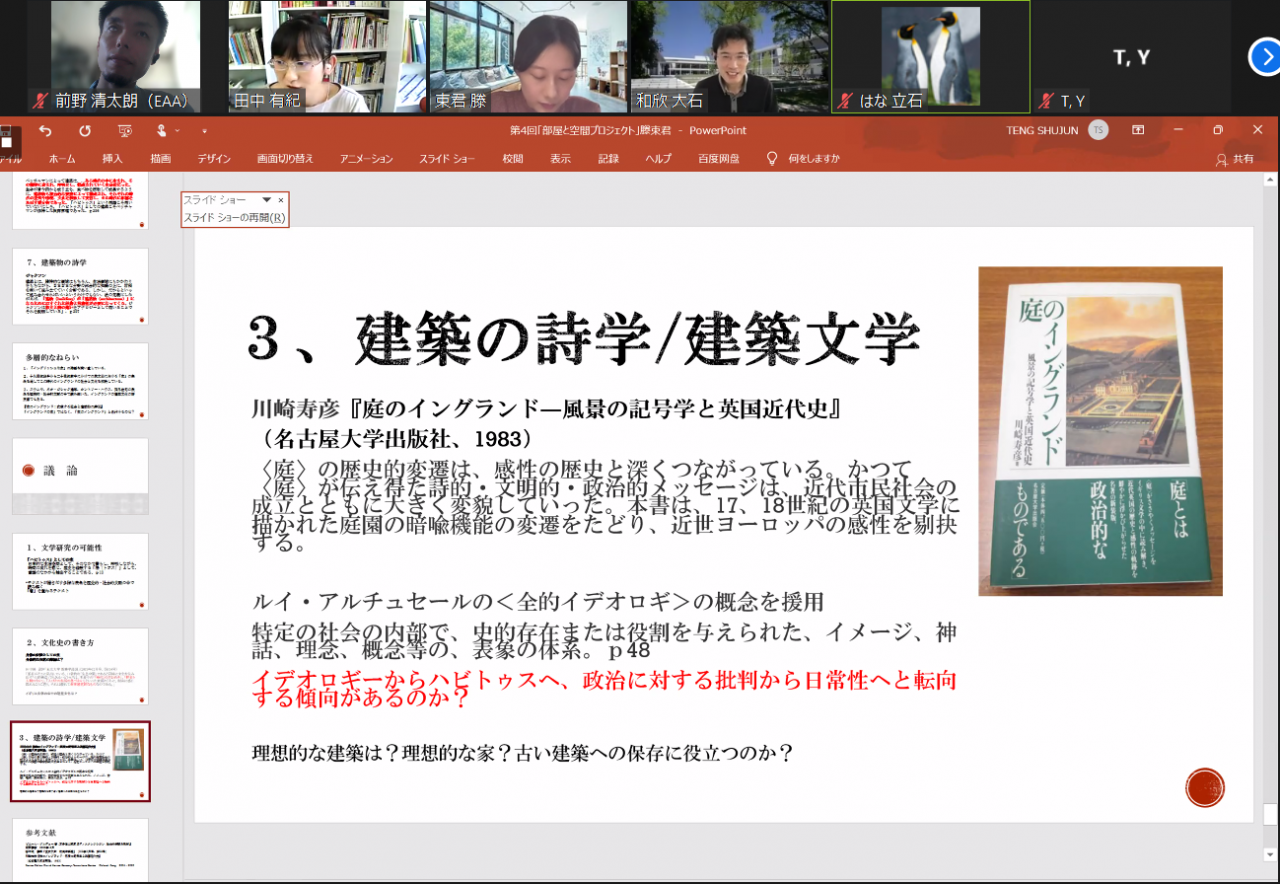
『家のイングランド』は19世紀後半から20世紀前半のイギリス文学に描かれた家の表象をとりあげ、同時代の歴史的・社会的文脈の中で、どのように「イングリッシュな」家をめぐる言説とイメージが生み出されていったのか、その位相をたどる。そして、そこに習慣的に呼吸し、住み、感じる日常生活的生息空間としての家が、文化を生み出す心的構造としての「ハビトゥス」としても出現する姿を確認する。
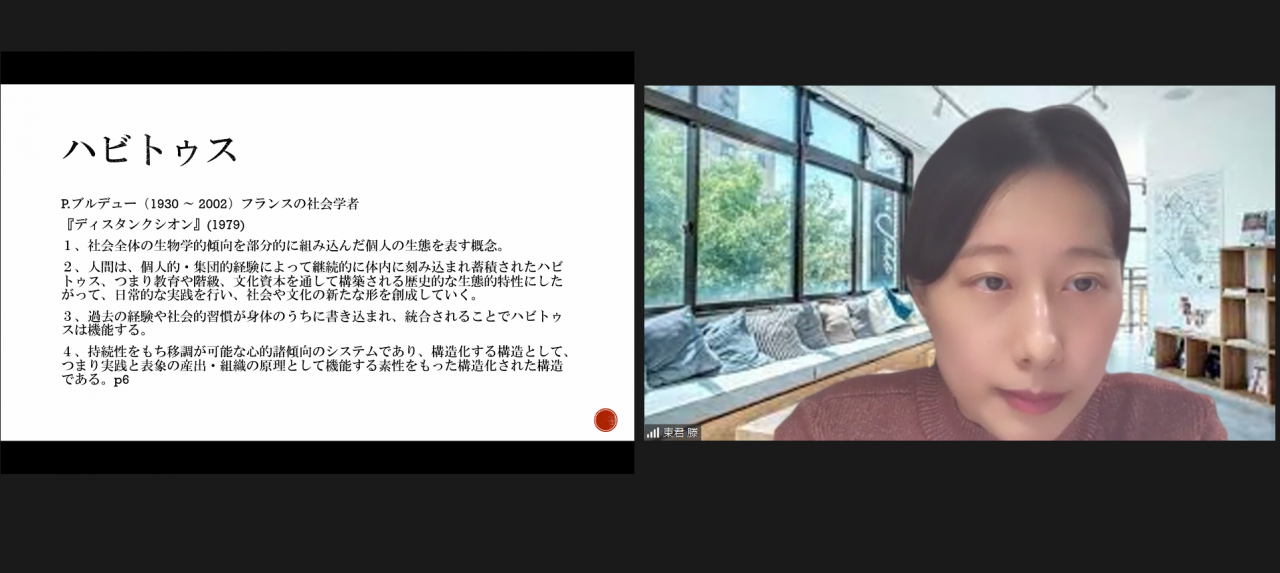
滕氏の報告では各章の内容を紹介した後、自身の感想を絡めながら、本書の持つ意義について説明を行った。まず、本書が「イングリッシュな家」の神話を問い直したことを評価する。『家のイングランド』はカヴァー図版の平和な雰囲気から一転して、理想的な家へのアンチテーゼであるスラムから始まる。中流階級的な美徳と言語によって批判的に描き出されたスラムだが、ディケンズもまた『オリヴァー・トゥイスト』でスラムと中流階級の家の対比を表象する。その一方で彼は『クリスマス・キャロル』で、家庭愛に裏打ちされた空間こそが「家庭(ホーム)」であり、たとえ立派な邸宅であってもディストピアへと反転する可能性を描く。このように、本書はディケンズの小説に描かれるいくつかの家の表象を対比することで、その背後にあるディケンズの家への認識を浮き彫りにした。厳密な歴史考証と詳細なテクスト分析により、私たちは本書を通して、文学における家の表象がいかに豊富であるか、また表象文化学において文学をどのように用いるかについても、多くのことを学ぶことができる。十九世紀後半から二十世紀前半にかけての英文学における家の表象を通して、この時代のイングランドの社会と文化を描き出したのも本書の特色であろう。たとえば、『ジキル博士とハイド氏』(1886)や〚ドラキュラ』(1897)で描かれる、スラムと上品な邸宅の表裏一体は、中流階級の恐怖の目線を通し、「退化」の過程にある帝国の二面性を反映しているという。また、スラムや、ネオ・ゴシック建築、カントリー・ハウス、郊外住宅の表象を歴史的・社会的文脈の中で読み解いた、イングランドの建築文化の研究書でもある。筆者が、文学研究として「ハビトゥスとしての家」を読み解くことを「日常的な生活空間として、そのなかで暮らし、呼吸しながら、時間の流れを感じ、歴史を経験する「場(トポス)」として、言語のなかから抽出することである」(p13)と表現するようにテクストが描きだす多様な表象(家のほかにも、音楽や動物など)を歴史的・社会的文脈の中で読み解くような、文学研究の新しい可能性が見出せるのではないかと滕氏は述べた。
そして以下の質問を投げかけた。本書のタイトルが、「イングランドの家」ではなく「家のイングランド」であるのは何故か。また、田中純氏の書評(「東京大学 教養学部報」第614号、2019年)で「ハビトゥスは、本書中の「「時代」のざわめき」、「歴史と人間の匂い」、「人びとの生活の息づかい」といった表現のうちに、如実に感じ取れるように思う。それは優れて身体感覚的なものなのである」というが、身体感覚のうち、聴覚に関する文化はどのように捉えられるか。『庭のイングランド―風景の記号学と英国近代史』(名古屋大学出版社、1983)を執筆した川崎寿彦氏は、イギリスのカントリー・ハウスは、ルイ・アルチュセールの「全的イデオロギー」の好例だと述べるが、本書は、イデオロギーよりもハビトゥスへ、政治に対する批判よりも日常性へと目を向けているということなのか。また、本書が様々に示す理想的な建築像は、古い建築をどう保存するかという問題に役立つのではないか。
大石氏は以下のように回答した。本書に大きな影響を与えたのは、IHS(大学院プログラム「多文化共生・統合人間学」)のプロジェクト「生命のかたち」であった。ここで生まれた、「身体として家がどう感じられているか、それが記憶の中でどう残存し、私たちの見方を規定しているか」という「問い」が本書の根源にある。身体でつかんだ知覚が心の中にどう現われてくるかについては、たとえばハイデガーが「空間に存在が意味を付与することによって、逆に空間が存在に意味を付与し、相互互換的な関係により、空間が単なるハコモノではなく実存的なものへ変わっていく」と考えたように、現象学を参照して考えることができるだろうし、聴覚も同じように考えられるのではないか。身体感覚に関しては「アフォーダンス」という概念も重要である。鳥・虫が木にとまるなど、動物は自分の身体に即して色々な物を使う。物は形・色・手触りによって扱われ方が変わってくる。家・住居・部屋にも「アフォーダンス」がある。自分が使いたい部屋に変え、使いたいものを置き、居間やピアノルームなど用途を考える際、空間の形や素材が重要な意味を持つ。音楽もTPOによって聴かれ方が大きく異なるだろう。

また本書は川崎氏の『庭のイングランド』を強く意識し、タイトルを決め、同じ出版社から刊行している。『家のイングランド』というタイトルには、家によって浮かび上がらせることのできる、イングランドの文化という思いを込めた。「イデオロギー」は、80年代文学研究のひとつのパターンである。身体に関心を持つ本書は、ピエール・ブルデューがハビトゥスという概念を建築学に使っていたことから着想したが、ハビトゥスだけでは捨象されてしまう要素もあったと認識している。
保存については、プリザベーションよりコンサベーションが重要だと考える。そのまま保存するのではなく、使っている人の使い勝手が良いように変更を加えながら残す、つまり「使いながら保全していく」ことが重要なのではないか。住む人がいることで、都市のバイタリティも生まれ、都市の中には異なる歴史の層が残されていく。
ほかの参加者からも多数の質問があった。張政遠氏(総合文化研究科)の「ハイデガーが「田舎」へと帰っていったように、建築をめぐり、農村やコテージを礼讃することの裏には、近代化への批判という読みも可能なのではないか」という質問に対し、大石氏は「農村の実態・実情とは関係なく、都市が洗練されたものになればなるほど、農村が比較対象となるのではないか」と応答した。
前野清太朗氏(EAA特任助教)の質問「過剰に批判されたり、逆に理想化されたりする「スラム」について、どう考えるか」について、大石氏は「金澤周作氏の書評(『史苑』81(2)、pp.141-149、立教大学史学会、2021)が指摘したように、実際にスラムに住んでいた人たちがどう考えていたのか、書かれたものからきちんと検証していく必要があるだろう」と述べた。また、たとえば「農村の木など、どこでもあるようなものにも場所性はあるのか、都市のモールや商店街なども、ある人にとっては大変重要な「場所」になりうるが、ハイデガーの「田舎」も、結局「住めば都」ということになるのだろうか」という質問に対し、大石氏は「どこにでもある竹藪でも、本人の記憶・身体・生活と結びつき大きな意味を持つようになる。擦過性(長年住むことで、部屋に「傷」がつき蓄積されていく)が、ある人にとって重要な意味を持つ場所となる」と答えた。
長いイギリス滞在経験を持つ片岡真伊氏(EAA特任研究員)は、築600年の家に住む友人の家を訪れ、家族でどのようにリノベーションしていくかについての話を聞いたそうだ。この家のうち、中世から引き継がれていたのは、キッチンの窓ガラスのほんの一部だけだという。アメーバのように増改築を繰り返す生活空間、文化の層を内包していく家という存在を、本書を読みながら考えていたという。そして、いまイギリスが重視するのは「ブリティッシュネス」という概念であり、多様性を重視する「ブリティッシュネス」の中で、「イングリッシュネス」はどう機能していくのかと質問した。さらにコロナ禍において「都市から地方へ移動する」現象が見られ、最近では古民家に憧憬を抱きリノベーションを行うことも流行しているが、このような現象についてどう見るかと質問した。
大石氏は、以下のように返答した。「ブリティッシュネス」は政治的に正しく重要な概念であるが、本書の中ではあえて「イングリッシュネス」を使った。たとえば、スコットランドとイングランドの家は異なり、違いは違いとして認識すべきである。イングランドの専門家は、イングランドについて書くという立場をはっきりさせることが文化への敬意である。また「地方への移動」「古民家への憧憬」について、古いものを使っていくことの大切さは理解できるが、都市には都市の良さ(便利さ、バイタリティ)がある。それぞれの生活スタイルが異なり、農村は決して楽なところではなく、マイナス面も意識し、そこでのコミュニティの大切さをきちん理解した上で行くべきだと考える。また、リノベーションについても、どのようなものがその風土に合っているかを検討した上で進めていくべきだと述べた。
最後に司会から「たとえば中国でも「家」は重要だが、ハコモノとしての「家」への関心というより、「家」の内実(家族、祖先)への関心が強い。「家」に自らの理想を投影しようとするのは、イングランド特有の文化なのだろうか。また、本書の「イングリッシュな伝統」とは結局何なのか」と質問した。これに対する返答は以下の通りである。「家」への関心については、イングランドの風土(冬は暗くて寒く、外で色々なことができない)と実用性(機能、心地よさ)を重視する文化が根底にあるのではないか。また「イングリッシュな伝統」とは、格式やディグニティ―など様々なものの背後に必ずある、居心地の良さを追求するような、プラクティカルな部分なのではないか。
私は、大石氏がIHSのプロジェクトで「家と身体」という着想を得たという話がとても印象に残っている。ある研究者が、偶然に、とあるプロジェクトに巻き込まれていく過程の中で、自らの研究の中に新しい光を見出す。たまたまその「場」に参加していたメンバーの研究あるいは何気ない発言が、のちの自分の研究を大いに広げていく。今はオンライン空間が中心だが、EAAのある101号館もまた、私にとって、学生時代に事務手続きをした場所、UTCPにいた時にシンポジウムの前に他のメンバーとおしゃべりした場所、そしていまEAAの活動をする拠点というふうに様々に変化し、いろいろな「傷」を残していく。この「場」は、きっと現在進行形で、私のみる世界をまた別のかたちへと構築しなおしているのだろう。
報告:田中有紀(東洋文化研究所)








