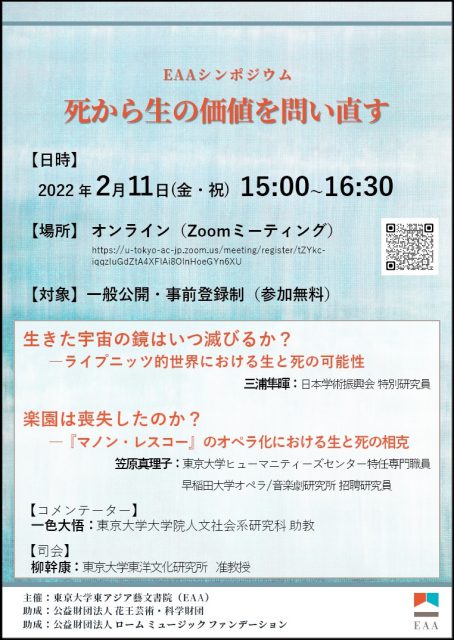
2022年2月11日(金)日本時間15時より、EAAシンポジウム「死から生の価値を問い直す」を開催した。これは人間の生と死に焦点をしぼり、その「価値」についての再考を試みるものである。当日は三浦隼暉氏(日本学術振興会特別研究員)と笠原真理子氏(東京大学ヒューマニティーズセンター特任専門職員、早稲田大学オペラ音楽劇研究所招聘研究員)のお二人をスピーカーにお招きした。
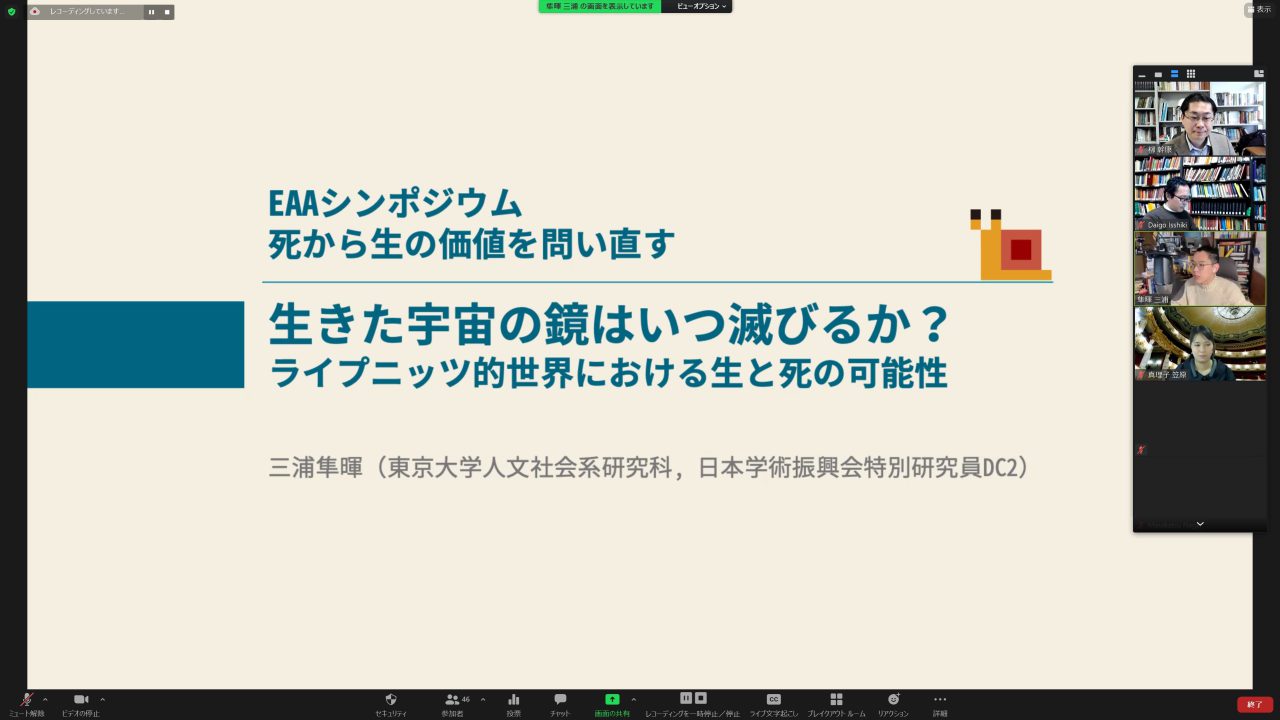
三浦氏はライプニッツを中心に近世哲学や生命思想史を研究されており、「生きた宇宙の鏡はいつ滅びるか?:ライプニッツ的世界における生と死の可能性」という題目でご発表いただいた。三浦氏の発表は、今日力を持つ死の語り――科学技術的に人の死を判定すること――からこぼれ落ちた語りが存在するのではないかという問いに端を発するものである。三浦氏はまず、今日的な死の語りの背後に「死の私的所有」という観念が存在していると指摘したうえで、その観念が19世紀初頭に先鋭化するまでの流れを概観した。それは死を身体的側面のみに即して語る流れであり、その過程で失われた魂を含む死の語りを掘り起こすことで、今日とは異なる死の語りが探究できる。そこで三浦氏はライプニッツの議論を参照し、彼が強調する三人称的同⼀性(他の人々により規定される同一性)に着目したうえで、一人称的ではなく他者に開かれた道徳的な死の語りの可能性を、科学技術的なものに局限された死とは異なる側面として描き出した。
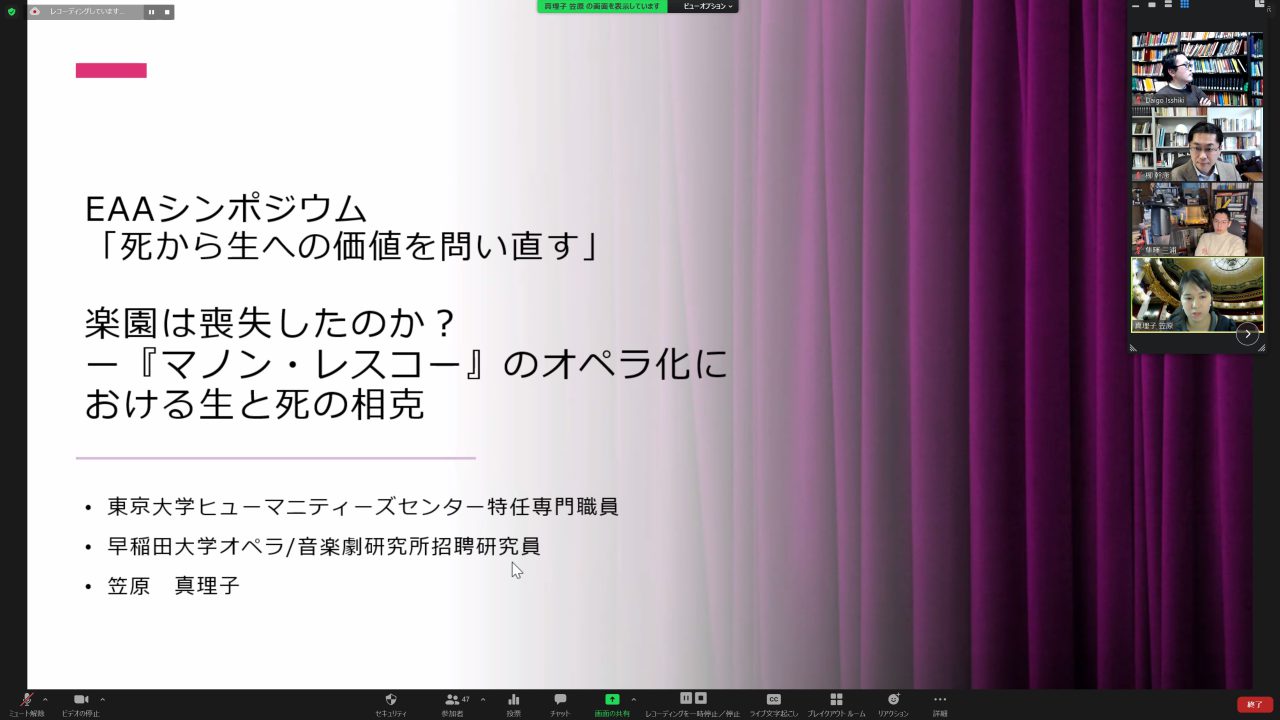
笠原氏はオペラ、ミュージカルを研究されており、「楽園は喪失したのか?:『マノン・レスコー』のオペラ化における生と死の相克」という題目でご発表いただいた。『マノン・レスコー』は悪女小説の先駆と称されるもので、1731年に初稿、1753年に決定稿が出版された。早くから大反響を呼び、今日にいたるまで戯曲・オペラ・バレエ・映画など様々なジャンルにおいて約50もの作品が制作されている。笠原氏はこのうち原作、およびオペラ作品一点(1884年マスネ作曲)を取り上げ、以下のように指摘された。すなわち、原作ではマノンの悪女・聖女としての両面性が描きだされており、オペラはそれを継承しつつアレンジを加えている。そのアレンジのうち注目すべきものとして、女性の社会進出にともない流行したファム・ファタール(男性に悲劇をもたらす運命の女)のイメージがオペラに採り入れられていること、原作では新大陸アメリカが理想郷として描かれていたのに対し、フロンティア消失が間近に迫った19世紀末のオペラ作品では楽園アメリカの話が削除されていること、オペラではマノンの死が自ら望んで得た救済とされていることなどがある。以上の指摘をしたうえで笠原氏は、その後のオペラ作品を複数紹介し、宗教的救済を示す必然性が薄れる現代においては、「救済」そのものの必要性を疑ったり、その新たな意義づけを模索するなどの新たな動きが見えると論じられた。
以上のご発表の後に、コメンテーターの一色大悟氏(東京大学大学院人文社会系研究科助教)より、以下二点のコメントをいただいた。

第一に、二氏の発表の内容を要約・架橋し、「死から生の価値を問い直す」というテーマのもとでともに議論する一つの場を構築していただいた。一色氏は、三浦氏の発表を「「死の私的所有」に対治される「死の共有」の可能性を理論の次元で示したもの」、笠原氏の発表を「劇場という場において「死の共有」が行われている具体例を示したもの」とまとめたうえで、「人間には、公共の次元において一定の価値をともなって生き、死ぬという語りがありうること、そしてそのような公共的な生死は、現代において生物としての科学的生死によってしばしば覆われてしまっているとしても、今なおすくい取られるべき意義があり、かつすくい取られてきた」と述べられた。
第二に、近代日本における仏教の事例を導入することで、両氏の発表を東アジアへと更に架橋してくださった。一色氏は仏教教理における死を三種類――(1)特定の個体が迎える死、(2)輪廻において次の生につづく死、(3)輪廻から解脱する覚者の死――に分類したうえで、近代日本の仏教学において輪廻の忌避にともない第二の死の語りが力を失ったことが、戦時教学の死の語り――国のために自己を擲つ軍人の死を(3)覚者の死と結び付ける説――の成立につながった可能性を指摘された。
その後、一色氏および聴講者の方々から寄せられた数多くの質問・コメントをめぐり、非常に活発な議論がなされた。その詳細については後日、別に機会を設けて紹介できればと愚考している。また当日は司会の柳の不手際で、予定の時間を大幅に超過してしまったが、それにもかかわらず多くの方に最後までお付き合いいただいた。この場をかりてお礼とお詫びを申し上げます。
報告者:柳幹康(東洋文化研究所)








