* 第1信 山内久明先生への手紙――(工藤庸子)
* 第2信 工藤庸子先生への手紙――(山内久明)
【3】山内久明先生
工藤庸子
素晴らしいお便り、ありがとう存じます。何度も読み返しながら、返信をしたためております。まずは静かに封印を解かれたことがらについて。1995年1月の『教養学部報』(往復書簡【1】に掲載)にさりげなく、ただしはっきりと《広島で被爆した筆者》と書いておられることに、あらためて胸を突かれたと申し上げなければなりません。さらに、このたび頂戴したお便りには《父が被爆死し、私自身は疎開先から直後に入市した「二次」被爆者です》とのお言葉がありました。
大江健三郎さん自身の言葉を、これにむきあわせて、架空の対話を構成してみたいと存じます。《僕は大学でひとりの広島出身の友人をもっていたが、かれは四年間、ただ一度も、原爆についてかたることがなかった。いうまでもなくかれには沈黙する権利がある》(『ヒロシマ・ノート』)。なるほど「被爆者であるとかたる」ことと「原爆についてかたる」こととは、同じではない、それどころか……というところで、わたくしは思考停止に陥ります。と同時に、「沈黙」そのものの深甚な暗さをこのように慮ることのできた作家は、大江さんを措いて他にいないのではないか、と何かを発見したような気持になったりもいたします。
大江さんの故郷である愛媛県と広島は――これも山内先生のお言葉ですが――《瀬戸内海によって隔てられているとも、繋がっているとも言うことができる》とのこと。この絶妙な距離の感覚は、友情のキズナを手放すことなく、それぞれの道を歩まれたお二人にふさわしいと感じております。
永く大江さんの担当記者をつとめられた尾崎真理子さんによれば、大江さんが山内先生のことを話されるときには、ふと表情がやわらいで、誇らしげで優しそうなお顔になるのだとか……
さて《昭和29年入学フランス語未修》クラスの名高い「四人組」のお話。リクエストに快くお応えくださり、出来れば秘蔵のお写真も、などと、厚かましいお願いをいたしましたのにも、ダメとはおっしゃらずに……心より御礼申し上げます。なぜ「四人組」と駒場祭でのクラス演劇が、わたくしの想像する大江文学の出発点という意味で重要であるかについて、箇条書きで述べさせていただきます。
① 英文系か? 仏文系か?
《何人かの尊敬すべき仏文系の先輩方の見立てによれば、大江さんは「英国モダニズム文学の人」であった》ということ、以前に書いたとおりでございます。山内先生のお考えによれば、文学的な素養としては、英仏のどちらの選択もありえた、ということになりましょうか。戦後10年という時点での駒場の教育は、今では思い描くことも困難なほど堅実で贅沢なものでもあったという事実も、この度のお手紙でお示し下さいました。いずれ話題にできればと思っておりますが、立派な外国人教師もおられました(英文学はアントニー・スウェイト先生、仏文学はベルナール・フランク先生)。ひと言いいそえれば、進学先として専門を選ぶことは、社会的なものの選択にもつながりますでしょう。とりわけ大江さんの場合、本郷では学生でありながら「芥川賞作家」というプロフェッションをお持ちになるわけですから。
② 二十歳の肖像
「文学」への絶対的な信頼と比類なき才能とたゆまぬ努力とが、大江健三郎という作家をつくったとすれば、そうした天稟が人生にもたらす負荷や困難を知る以前、日々を存分に生きることのできた自由な時間が、駒場の2年間にあったにちがいない……先のお便りにあった《光り輝く精神の果物屋》という大江さんの自己紹介のことを考え、この謎めいた形容を表題にした志甫溥さんのエッセイを繰りかえし読んで、そう確信するに至りました(新潮社『大江健三郎全作品2』付録、1966年。先に紹介した紀要論文がきっかけで交流するようになった服部訓和さんが送ってくださった資料です)。
志甫さんのエッセイは、駒場の大江さんのポートレイトとして秀逸。文末に「1966・7・末 TBS報道局勤務」とありますから、30歳になったばかりでしょうか。山内先生はよくご存じのはずのエッセイですけれど、このブログを読んでくださる方たちのために、かいつまんで……《若くして俗塵に染まぬ光り輝く精神の果物屋》というのが、自己紹介のロング・ヴァージョンのようです(ちょっとだけ、わかったような……)。4月半ば、薄暗い教室で《幼い儀式にも似て、僕が煙草をすすめると、孫悟空のように鼻から煙を出すことは好まない、といそいで断った》のが、大江さん。新入生のクラス・コンパの席では《祖父からの拝領物という背広に身を固め、居ずまいをただして、漢学の素養からいうと、オオエ・ケンサンロウと発音する、と自からを闡明したが、僕はそれ以来、けんざぶろうという呼称が、正統ではなく、どちらかといえば猥雑なひびきさえ持っているように感ずる事になる》。簡略な「四人組」のメンバー紹介につづいて《僕ら四人は、授業中私語をかわすこと最も多いグループとなり、中でも彼の発言――多くは江戸小咄や連歌の類についての――が最も頻繁であった》。駒場祭には《彼の構成になる野外劇》を上演し、《温厚な山内久明は、舞台のうしろから死の灰に擬した紙切れを撒いた》……というところで、わたくしは「温厚な」という形容だけでは物足りない、と立ち止まり、「秘められた精神の強靭さ」という形容はどうか、などと内心でつぶやいてみるけれど、手紙の宛先でもある山内先生の肖像を、ここに描きそえる度胸はさすがにありません。
③ 『﨟(らふ)たしアナベル・リイ 総毛立ちつ身まかりつ』と駒場

『﨟たしアナベル・リイ総毛立ちつ身まかりつ』単行本書影
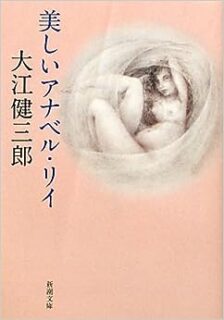
『美しいアナベル・リイ』文庫本書影
2007年に刊行され、文庫化にさいして『美しいアナベル・リイ』と改題された作品ですが、2009年の『水死』、2013年の『晩年様式集(イン・レイト・スタイル)』をもって大江文学は幕を下ろしますから、自らの人生と作品を、最終的な「パースペクティヴ」におさめようという意図が、はっきりと見てとれます(この「パースペクティヴ」という言葉は、晩年の大江さんにとって、特別な意味を持っていたのではないでしょうか)。
国際的な女優の「サクラさん」が、幼いときのボンヤリした記憶にある《恐ろしい、酷たらしい》こと――進駐軍の情報将校から受けた性的凌辱――を、女優というプロフェッションを生き抜くことで、生涯をかけて乗り越える物語。ヒロインに協力して、シナリオを書く作家とプロデューサーの二人組に、駒場祭のクラス演劇で「台本」と「演出」にかかわった二人の影がチラホラ。作中の「木守有」は、作家を正統的に「ケンサンロウ」と呼ぶことに決めているようですし。
とはいえ「物語」的には、TBS会長となられる「四人組」のお一人と「木守有」とは、ぜんぜん似ていません。それにわたくしは、何かというと「モデル問題」を持ち出す小説の読み方は苦手、というか、好きではありません。プルーストは、A夫人の衣装、B夫人の台詞、C夫人の仕草……とパッチワークのように繋いで作中人物を造形していたといわれます。それはそれとして、作中の「ケンサンロウ」の台詞を少しだけ引用させていただきますね……
とにかくね、われわれが知り合った駒場では、少年がいちばん美しかった面影を残して青年になっている……それが周りの者みなの、きみへの認識だったんじゃないか? きみはスターだった。きみは教養学科に進んだ、入れる下限の点が一番高い、駒場にできたばかりの学科でね、とにかく二年間の成績の良かった連中はそこへ行く。ぼくはフランス文学科で本郷だから〔中略〕
そういえば、あの頃、女子学生はきみのことをPetit princeと呼んでたろう?
――益体(やくたい)も無い!
この「益体も無い!」を聞いてケンサンロウは、《そういえば、駒場でのかれがこうした古風な言い廻しを好むようだった》ことを思い出す。たしかに、そういえば、志甫さんのエッセイには「自からを闡明した」とか、「古風な言い廻し」がありますけれど、もっと広い意味で、つまり「話し言葉」のレヴェルで、山内先生のご友人と「木守有」は、よく似た「文体」を持つのではないでしょうか? ただ想像しているだけ、でございますけれど。
一方、Petit princeについては、貴重なお写真を拝見して、「やっぱり‼」という感じで、謎が解けました。クラスの集合写真の前方には、この名にふさわしい方が、複数おられる……
さらに、小説の幕開けで、散歩中の作家に《――What!are you here?》とエリオットを引用しつつ声をかけてくる人物が、《英国風の発音》だったりするのも、山内先生とアントニー・スウェイト先生へのサインかな、と思ったりいたしますけれど、こんな気軽なおしゃべりを続けていると、先ほど好きではない、といったばかりの「モデル問題」に、じわじわと接近してしまいそうなので、頭を切り替えます。
『﨟たしアナベル・リイ 総毛立ちつ身まかりつ』は、女優とその保護者のような女友だち、作家と友人のプロデューサーの男女「四人組」が織りなすドラマ。出来事だけを要約するなら、1970年代半ばの壮年期に立ち上げた国際的な映画の共同企画が頓挫して、30年が経過したのち、かつての構想を発展的に継承する女たちの芸術イヴェントが、終幕を飾るという構成です。「駒場」と名指される20歳の時空が折りに触れ、蓄積した年月の裂け目から垣間見える……といったらよいでしょうか、時間論的にはみごとな三層構造をなした作品でもあります。
エリオットの『四つの四重奏』のほか、表題にも引用され、物語を説話論的に牽引する機能を持つらしいポーの詩『アナベル・リイ』(日夏耿之介訳)、ドラマの伏線となるナボコフの『ロリータ』など、英文学への温かいオマージュのようにさえ感じられはしないでしょうか……
大江さんにとって「駒場」は端的に「懐かしい」ところだったろう、とわたくしは考えております。では、進学先の本郷は? 社会的なものに否応なく接続するという意味で、より複雑であいまいなところだったかもしれない、とも思います。大江さんは、世界的な作家となられてからもフランス文学会や日仏会館のシンポジウムなどに登壇なさり、小西財団の日仏翻訳文学賞の審査員として次世代の育成にもつとめられました。その一方で――バフチンやバシュラールなどの限られた例をのぞけば――「ヌーヴェル・クリティック」をはじめとする批評の方法論や「現代思想」と呼ばれた先端的な哲学について積極的に発言なさることは、あまりなかったように思います。でもじつは、まちがいなく、あれもこれも読んでおられる……と直感したことは、これまでに何度かございます。
決定的なのは山内先生がメールに書いてくださった次のひと言――《大江さんは、研究社出版が出していた英語学・英文学の専門月刊誌『英語青年』を精読していて、同誌には学会誌、紀要、同人誌を網羅した論文書誌が掲載され、それを通して英文学界の動向に目配りができていたところがすごいと感嘆します》。そこで考えますのは、やっぱり大江さんは――バランスというものがありますでしょう?――「英文学界の動向」だけでなく「仏文学界の動向にも目配りができていた」のじゃないか、ということ。本当に、ただもう、ひたすら感嘆するしかありません。
長くなりました。唐突ながら、本日はここまでとさせていただきます。


2023年8月12日 工藤庸子








