12月26日に、EAAの授業Modern Classics, East and West(東西文明学)の最終授業があり、履修者による発表が行われた。授業は学部生向け(履修者は主に2年生)で、毎週指定されたテキストをあらかじめ読んだ上で、テキストを読み込み、それをベースとして議論するものであった。テキスト講読および議論は、基本的に英語で行われた。テキストとしてはMichel Foucaultの”What is Enlightenment”、Walter Benjaminの“Comments on the Poems of Brecht”、”The Task of the Translator”、魯迅の『狂人日記』『故郷』、竹内好『近代とは何か』などが扱われた。
発表では、最終レポートの内容やその方向性について各自披露した。最終レポートの提出前にアウトプットを行い、議論やフィードバックを通してより良いものへと修正することを目的とした。そのためこの発表は、各自が現段階で考えていることを、たとえ中途半端な状態で煮詰まっていなくても、とにかくアウトプットするための場となった。
具体的には、各自がこれまでの授業を踏まえ、何かしらのテキストを読み、それについて自由に論じた。履修者は、これまで色々なテキストを講読する中で、その読み方、また色々な考え方に触れてきた経験を活かし、その内容や方法論を、個々の興味関心に沿って自分なりの考えを展開した。

最初の発表者は、Giorgio AgambenにおけるContemporaryという概念を踏まえつつ、自分なりの意見を自由に、かつ楽しげに展開した。Displacement, contradiction, creativityといった別の概念と結び付けることで、何か新しい考えにたどり着くことができるのかという模索が行われた。発表者は、哲学を研究として続けることを考えており、自分の考えを作り上げる練習をしたいという意図のもと、テキスト自体の解釈にとどまらず、他の概念との共通点・相違点を考察した。一方で、先行研究との類似性について指摘されるなど、今後の課題も明らかになった発表だった。

2番目の発表者は、尾形亀之助(1900-1942)の詩を、(政治的)抵抗の視点、contemporaryの観点から読解することを試みた。尾形の作品は、ある意味で凡庸な内容で、政治的抵抗を前面に押し出した詩が見られた当時においては変わった作風であり、その作風が全く違った形での抵抗になっていたのではないだろうか、ということを指摘した。
発表者の問いは、竹内好や魯迅が言うところの「抵抗」との相違点から、尾形の「抵抗」を論じられないか、というものであった。具体的に、最大の相違点として“hopeless”という観点について指摘した。竹内好や魯迅においては、現状がどうしようもないと認めつつも、何かしら抵抗すること・挑戦することを価値あることとして捉えられていたのに対して、尾形亀之助の詩では、現在の状態・今ちょうど感じていることが書かれているのみで、そこには将来についての記述はなく、ましてはhopeについて何も書かれていない。発表者は、この点こそが、むしろ何かしら新しい形での抵抗になっているのではないだろうかと論じた。また発表者は、韓国の詩人の生涯を描いた映画を見て、植民地支配下で政治的に間接的に詩を通じて抵抗する姿を見て、それとは対照的な尾形亀之助の詩が却って気になったというエピソードを話した。
発表に対して、実際のところ尾形亀之助は抵抗に成功したのかどうか、成功したとすればどう示すのか、という指摘が出た。着想・発想が面白い一方で、これを論理的に示す大変さをひしひしと感じる結果となった。

最後の発表者はエクソフォニー(Exophony)について論じた。エクソフォニーは母語の外に出た状態一般を指すことである。発表者は、外国語によって自己表現や他者表現を綴る、つまり外国語で文学を創ろうとすることについて議論した。日本人でありながらドイツ語でも文学作品を発表している多和田葉子のエッセイを元に、母国語以外で表現することそのものの可能性について、翻訳に関する議論を交えつつ発表した。
発表中、多和田葉子の興味深い翻訳が紹介された。空港のterminalを「民なる」と訳したという。発音を共有しつつ、「その地に降り立つことでその国にいる人となる」という意味を持たせた翻訳である。このような音や意味を拡大することを含む、様々な弾力性を有するような言語体験が語られていると、発表者は指摘した。
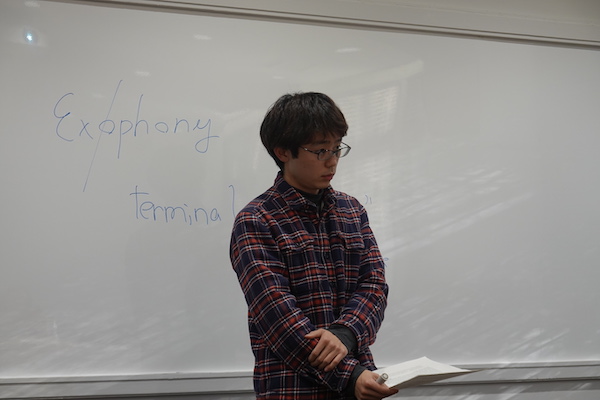
多和田は『エクソフォニー』の中で「ある言語で小説を書くということは、その言語が現在多くの人によって使われている姿をなるべく真似するということではない。(中略)むしろ、その言語の中に潜在しながらまだ誰も見たことのない姿を引き出して見せることの方が重要だろう。そのことによって言語表現の可能性と不可能性という問題に迫るためには、母語の外部に出ることが一つの有力戦略になる」と述べており、これは授業で取り上げたBenjaminの「翻訳者の使命」と類似するところがある。翻訳が言語の可能性を拡大しうるように、エクソフォニーという母語の外部へ出て言語表現すること、文章を書き、話をすることは、言葉に新しい可能性をもたらすだろう。
発表後には、各自が本授業への感想を述べた。哲学を扱うような授業が少なく(特にPEAKの授業では)、また、一つ一つのテキストを深く読むような授業も新鮮だったという意見が見られた。また、授業内での議論では背景に関係なくお互いが尊重されるということが良かったという声や、時には理解が難しいこともあったが、一方で抽象的に物事を考えるきっかけを得ることができてためになったという声が聞かれた。学部生という早い段階で、Modern classicsに触れつつ、テキストとしっかり向き合うような読み方に触れる良い機会となったのではないだろうか。
報告者:野波新(総合文化研究科修士課程/EAA TA)








