2020年12月28日(月)15時より、第3回『天下的当代性』を読む会がZoom上で開催された。当日の参加者は、石井剛氏(EAA副院長)、ヴィクトリヤ・ニコロヴァ氏(総合文化研究科修士課程)、および孔德湧氏、王嘉蔚氏、籔本器氏と報告者の円光門(以上4名はEAAユース)の計6名である。
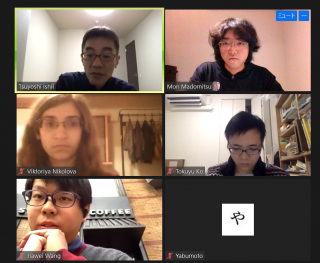
前2回で趙汀陽『天下的当代性――世界秩序的実践与想像』(中信出版集団、2016年)を読み終えたため、第3回となる今回は、各参加者が本書全体に関する疑問点を提示し、石井氏からコメントをいただくという会になった。
まず円光が、趙汀陽の提唱する「天下」概念に基づいた世界秩序と、実際の中国共産党/政府が掲げる外交政策との関連性はどこまであるのかという疑問を提起した。石井氏は両者の関連性については不明確であるとした上で、もし関連があるとすれば、それは「学問と政治の距離関係をどう認識すべきか」という問題につながるものだと述べた。一般的に、哲学者が政府の政策を正当化する議論を展開することは、「学問と政治の癒着」として批判的な文脈で語られることが多い。だが石井氏によれば、学問と政治の関係は、前者が後者に取り込まれているか否かといった二分法で捉えきれるものではなく、より複雑なものである。 『孟子』の中に、学問の役割は「王者の師となる」(為王者師)ことであるという一節があるが、この「王者」というのは、ただ1つの「国家」ではなくそれら全てを含めた「天下」を代表する者である。顧炎武は『日知録』の中で、国家は滅びても天下が滅びるわけではないとして両者を明確に区別した。つまり、学者が貢献すべき対象は前者ではなく後者なのである。このように考えると、趙汀陽が「天下」概念に基づいた世界秩序を提唱したことは、たしかに中国政府の外交政策に関わるものではあるかもしれないが、それが志向するのは中国という一国家に限られるものでは決してないのではないかと、石井氏は語った。
次に孔氏が(1)趙汀陽は「天下」を全てが内部化された外部性なき世界であると定義するが、外部性を排除している時点でそうした外部性を持つことにはならないだろうか、(2)「天下」は中心を持たない秩序だとされているが、そもそも中心なき秩序というものは可能であるのかという2点を質問した。石井氏は第1の問いに対し、「天下」はそれをより高次から説明し得るようなメタ的な原理を持たない、いわば神学的な議論であるため、内部性が外部性によって規定されるといったようなカール・シュミットやミシェル・フーコーによく見られる議論とは全く異なるレベルに位置しているのだと答えた。第2の問いに関しては、たしかに中心の克服というのは難しい問題であり、日本においても、「近代の超克」や高山岩男『世界史の哲学』(岩波書店、1942年)で展開された議論が「無」という概念を持ち出して中心を克服しようと試みたものの、結果的に失敗している。このように、中心を理論的に克服すること自体はできないかもしれないが、「天下」というのは常に革命の可能性を内包した、支配者の永続性を否定するシステムであるから、こうした可能性を担保していくことが、中心の持つ弊害を上手くなだめていく方法なのかもしれないと石井氏は述べた。
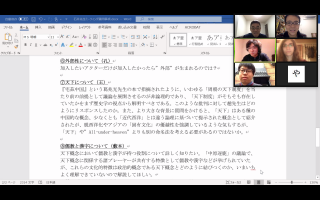
最後に籔本氏が、「天下」における漢字の役割とはどういうものかと尋ねた。具体的には、人が漢字を通じて世界を記述する際、人の精神が世界を見るのと同時に漢字もまた世界を見るのであり、故に漢字は「天下」が創造される際の重要な要素であるという議論が本書196-197頁でなされているが、これはどのような意味なのかという質問である。石井氏は、本書の「倉頡が文字を造った時、鬼神が夜に泣いた」という王充『論衡』が引用された箇所(本書181頁)に着目し、漢字が発明されたことで鬼神が泣いたのは、人間が文字を手にしたことでもはや魔術に惑わされることがなくなったからであると解説した。その上で、人間が漢字を使用する様子を趙汀陽が「摂魂」(魂を食らう)という言葉で表現したことを石井氏は指摘し、漢字を書くということは、魂=魔術的なものを食らうような仕方で客観的な世界を記述することであると説明した。すなわち、漢字を用いる人間は、魂=魔術的なものを食らうことによって、鬼神を斥けることで、自らが魔術を司る鬼神となったのである。こうして人間が得た魔術とは、歴史を記述することで世界を創造することのできる能力のことだと石井氏は語る。つまり「天下」という世界は、漢字が存在してこそ成立するものなのだ。
これに対してヴィクトリヤ氏は、歴史を記述することで世界を創造するという機能は、漢字だけでなく文字全般について言えることではないか、漢字とその他の文字の差異はどこにあるのかと尋ねた。石井氏いわく、漢字とアルファベットの決定的な差異は表意文字と表音文字の差にあるが、20世紀初頭までは、アルファベットのような表音文字とは音、すなわち発話者の声によって表される文字であるため、声=ロゴスに合致する論理的な文字だとされてきたのに対し、表意文字である漢字は音と切り離された形で表されるため、ロゴス的、論理的ではない文字だとされてきた。中国が近代化する過程で漢字廃止論を唱えた呉稚暉や銭玄同は、まさにこうした議論の提唱者である。このように声が文字に優位するという考え方は後にジャック・デリダによって「ロゴス中心主義」として批判されるようになるが、趙汀陽が漢字の強みであるとするのは、まさに漢字が音と切り離されているという点である。つまり、漢字は音と切り離されているからこそ、高い包摂性を持つのであり、異なる音声の言語を用いる民族も漢字を通じて共通のコミュニケーション媒体を持つことができるのである。このようにして、漢字の存在が異なる民族を結び付け、包摂的で外部性のない世界、すなわち「天下」を可能にすると趙汀陽は論じているのではないかと、石井氏は最後に述べた。
以上の質疑応答をもって、第3回『天下的当代性』を読む会は終了した。ご多忙にもかかわらずお越しいただいた石井氏には深く感謝を申し上げたい。EAAユース第1期生が中心となって発足したこの読書会は今回でひとまずの区切りを迎えるが、今後もさまざまな書物について学生間で議論する場をつくっていきたいと考えている。
報告者:円光門(EAAユース第1期生)








