2020年10月14日(水)、研究員・RAスタッフによるはじめてのEAA ブック・トークが実施された。EAAスタッフによる研究活動の一環として多言語ブックレビューのコーナーを立ち上げるに先立ち、全体的なレビューの方向性と企画への期待をシェアする機会として設けた集まりである。
当日の参加者は、髙山花子(EAA特任研究員)、若澤佑典(EAA特任研究員)、建部良平(EAAリサーチ・アシスタント)、張瀛子(EAAリサーチ・アシスタント)、そして本報告執筆者の前野清太朗(EAA特任助教)である。集まった企画者たちがこれからレビューを通じて展開することを望むリベラルでオープンな学術空間を象徴する場所として旧第一高等学校寄宿寮(駒場寮)跡をえらび、その前での「青空トーク」をセッティングした。

ブック・トークを企画するにあたって、5名の参加者であらかじめ申し合わせてそれぞれが「読みどころ」をアピールしたい数冊の本を持ち寄ってもらった。持ち寄られた本は下記の通り(紹介順)。
・アンダーソン, B.(著)、加藤剛(訳)(2009)『ヤシガラ椀の外へ』NTT出版
・阿辻哲次(1985)『漢字学――『説文解字』の世界』東海大学出版会
・大江健三郎(2013)『晩年様式集 イン・レイト・スタイル』講談社
・熊代亨(2020)『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』イースト・プレス
・王甫昌(著)、松葉隼,・洪郁如(訳)(2014)『族群――現代台湾のエスニック・イマジネーション』東方書店
・長谷川まゆ帆(2004)『お産椅子への旅――ものと身体の歴史人類学』岩波書店
・五来重(1976)『仏教と民俗 仏教民俗学入門』角川書店
・Blanchot, M. (1971) L’Amitié. Gallimard.
・箭内匡(2017)『イメージの人類学』せりか書房
・クローチェ, B.(著)、上村忠男(訳)(1988)『思考としての歴史と行動としての歴史』未来社
・カー, E.H.(著)、清水幾太郎(訳)(1962)『歴史とは何か』岩波書店
・デュモン, F.(著)、伊達聖伸(訳)(2016)『記憶の未来 伝統の解体と再生』白水社
・Lowenthal, D. (1985) The Past is a Foreign Country. Cambridge University Press.
本を持ってくることじたいは申し合わせていたが、どういった本を各自持ってくるかは当日まで調整はしていなかった。しかし期せずして関心のクロスする本を持ち寄ることになった。もっとも「関心のクロス」を見いだせたのは、ネゴシエーティブに互いの関心を探り合うブック・トークならではの成果であったかもしれない。各々持ち時間15分で持ち寄った本の「読みどころ」を語り、それに続けて他のメンバーが話を展開していったのであったが、紹介される本が積み重なるにつれて、先の話題とのつながりが広がって新しい視角が生まれる経験は非常に心地よいものであった。

個別の本についての「読みどころ」の紹介は今後のレビューに期待するものとして、その代わりに各々の本をきっかけに広がった話題についていささか触れておきたい。報告者のみるところ概ね2つのテーマについて話題が広がりをみたように思う。1つには学問する人の自己認識の問題、もう1つには過去について「書くこと」をめぐる問題であった。もっとも参加したスタッフはいずれも学問しかつ書く人間であるから、この2つも煎じ詰めれば自分たちの現在をそれぞれ解釈したいとの根本の動機に発したものであったかもしれない。
前者はB・アンダーソン『ヤシガラ椀の外へ』、箭内匡『イメージの人類学』、それから大江健三郎『晩年様式集 イン・レイト・スタイル』へ触れる中で出てきた話題である。ある学問への「外からの期待」と「中での議論の流れ」がしばしば一致しないなかでいかに学際的に生きていくか、アンダーソンが経験したような「梁山泊」的な空間がもつ可能性、あるいは絶えざる「晩年」のなかで自己をつねに再確定していく生き方について意見を交わした。
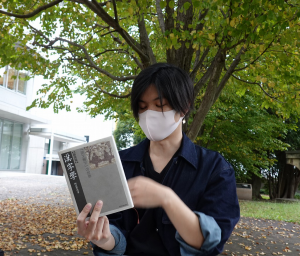
後者はとくに18世紀を研究フィールドとする3名(若澤・建部・張)が集っていたので、中華-西欧の学問的バックグラウンドをふまえた意見交換となった。人類学・民俗学・社会史に関するブックレビューも踏まえながら、「経」と「史」、「いにしえ」と「history」の間にあるずれと対立、中華的な枠組みと西欧由来の枠組みの不一致と齟齬に分析を広げる可能性に話が広がった。
インドネシアに「ヤシガラ椀の下のカエル」なる言い回しがあるという。あたたかい椀の中の心地よさにやがてそこを世界の全てと思い込むようになる、との「井の中の蛙」に似た意味のことわざである。しかし「ヤシガラ椀から出る」ことははたして辛いことなのであろうか? そして一旦そこを出たら戻ってきてはいけないのか? 決してそのようなことはないはずである。知を持ち寄って対話し、知をおのおのの「ヤシガラ椀」へ持ち帰る、そうした対話のハブ(hub)としての、心地よい「ヤシガラ椀の外」としての役割が「書院」的な場所がもつ知の可能性であると考えている。
報告:前野清太朗(EAA特任助教)








