近現代日本の名著を小国論や世俗と宗教を意識しながら2週間で1冊のペースで読んで議論していくこの授業では、年度が違っても同一著者は選ばないようにする不文律をぼんやりと自分のなかで立てていた。鶴見俊輔については昨年度すでに『戦時期日本の精神史』を読んでいるのだが、今年が生誕百年という理由で原則を崩し、『北米体験再考』を読むことにした。というより、彼は戦後日本を代表する知識人であるだけでなく、ある種の知識人を批判して大衆や民衆に向かった面も持ち、一大交差点を思わせる「ハブ的存在」として小国論や世俗と宗教という問題系においても核心にいる主要人物であると見えてきた(もう少し議論の手続きを踏まないと説得力を持たせることはできないかもしれないが)。私の選択眼自体がすでに影響を受けており、今後も鶴見の著作を取りあげる可能性はむしろ高い。
1971年刊行の『北米体験再考』は、鶴見俊輔(1922〜2015)の人生のほぼ折り返し地点に位置する著作で、若き日の米国留学時代(1938〜1942)を振り返りつつ、そのときに見えていなかったアメリカ合州国の姿を映し出そうと試みる。あの頃はわからなかったが、今ならわかる面がある。だが、もうすっかりわかったという態度では書かれていない。「自分がとらえることのできなかったものが何かを知ることをとおして、今、自分が何をとらえることができないかをさがす手がかりとしたい」という佇まいゆえ、鶴見自身の青年期の留学体験と執筆当時の認識を読者に向かって語る本書自体が、後年の再読をある意味で先取りしている。読者および著者に何度も再考を迫る性質の本である。
『戦時期日本の精神史』と『戦後日本の大衆文化史』のもとになった鶴見の講義を1979年から翌年にかけてモントリオールで受けた加藤典洋は、『アメリカの影』で文芸評論家としてデビューした。その彼は、鶴見を『北米体験再考』から読みはじめ、この本を何度も繰り返し読んだ。大教室ではなく小さな教室でのゼミ形式で行なった最終講義で読むのに選んだのも、やはりこの本だった(加藤典洋『言葉の降る日』)。これは、加藤が鶴見にいかに多くのものを負っているかの証言であると同時に、『北米体験再考』が再読を促す性質を帯びている本であることをよく物語っている。
本書は、留学当時のことを記した序章と執筆当時のことを記した終章が、三つの章をはさむ形で構成されている。若き鶴見俊輔が捕虜交換船で留学から帰国したのは、太平洋戦争の最中の1942年。本書の執筆はベトナム戦争の最中の1971年。米軍が撤退したアフガニスタンでタリバンが復権し、ロシア軍がウクライナに侵攻して戦闘が続く最中で迎えられようとしている鶴見生誕100年のいま、本書をどう読むことができるだろうか。

鶴見俊輔『北米体験再考』(岩波新書、1971年)。
米国留学時代の鶴見は大学や下宿先で、この国を支える理念とそれを体現する人びとに触れて暮らすことができた。その一方、米国市民ではない日本人である自分が、「敵国」となった米国の役人からどのような処遇を受けるのかも身をもって体験した。アメリカの留置所のなかで卒論を執筆した鶴見は、それでも「日本の留置場についてそのころまでに読んで知っていたことにくらべて、公平さがどこにも残っていた」と書いている。「このことは、米国のデモクラシーが日本人である自分には適用されないことを知った後にも、この国のデモクラシーがある仕方である人びとにとっては生きているという確信をもたせた」という。「監獄の中からその社会を見ることが、その社会にデモクラシーがどの程度にあるかを知る一つの方法になるだろう」と述べる鶴見の言葉は、監獄制度の視察に訪れて『アメリのデモクラシー』を著したトクヴィルの姿を思わせるが、現代日本のデモクラシーの度合いをはかる言葉としても重く響く。日本の敗戦を確信しながら、戦争に負けたときの日本にいなければと思って帰国した鶴見の感情には、屈折したところが見られる。占領下の日本で、ハーバード大卒の若き鶴見は有用な人材と目され勧誘を受けたが、「ほこらしい気もちで単純に占領軍の側に立てなかった」ためにその誘いを断った。ここにも「屈折した感情」が見られる。本書は日本が戦争に負けてから、アメリカおよび日本のある面と闘うために、アメリカの別の面を掘り起こそうとした企ての記録として読むことができる。


F.O.マシーセン『アメリカン・ルネサンス』上・下、飯野友幸ほか訳(上智大学出版、2011年)。
第1章で扱われているのは、文芸批評家のF・O・マシースン(1902〜1950)。父親は親から譲り受けた事業を潰してしまい、13歳のときに両親が離婚。資本主義の富が人間を腐らせるという思いを抱いたようである。イエール大学に学んだ頃にR・H・トーニーの『獲得社会』を読んで社会主義に目覚めた彼は、1929年の世界大恐慌を受けて北米の知識人が左傾化した時代の「典型的なニューデリー左派」を代表する。ハーバード大学教授という身分を持ちながら左派の政治的活動に取り組み、教員組合を作り労働組合とも接触した彼の姿勢は、それ以前のこの大学の教授格にはなかった態度である。鶴見がハーバードに学んだ頃は、彼の世代が大学教員の中核世代であり、同時代を代表する著述家たちでもあった。鶴見自身、マシースンの講演を聞いたことがあるという。社会主義者のマシースンはキリスト教徒でもあり、人間は間違いを犯しやすく神の愛の前にへりくだるべき存在であることの自覚は、社会主義や共産主義を絶対視することの歯止めとして機能した。第二次世界大戦から冷戦へと移る時代にあって、共産主義の理想はソヴィエトの独裁者が腐敗させ、民主主義の理想はアメリカの資本家が腐敗させたと論じた彼は、「個人と社会の双方に配慮するような、より十分な社会主義」を構想したが、マッカーシーの赤狩り旋風が吹き荒れるなかでホテルから身を投げて自ら命を絶った。マシースンと親交のあった詩人ロバート・オーウェルの詩の一節を鶴見は引いて、この文芸批評家が「同性愛の男」であったことが読者にわかるようにしてあるが、ハーバード大学教授にして民衆に近づこうとし、社会主義者にしてキリスト教徒であったこのマージナルな人物がセクシュアル・マイノリティでもあったことを、『北米体験再考』は前景化させていない。とはいえ、本書を収録してある『鶴見俊輔集1』の「著者自身による解説」では、社会主義者だったマシースンがFBIから「同性愛をばらす」という仕方で脅迫されていたことが記されている。
鶴見はマシースンの主著として『アメリカの文芸復興』(1941)を紹介している(現在は邦訳も出ている。F・O・マシーセン『アメリカン・ルネサンス』飯野友幸、江田孝臣、大塚寿郎、高尾直知、堀内正規訳、上下巻、上智大学出版、2011年)。アメリカではなぜ1850年〜55年という短期間に優れた文学作品が陸続と出現したのかという問題設定のもとに書かれたこの本は、エマソン、ソロー、ホーソーン、メルヴィル、ホイットマンを取りあげているが、前四者はマサチューセッツ州のコンコードに住んだ。若き鶴見も、コンコードの予備校の寮で過ごしたことがある。その予備校の先生が、エマソンを賞賛する日本人に出会ってその人から自分が書いたという本をもらったと鶴見に語ったことがある。その本の著者は暁烏敏で、天皇への忠誠を説く内容だった。それで鶴見は相当に困ったらしい。エマソンと言えば、個人の内面を重視する精神主義の立場に立ち、偉人を特別視するエリート主義的な見方を批判し、自然を讃美して人びとの平等を説いた民主主義者である。一方、暁烏敏は清沢満之の門下生で精神主義を説き、大正時代には親鸞の教えを大衆に広めて人気を博したが、昭和時代に入ると皇道と真宗信仰の一体性を説くようになる(島薗進『国家神道と日本人』第1章はこの話で幕を開ける)。鶴見が困ったのは、エマソンの民主主義と昭和時代の暁烏敏が説いた天皇中心主義は対極的であるはずなのに、なぜかつながってしまうことである。
受講生のS・Nさんは、親鸞と浄土真宗の教えの中心には阿弥陀如来があり、世俗権力やその他の神々にしたがわない神祇不拝の考えがあるにもかかわらず、絶対他力は思考停止に陥る危険も秘めているのではと指摘した。そして「親鸞の思想そのもののなかに、全体主義的な日本主義と結びつきやすい構造的要因があるのではないか」と中島岳志が『親鸞と日本主義』(2017)において提起した問いを紹介し、絶対他力の信仰が、天皇崇拝に行き着くメカニズムについて説明を加えてくれた。
*
第2章は、悪人面をしているが実は心の温かい善人という西部劇映画の主人公に熱中した大正期の日本人が、映画の「背景」に「あらあらしい未開の民としてあらわれるインディアン」についてはよく見ていなかったのではないかという反省的な問題意識から、ネイティヴ・アメリカンの世界観の豊かさと、その知恵に学ぼうとしてきたアメリカ人の系譜を掘り起こす。デフォー『ロビンソン・クルーソー』を、フライデーの観点から語り直したミシェル・トゥルニエ『フライデーあるいは太平洋の冥界』(1967)などを髣髴とさせる。
新大陸に渡ってきたロジャー・ウィリアムズ(1603〜1683)は、本国の英国国教会に対しては断固として手を切るよう主張したが、キリスト教の宗派は人間が考え出したものにすぎず、あらゆる宗派を平等に扱うべきであると説くとともに、法的権威と宗教的権威を結びつけてはならないとも述べた。また、北米の土地はインディアンのものであるとの考えを表明した。ジョン・ロックが『寛容についての手紙』(1689)で政治と宗教の領域の分離を説いたのは、ウィリアムズより一世代あとである。また、ロックは「自由な人間」を人格・身体・土地の「所有」の観点から構想しており、これは新大陸への入植と土地所有を正当化する思想ともなった(西谷修『アメリカ――異形の制度空間』講談社選書メチエ、2016年)。
授業参加者のH・Tさんは、ロジャー・ウィリアムズが説いた政教分離と寛容論はロックの時代に先駆けていただけでなく、無神論者も寛容の対象に入れている点で、ロックよりも寛容の度合いが高いようにも見えると指摘した。また、ウィリアムズはネイティヴ・アメリカンの言語を習得して『アメリカ現地語案内』(1643)を書いており、前回読んだ茅辺かのう『アイヌの世界に生きる』との類似点があるのではと発言した。
S・Kさんも、鶴見が引用する本田勝一『アメリカ合州国』に紹介されているプエブロ・インディアンの「部落長」の次の言葉から、アイヌの世界観との共通点を思い出したと述べた。「動物たちも、神から授かったひとつの命しか持っていません。あなたも、私も、この点は同じことです。それを白人どもは、自分が生きるための食物としてでなく、スポーツとして殺そうというのです。私たちも動物を殺すことがありますが、それは神の与え給うた聖なる食物としてか、でなければ神聖な儀式のときに限られています。儀式のときは、皮も毛も角も内臓も、すべて宗教的意味を持った聖なる目的に使われるのです」。
ゲリー・スナイダー(1930年生まれ)は、大学で文化人類学を専攻し、「アメリカ・インディアンの宗教にある、いろいろの行をした」。父親が木こりだったスナイダーは、子どものころから森で馬や牛と一緒に暮らした。「動物と一緒にいると、動物と人間とは、あまりかわりがないことがわかる」。来日した彼は京都の禅寺で修行をした。鶴見とも何度か会っている。宮沢賢治の翻訳も手がけている。こうしてスナイダーはコロンブス到着「以前」の北米から伝わる文化の火を蘇らせようとしていると鶴見は言う。
1971年刊行の本書で鶴見は、「北米にいた時にも、その後も、私は、アメリカ・インディアンに会ったことがない」と述べているが、1972年から翌年にかけてメキシコに滞在した際にはヤキ族のもとを、そして1979年から翌年にかけてケベックに滞在したときにはモホーク族のもとを訪れている。カナダで先住民運動の代表者と会ったときには、いきなり「あなたはインディアンだ」と呼びかけられた。「私はそういう期待にそうことができればうれしいのだが、そうなれないだろうと思ってはずかしかった」(「二つの国を見わたして――カナダの居留地」)。この「はずかしかった」という鶴見の感覚を理解するのはなかなか難しいが、日本人としての自分は本当にインディアンに近いのか、むしろ西部劇の主人公のほうに近いのではという葛藤が、ここには読み取れるのではないだろうか。
*

第3章は、留学時代の自分が、リンカンの奴隷解放以来、北米の黒人は選挙権を与えられたと信じており、アメリカ社会における黒人に対する人種差別を十分に理解していなかったことへの反省から書かれている。1960年に結成されたスニック(SNCC:学生非暴力調整委員会)は、黒人差別に対する反対を唱える公民権運動組織として生まれた。初代委員長マリオン・ベアリは、非暴力という宗教的理想を行動様式に据えた。1966年には当時の委員長ストークリー・カーマイケルが「ブラック・パワー」を提唱した。ベトナム反戦運動にも加わり、米国に出かけていた小田実がSNCCのハワード・ジン(1922〜2010)とラルフ・フェザーストーン(1939〜1970)を日本に連れてきた。1965年に小田実と高畠通敏と一緒にベ平連を結成した鶴見は、1966年にジンとフェザーストーンを連れて日本列島を北海道から南へと縦断する講演キャラバンに通訳として福岡まで同行した。沖縄は当時いわゆる本土復帰前の米軍統治下で、本土の日本人であるベ平連メンバーは渡航できず、ジンとフェザーストーンを送って講演会を開いてもらった。米国に帰国する前にフェザーストーンは鶴見に「日本は、沖縄と沖縄以外の部分と、その二つにわかれている」と印象的な言葉を残した。「フェザーストーンは、黒人として彼のもっている直観で、沖縄の聴衆には、北米における黒人と同じく圧迫されたものの要求を感じとった」のだろうと鶴見は推し量っている。1969年、スニックはSNCCの頭文字はそのままで、組織名を「学生全米調整委員会」に改めた。Nが “nonviolent” から “national” に変わったことは、「大国」(great power)ないし「超大国」(superpower)として君臨し国内外で暴力を行使する「神の下のひとつの国」(One nation under God)たるアメリカ合州国に「黒人の力」(black power)に依拠するもうひとつのネイションの存在を印象づける効果を持つ一方で、非暴力主義路線の限界を露呈するものとも解釈しうる。そうしたなかで、翌1970年にはフェザーストーンが自動車に爆弾を仕掛けられて死亡したニュースが鶴見のもとに飛び込んできた。
第3章で論じられるもう一人の名はエルドリッジ・クリーヴァー(1935〜1998)。ロサンジェルスの黒人街で育ち、「自転車泥棒をふりだしに、マリファナふかし、白人女性強姦など」で16歳から30歳頃まで監獄を出たり入ったりしていた。監獄の壁に「白人の女」の写真を貼っていたところ、看守に剥がされ、貼るのが「黒い女」なら眼をつぶってやると言われて、あるひとつの認識に達した。自分は黒人なのに、北米で育って「白人の美の規準を心の底にまでたたきこまれていることに気づいた。これでは、黒人は、幸福になりようもないではないか」。「強姦をとおして自分の憎しみを白人の女にぶつけるという行為は、自分自身を自分にとっていやなものにした」。「人間を憎むことの代価は、それだけ自分自身を愛せなくなるということなのだ」。黒人男性は白人女性を「抱く」ことで「奴隷制をかけのぼってその頂上にたつ錯覚」を抱くが、そのような黒人男性は白人に対しては「政治的に去勢された男」になり、黒人に対しては「性的に去勢された男」となる。
想起したのは、ハイチ出身の作家ダニー・ラフェリエールの『ニグロと疲れずにセックスする方法』(立花英裕訳、藤原書店、2012年)で、精力絶倫の黒人男性が良家の白人女性たちからモテまくるという舞台設定である。一見不思議に見えるかもしれないが、西洋の価値観では、白人男性、白人女性、黒人男性という序列があるために、白人女性は黒人男性で性的要求を満たす構造があることを主人公の黒人男性は見抜いており、性的魅力を梃子として人種の階層秩序を転倒することを画策している。もうひとつ思い出したのは、ラファエル・リオジエが『男性性の探究』(拙訳、講談社、2021年)において、女性を所有しようとする男性の志向性が、めぐりめぐってかえって男性を惨めにするメカニズムが存在すると指摘していることである(リオジエを囲んでの連続討論会の報告はこちら)。
なお、クリーヴァーはブラック・ムスリムの信者で、マルコムXを先人と仰ぎ、SNCCとも関係する黒豹党から1968年に大統領選に立候補している。アナーキスト人類学者のイルコモンズは、それからちょうど40年後の2008年にバラク・オバマが「米国史上初の黒人の大統領」になったことに黒人の目から見た「米国史」を透視し、いずれさらにもうひとつの『北米体験再考』が書かれるべきだと主張している(「あなたのきいているのとは別のもうひとつの太鼓をきく」『鶴見俊輔――いつも新しい思想家』河出書房新社、2008年)。
現在の文脈で本書第3章を読み直してすぐに念頭に浮かぶのは、やはりブラック・ライヴズ・マター(BLM)運動だろう。2013年にSNSのハッシュタグ(#BlackLivesMatter)として発生したこの運動は、前年に黒人少年を射殺した元警官が正当防衛で無罪判決とされたことを受けて、アリシア・ガルザ、パトリス・カラーズ、オパール・トメティが示した反応がもとになっているが、特定のリーダーのいない運動として知られている。2020年にはジョージ・フロイド氏が警官によって圧殺され、それに抗議するBLM運動は全米に、そして国境を超えて世界へと広がった。
現在の観点から、『北米体験再考』第3章を読み直して気になるのは、黒人女性の存在が希薄であることかもしれない。本書のさらなる「再考」のためには、交差性(インターセクショナリティ)の観点からも議論を掘り下げる必要があるだろう。「人種、階級、ジェンダーなどをめぐる権力関係は、別々に独立した相互排他的な存在ではなく、むしろ〔……〕相互に作用し合っている」(パトリシア・ヒル・コリンズ、スルマ・ビルゲ『インターセクショナリティ』小原理乃訳、下地ローレンス吉孝監訳、人文書院、2021年)。交差性の概念は黒人フェミニストの理論的実践に由来することが知られており、BLM運動においても人種や階級やジェンダーは別個のものではなく、複合的に絡み合うものとしてとらえられ、問題改善へのアプローチが探られている。
*
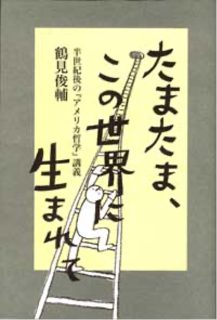
鶴見俊輔『たまたま、この世の世界に生まれて——半世紀後の「アメリカ哲学」講義』(編集グループSURE、2007年)。
アメリカの哲学と言えばプラグマティズムであり、鶴見の哲学の土台もプラグマティズムと言ってよい。「私は、プラグマティズムの哲学が帝国主義に奉仕する側面をもってきたことを認める。同時に、パース、ジェイムズ、ミードのプラグマティズムを、全体として帝国主義の哲学として捨てきれると思わない」。彼が、もうひとつのプラグマティズムのあり方を求めていることがわかる。それはアメリカの伝統に基づきながら、帝国主義への回収やイデオロギー的な硬直に陥ることを避け、現状の改善に向けて今を生きることに焦点を合わせる哲学である。1960年代の黒人の活動家たちが「かれらの抑圧された経験の中から自分の権利を見出してゆく方法に、今日の私にとってもっと重大なプラグマティズムがあらわれているように思える」という本書での鶴見の言葉は、今日の格率としても妥当であるはずだ。
『たまたま、この世界に生まれて――半世紀後の『アメリカ哲学』講義』(SURE、2007年)は、鶴見の最初のまとまった本『アメリカ哲学』(1950)を、ルイ・メナンドの『メタフィジカル・クラブ』(原書は2001年刊行、野口良平・那須耕介・石井素子訳、みすず書房、2011年)と重ね合わせながら読む座談会形式の本である。これらを読むと、プラグマティズムが南北戦争の戦後思想として19世紀末に生まれていることがわかる。敗北した南軍だけでなく、勝利した北軍も深い傷跡を負った。
その傷をもとにした共感が、おそらく鶴見のプラグマティズムの核心部分にある。もうひとつ、鶴見のプラグマティズムを構成する要素として重要なのは、同調しない権利ではないかと思う。プラグマティズムはアメリカの伝統に深く根ざしている哲学ゆえ、19世紀末の「誕生」を待たずに、プラグマティズム以前のプラグマティズムがあると考えるのが妥当である。本書でも鶴見は「プラグマティズムは、フランクリンからエマソンまでの著作の中に、すでに骨格をあきらかにしている」と明言している。ベンジャミン・フランクリンは資本主義の父のイメージが強いが、鶴見は彼に先住民族から学ぶ知恵を持ち合わせていた人物をも見ている。また、エマソンとその仲間たちは「不同調の自由」を大切にする社会を作ることを望んでいたと述べている。「傷をもとにした共感」さえもが同調圧力になるときには、「不同調の自由」に立て籠ることが「傷をもとにした共感」を立て直す手がかりになる。
*
終章「岩国」には、心温まる話が紹介されている。1971年5月5日の子どもの日。ベ平連が子どもたちに呼びかけて、山口県の岩国で風船を飛ばし、凧揚げをする。これが、岩国基地から戦地ベトナムに向かって飛び立つ米軍機の離陸を妨害する効果を持つ。警官たちが山口県全体からかき集められたが、統率が取れていない。なかには「凧あげなら、君たちよりもうまいぞ」と言って、米軍機を飛び立てなくする凧を子どもたちと一緒に揚げてくれる警官までいた。凧揚げが終わったあとに開かれた河原での反戦集会には、基地を抜け出してきた米軍兵士も混じっていた。
たしかに、警察や軍隊は統率が取れていないと困る組織の最たるものだろう。しかし、戦争は嫌だという感覚を持つ者が、命令を下される者や命令を下す側の者に皆無であることのほうがもっと困る。統制で雁字搦めにはなっていないある種のゆとり、それが暴力への逸脱と向かうのではなく、のどかさへと向う余地は、今でも残されているだろうか。
受講者のN・MさんとK・Mさんの2人が、本書を読んでそれぞれ別々に、しかし互いに示し合わせたかのように、終章にある次の言葉に打たれたと伝えてくれたことを記しておきたい。「普通に誰でもがもっている、他の人間を殺したくないという感情が、国家の法規よりも優先する条件をつくりださなくては、今の行きづまりから人間が逃れることはできないのではないか」。半世紀前の鶴見俊輔の言葉が今もなお響くようである。
報告者:伊達聖伸(総合文化研究科)








