2022年12月22日、第7回の藝文学研究会が開催された。今回のテーマは、「20世紀の東アジアにおけるベールの受容」である。発表者の劉玲芳氏(東京大学東洋文化研究所/日本学術振興会特別研究員PD)は、中華民国期の新聞雑誌を手がかりに、西洋からの舶来品であるベールが中国や日本でどのように受容されたのかについて、現段階の調査結果を共有した。
1910年代初頭、「文明結婚」という時代の風が中国古来の結婚式にも舞い込んできた。当時洋風的とされた要素であったベールを花嫁衣裳に取り入れることは、男性のように完全に洋装することが難しい当時の女性にとって、自分は文明的であるということをアピールするために必要であったと推察できる。1930年代以降、「集団結婚」という倹約合理的な結婚式が求められたことや、会社や新聞の広告が広めた新しい花嫁のイメージが、ベールの利用を促していった。もちろん、こうした受容は突然に起こったことではない。1910 年代の改良されたツーピースの上衣下裙から1920 年代末のチャイナドレスとベールの組み合わせへという様式の変化、そして赤、桃色から純白へという色の変化のように、新しい文化の受容は常に伝統の編み直しの中で行われている。中国に比べて、日本におけるベールは花嫁のアイテムというより、流行品として受容されたと考えられる。
ベールは多重の象徴的意味をもっており、興味深い研究対象であるに違いない。一方、近代における服装・儀礼の変化に関してはすでに多くの研究がある。そうした中、ベールの受容史をどのような視点で掘り下げたら、我々の近代・身体・礼儀の関係に対する理解が深まるのであろうか。それを考察するための観測点がディスカッションの中で浮かび上がった。たとえば、顔隠しの伝統の有無がベールの受容に与えうる影響、民族の多様性に萌す「中洋折衷」の曖昧性、女性のアイデンティティおよび社会的期待の再構築に関するベールの役割などが挙げられる。本研究会は、たくさんの緊張関係に立ち向かっていた百年前の女性が、人生の最も華やかしい儀式に、軽いベール一枚を自らの頭に被ることの重さを感じさせる機会となった。

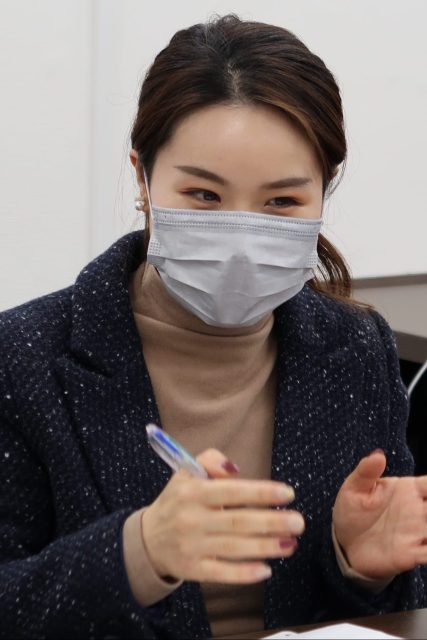



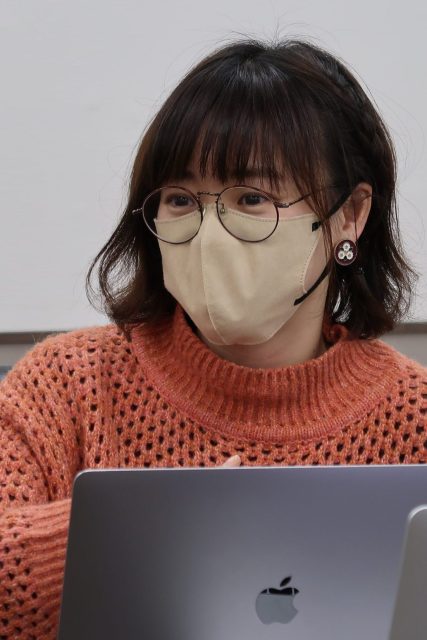
報告:汪牧耘(EAA特任研究員)








