2021年2月26日、第6回101号館映像制作ワークショップが開催された。緊急事態宣言発令中のため、前回(第5回)同様、今回もオンラインでの開催となった。リサーチ・アシスタント3名(高原智史氏、日隈脩一郎氏、小手川将氏)による報告に対し、高山花子氏(EAA特任助教)と崎濱紗奈(報告者:EAA特任研究員)がコメントする形で会は進行した。
高原氏からは、当時の寮日誌に関する報告がなされた。氏は、とりわけ「茶話会」に関する記事に注目することで、留学生自身の声を浮かび上がらせることを企図している。高原氏によれば、1930(昭和5)年や1935(昭和10)年頃の資料からは、特設高等科への要求を伝える記事などを通して、留学生側からの反応を窺い知ることができる。
続いて小手川氏からは、氏が撮影した、駒場キャンパス内の梅や金木犀の映像が共有された。以前のワークショップで、石井剛氏(EAA副院長)から、101号館の前にも植えられている「梅」は、「牡丹」と並んで中華文化圏において極めて重要な意味を持つ花であるという指摘がなされた。これを受けて小手川氏は、今まさに咲き誇る梅の花をカメラに収めてくれた。

駒場キャンパスの梅(撮影:小手川将氏)
日隈氏は、1887年に刊行が開始された雑誌『哲学雑誌』を読み進めていると報告した。日隈氏が着目したのは、当時、一高と東京帝大の教員を兼任していた桑木厳翼(1874−1946)の存在である。特設高等科に関する直接的な関わりを洗い出すというよりは、当該雑誌に掲載されている論文・授業報告等を通して、一高をめぐる当時の雰囲気を窺い知ることが目的である、と氏は述べた。
3名の報告のあと、高山氏からは、1954年2月の『教養学部報』(1951年創刊)が紹介された。ここには、藤木邦彦(1907−1993)の筆による101号館(当時の通称は「特高館」であったらしい)にまつわる記事が掲載されている。藤木邦彦が遺した膨大な文書=「藤木文書」の整理は、宇野瑞木氏(EAA特任研究員)と高原氏を中心に昨年度より進められてきた一高プロジェクトの主要な活動の一つとして取り組まれてきた。

教養学部報28号(1954年2月)
今回高山氏が紹介した記事からは、藤木が一高、とりわけ特設高等科に特別な思いを寄せていた様子を窺い知ることができた。以下の文章を引用したい——「特設高等科は、昭和二十四年の学制改革で、一高とともにその姿を消したが、その間通計二百余名の優秀な中国人(戦後はさらに朝鮮人も)留学生を教育した。彼らは日常駒場寮で日本人学生と同居して、交情まことにこまやかであったし、今日なおその友情が続いている実例を私はいくつも知っている。特高館こそは、善隣友好の精神を象徴する、ひとつのささやかな記念碑ともいい得る」。
1932(昭和7)年に講師として一高に着任し、1942(昭和17)年には留学生課長に就任した藤木氏は、日中戦争・太平洋戦争の開戦から日本の敗戦という激動の時代の一高に居合わせた人物である。興味深いことに、上に引用した短い文章には、1945年から学制改革までのわずか数年のうちには、朝鮮半島出身の学生も「留学生」として特設高等科に在籍していた事実が触れられている。植民地支配からの「解放」期、朝鮮戦争前夜の半島からやってきた学生が「朝鮮人留学生」としてここに姿を現している。前回のワークショップでは、朝鮮半島や台湾出身の学生——1945年以前、「植民地」であったがために、制度上「留学生」としては扱われてこなかったであろう学生——の存在を念頭に置くことの重要性も指摘されたが、この短い一文から、こうした問題系につながる手がかりを得ることができた。
藤木が「善隣友好」の「記念碑」と呼んだ特高館=101号館に、現在東アジア藝文書院がオフィスを構えていることは、石井氏がつとに指摘してきたように、得難い良縁であると言えよう。しかし一方で、スタッフ間で議論されてきたように、その時代背景には、日本の帝国主義と、それへの抵抗運動としての抗日愛国運動といったように、両者の間には緊迫した関係性があったことも、同時に忘却されてはならない。抗日という思想的態度と、日常生活における日本人学生との交流・友情との間で、引き裂かれる思いを抱えて当時を過ごした留学生や植民地出身の学生も数多くいたであろう(そして、「沖縄」や「アイヌ」といった出自を持つ、「辺境」という立場に立たされた学生もいたであろう)。
資(史)料的制約はあるものの、幸い今回の映像制作には、完全なるドキュメンタリーではない、ある種の「文学」的語りを導入する余地が含まれている。一枚岩では語りきれない間(あわい)をどのように表現するか、今後の焦点になりそうである。最後に、小手川氏から、男子学生のみのホモソーシャルな空間から、学制改革により男女共学となったことがもたらした(あるいは、もたらされなかった)ドラスティックな変化についても着目し、必ずしも滑らかな連続性を持たない、一高と現在の教養学部を繋ぐ凸凹な歴史を念頭に置く必要性が指摘されたことを付言しておく。
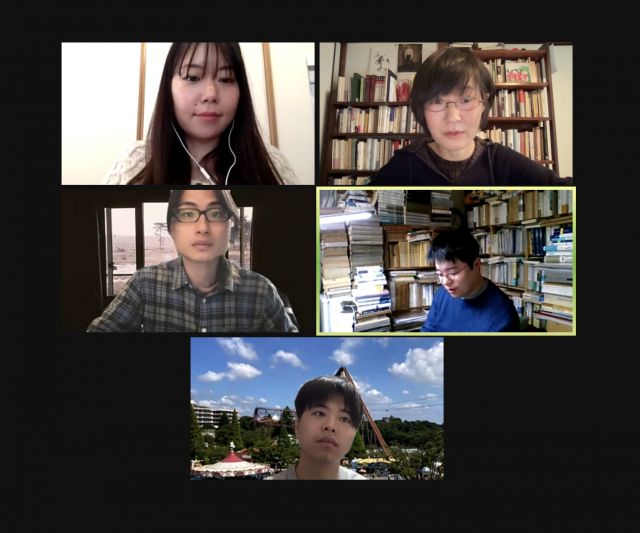
報告者:崎濱紗奈(EAA特任研究員)








