2021年2月15日(月)15:00より第14回石牟礼道子を読む会が開催された。発表担当者は髙山花子氏(EAA特任助教)で、このほかに、張政遠氏(東京大学大学院総合文化研究科)、山田悠介氏(大東文化大学)、佐藤麻貴氏(東京大学連携研究機構HMC)、宮田晃碩氏(東京大学大学院総合文化研究科博士課程)、建部良平氏(東京大学大学院総合文化研究科博士課程)、そして報告者の宇野瑞木(EAA特任研究員)の7名が参加した。
本読書会では、昨年6月から『苦海浄土』3部作を読んできたが、その後にメインテクストに据えたのが、前回から読んでいる『流民の都』(1973年)である。『流民の都』は、石牟礼がある時点まで『苦海浄土』の第4部にすることを想定していたことがわかっている。今回は『苦海浄土』を共同で読んできた今年度の締めくくりの会となることもあって、髙山氏の発表は、『流民の都』から浮かび上がってきた「みやこ/都」「流民」という新たな視点をもって、『苦海浄土』3部作を振り返るという総まとめ的な内容となった。
今回、メインテクストに選ばれたのは、『流民の都』(大和書房、1973年)の中でも特に、下記の2篇である。
1.「流民の都1」(初出『現代の眼』1972年4月号)
2.「もうひとつのこの世へ」(初出『告発』第13号、1970年6月、『人間として』第3号、1970年9月、原題「断章苦海浄土」)
またサブテクストは、以下の通り。
1.水溜真由美「石牟礼道子と「流民」」、『現代思想』2018年5月臨時増刊号、186-193頁)
2.宮本久雄『旅人の脱在論――自・他相生の思想と物語りの展開』(創文社、2011年)より第2部第8章抜粋(253-260頁)
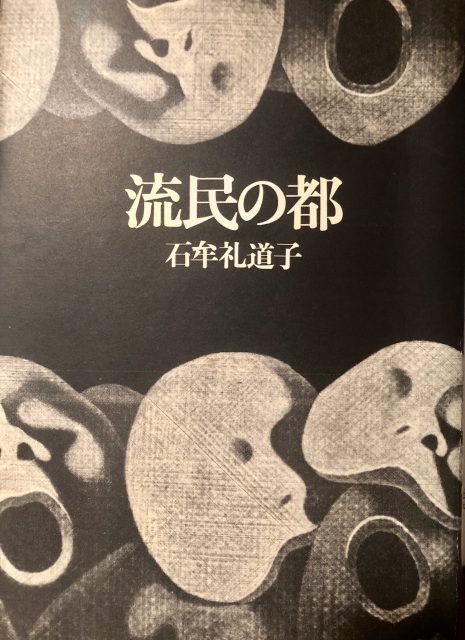
石牟礼道子『流民の都』(大和書房、1973年)。表紙は水俣で石牟礼と親交のあった銅版画家・秀島由己男の作品。
まず、髙山氏は「流民の都1」について論じられた水溜論文を参照しながら、石牟礼のいう「流民」の背景として、石牟礼が育った水俣の村周辺では、石牟礼の家を含め天草や薩摩から流れてきた人たちが多かったこと、また彼らは学歴のないために周縁的な労働者にしかなれなかったにもかかわらず、会社(=チッソ)の発展を喜び「都人」としての幻想を抱く人々であったことが確認された。さらには、貧困ゆえにマレーシアなどへ売られていった天草の女性たちや、南米・南洋への移住を試みた後に戻ってきて水俣に住みついた天草出身者たちをもごく身近に感じていたこと等が指摘された。
以上を踏まえて、「流民」「都」、また「故郷」がいかなる意味をもたされていたか、3部作において改めて確認する作業がなされた。第1部においては、ゆき女などの主要な登場人物が天草流れであると自ら語っていること、このときの「都」は会社(=チッソ)のできた水俣という流れ者からなる村のイメージが強かったことが確認された。これに対して、第2部では、新たに出郷した者も故郷に留まった者も行き場がなく、石牟礼自身も故郷にいながら「もうひとつのこの世」を希求する状況が描き出されるようになる。また「みやこ」として京都や大阪、さらに東京が語られるようになるが、東京は風土や季節と切り離された「造花」のイメージであると共に、かつての「みやこ」は「長崎」であったことが注目された。さらに東京のチッソ本社前に座り込みをする場面から始まる第3部では、「都/みやこ」は明確に東京を表す言葉となり、天皇のいる場で、自然との乖離や無名性といった特徴が示されていた点が確認された。また、一貫して「流れ」という言葉には「舟」や「流木」のような海を漂流するイメージがあることも明らかになった。
その上で、もうひとつのサブテクストである宮本論文「たましい(魂・anima)への旅」において、「苦海浄土」の「浄土」が存在の母層すなわちアニマの母層であり、その場所では「国家」の「国」ではない「くに」へ繋がっていくものであるとする議論が参照され、この「アニマ」の「くに」と石牟礼の希求する「もうひとつのこの世」との関係が検討された。最後に、故郷にいながらにして故郷を喪失するような時代への眼差しが、胎児性水俣病患者の逃げ場のなさと重ねられながら、まぼろしのみやこではなく、国家や行政区分とも別の場を求める動きへと向かったとし、「相思社」という具体的な活動の場を実現した点に着目を促して発表を終える形となった。
質疑では、「流民」「流れ」というキーワードについて、現代にまで続く差別の構造、移民・難民の問題、また石牟礼が傾倒した高群逸枝の女性史観と絡めて近代以前の日本社会における女性の地位や宗教的呪術的な面における特権的な在り方、さらには天草や長崎の遊女の問題など、さまざまな方向から議論がなされた。また長崎という天皇制とは直接関係しない、中国やオランダと結びついたかつての都の影響下にあった天草・水俣あたりの土地では、国家の境界を越える海によって繋がる圏域・海路のイメージをもっていたこと、さらにそうした海からみた圏域では、女性が執り行う祭祀が残る南島の習俗や航海を見守る媽祖などの女神信仰に近しいものを感じていたのではないか、といった点も指摘された。
さらに「流れ」という流動性が、『苦海浄土』では常に陸上の移動ではなく海上で潮に流されるイメージであることに着目し、かつては流刑が死刑に次ぐ重刑であったように縁なき土地に流され帰る場所を失うことの耐えがたさ・苦しみの深さへの注意が促された。その一方で、小説において「海」から陸を眺める眼差しを様々なレベルで内包していることの意味が示唆され、例えば漁師は「海の上」というもうひとつの場所から陸地すなわち日常・現実を眺めることのできる浄土性・異界性を享受したといえるのではないか、といった指摘もなされた。
現実と異なる位相に漂わせてくれる海上という両義的な場は、石牟礼の短歌時代から一貫して思念の場であった(そしてそれは家や結婚に拘束される身から魂が漂浪きだす場でもあったであろう)「空と海のあいだ」のイメージにも通じているように思われる。そして、海を介して繋がるのは空間だけではなく、『苦海浄土』に生命の源の破壊の上に現われた「竜宮」、あるいは失われた「生類のみやこ」というまぼろしの古代の時間でもあったのだろう。もちろん、こうした超地上性への希求や甘美なノスタルジーが生命の病の上に現われるものであるとも言及されていたことに注意しなければならない。そして、一方では髙山氏が述べたように現実世界にもうひとつの共同体を具体的に現出させようと動いていたことも注目される。その内実については今後の課題であるだろう。
以上のように、『苦海浄土』第4部となることが当初は想定されていた『流民の都』のテーマである「流民」「都」といったテーマから、もう一度3部作を眺めたことで、その視点が、水俣の風土を決定づける重要な意味を持ち続けたと同時に、石牟礼自身が移動や親交の範囲を拡げていくなかで、3部作を通じてかなり意味が変化・拡大していったことも明らかになった。また、これまでの読みでは、「漂浪(され)き」といった言葉を旅、巡礼などと結びつけて考えてきたが、そこには舟で潮にのって流れていくような陸上の移動とは異なるイメージがあることが新たに確認されたことで、海からの視点という「私」「わたくし」とは別の、あるいは分離した視点からの読みがより可能になったように思われる。
宮本久雄氏は、石牟礼のその後の作品は『苦海浄土』の注釈であると述べているが、そうした問題意識にも触発されながら、石牟礼の残した多様な作品において、その世界がどこに向かっていくのか、その行方について共に議論して行きたいと改めて感じた。
報告:宇野瑞木(EAA特任研究員)








